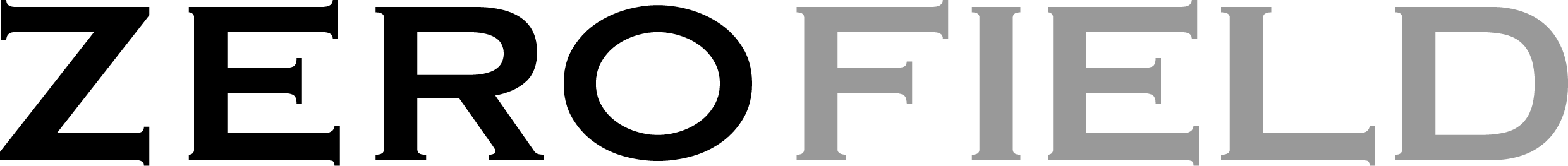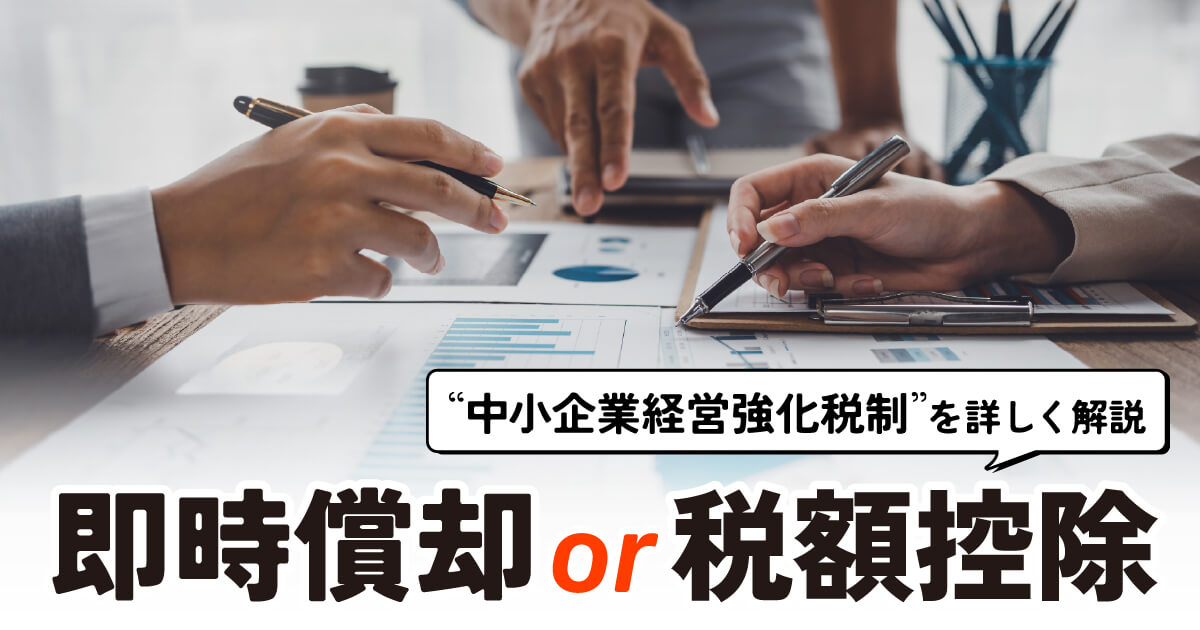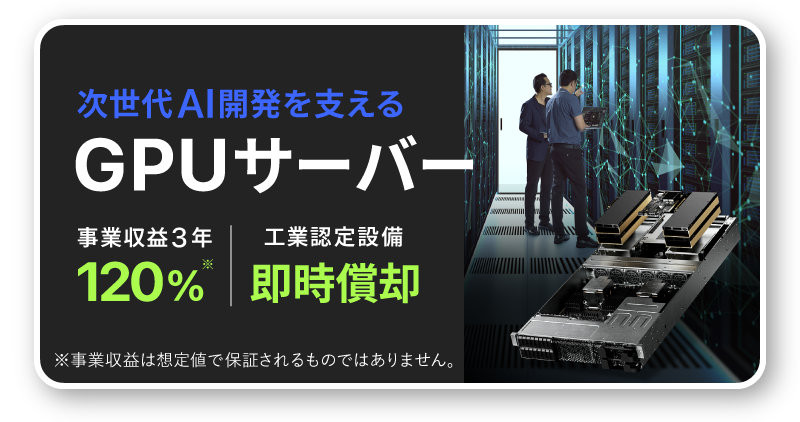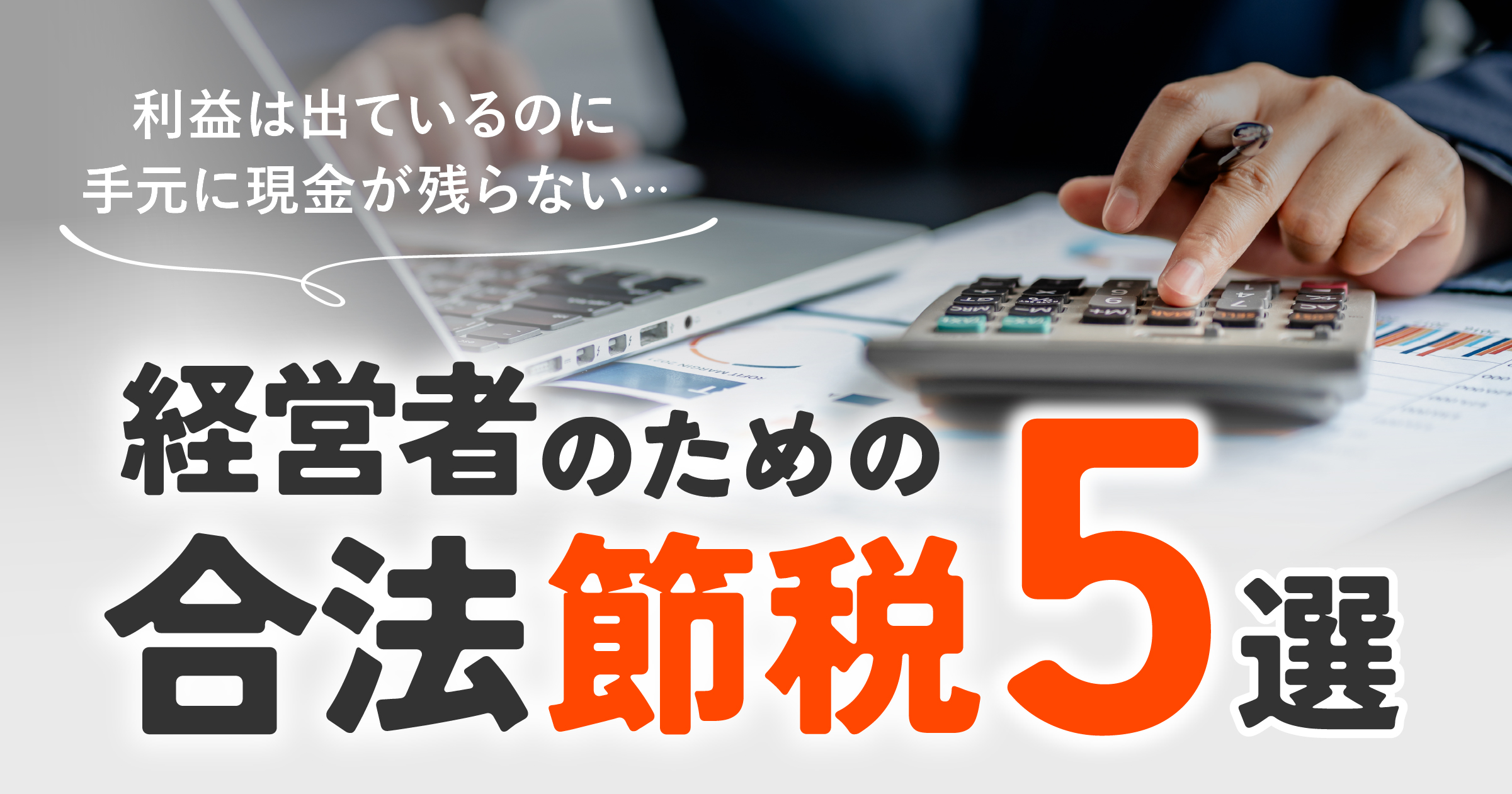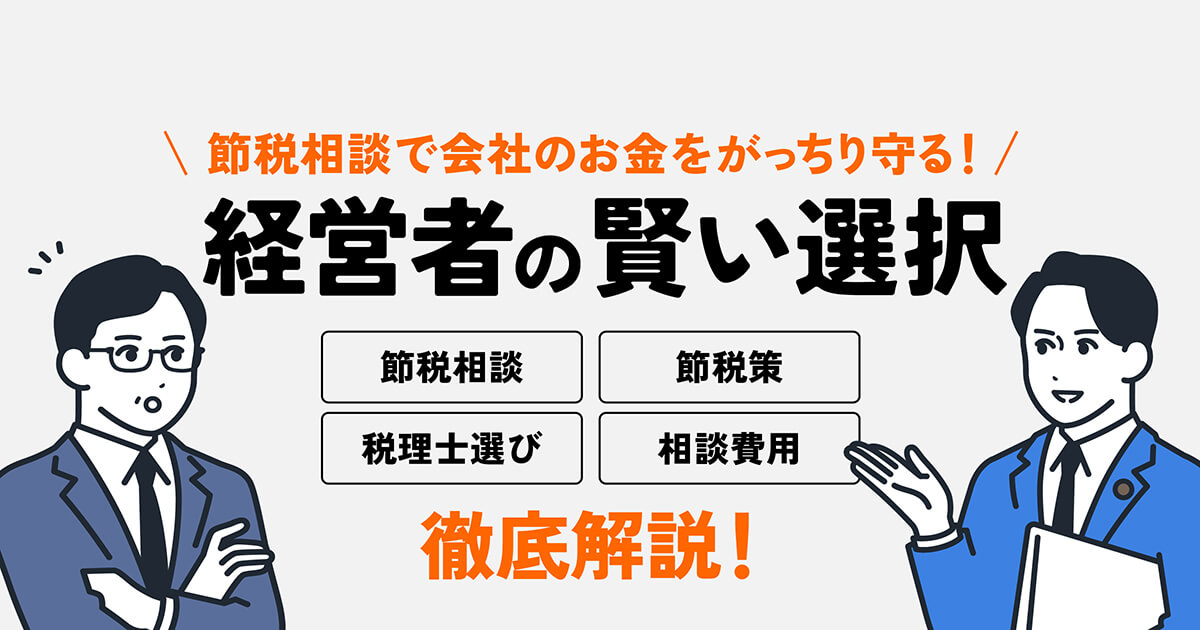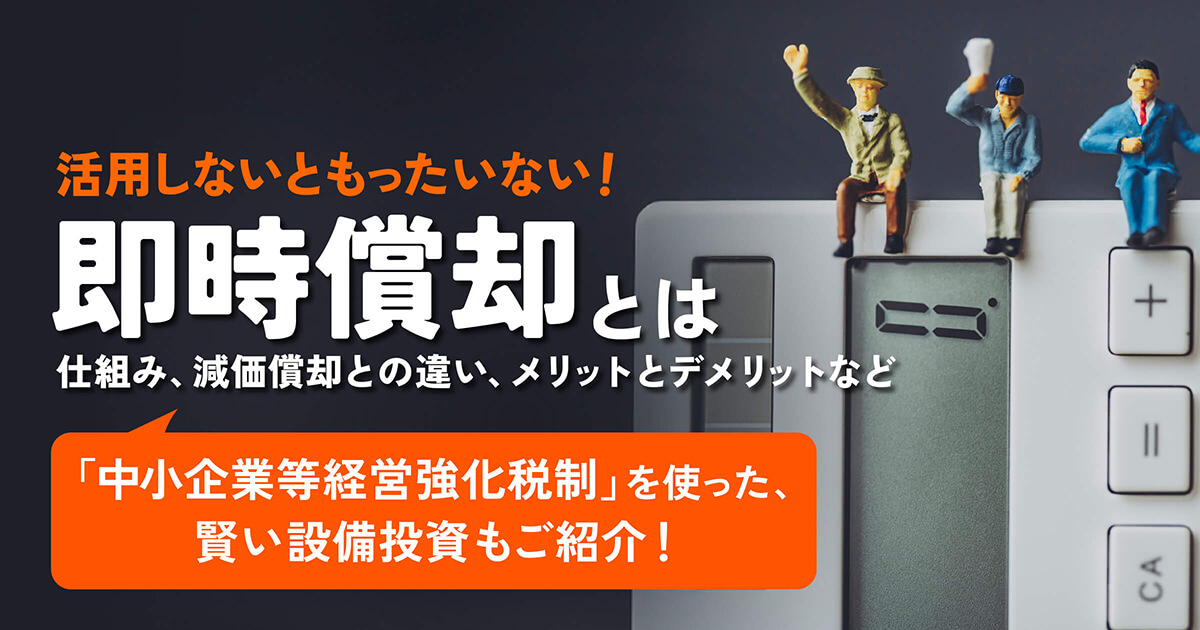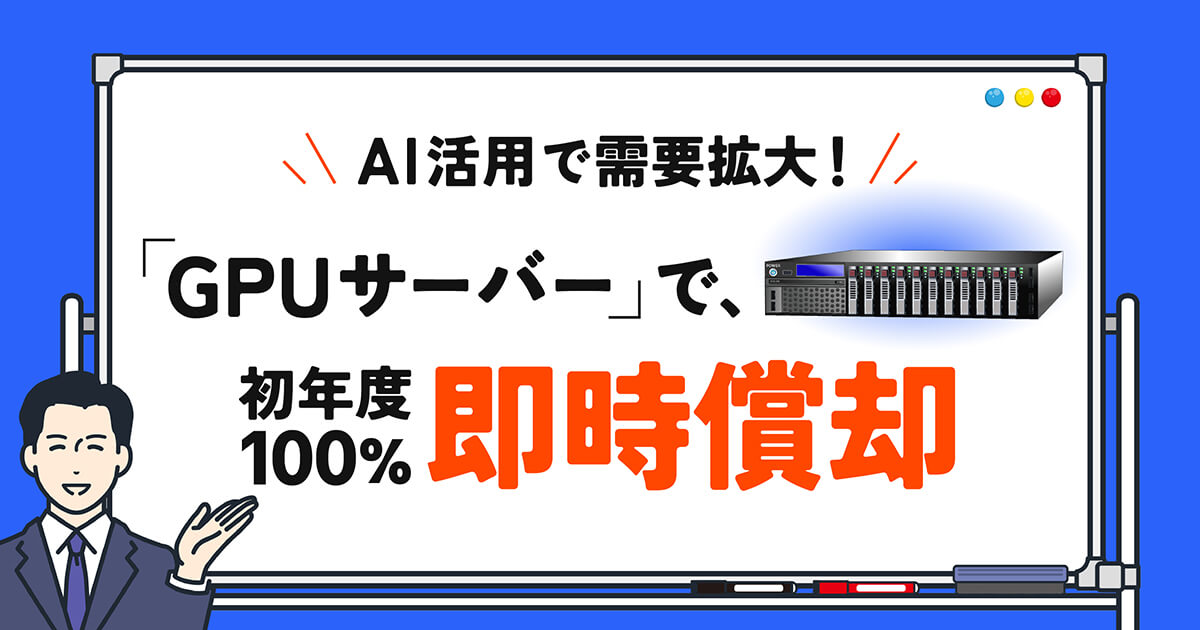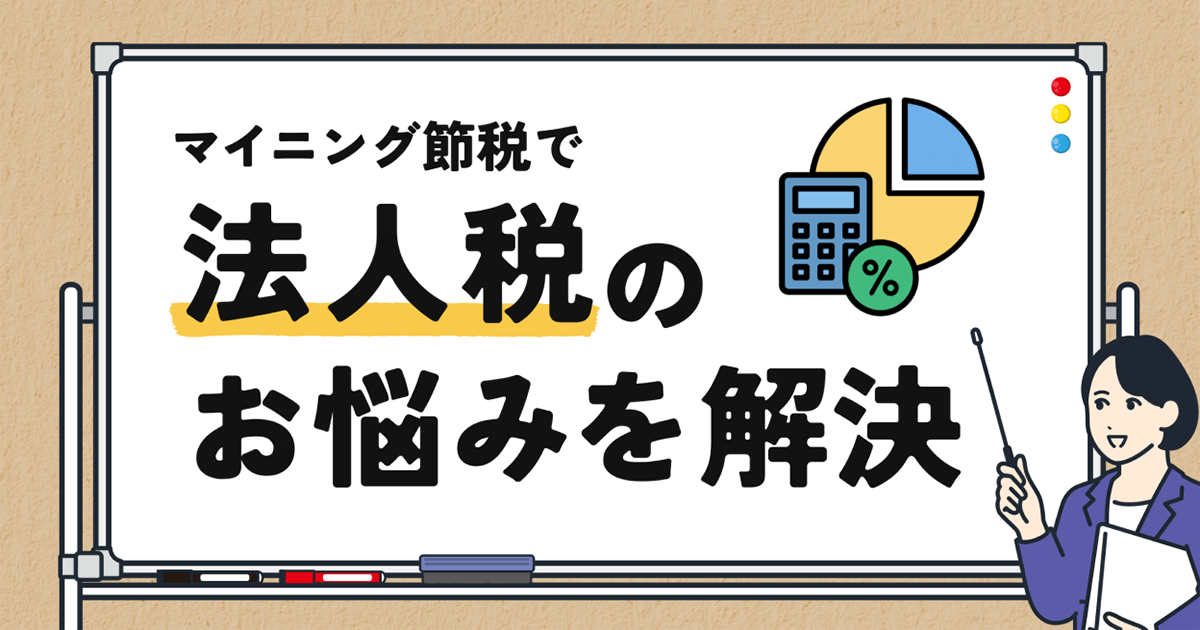中小企業の設備投資を強力に支援する「中小企業経営強化税制」。本記事では、制度の概要や対象要件、申請手続きの流れを網羅的に解説します。特に重要な選択肢である「即時償却」と「税額控除」について、どちらが自社にとって有利なのかをメリット・デメリット、ケース別のシミュレーションを交えて徹底比較。この記事を読めば、制度を最大限に活用し、賢く節税する方法がわかります。
中小企業経営強化税制とは 設備投資を支援する税の優遇措置
中小企業経営強化税制とは、中小企業の設備投資を促進し、生産性の向上や収益力の強化を後押しするために設けられた税制上の優遇措置です。具体的には、国から「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業が、特定の設備を取得した場合に、取得価額の全額をその年の経費として計上できる「即時償却」、または取得価額の最大10%を法人税額(または所得税額)から直接差し引ける「税額控除」のいずれかを選択適用できる制度です。厳しい経済環境の中で、積極的な投資に踏み切れない中小企業にとって、非常に強力な支援策といえます。
この制度を活用することで、設備投資に伴う初年度の税負担を大幅に軽減し、キャッシュフローを改善させることが可能になります。その結果、新たな投資や事業拡大への再投資がしやすくなり、企業の持続的な成長をサポートします。本制度は、単なる節税対策に留まらず、企業の競争力を根本から強化するための戦略的な一手となり得る重要な制度です。
1.1 制度の概要と目的をわかりやすく解説
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法という法律に基づいて実施されています。この制度の主な目的は、中小企業が抱える人手不足、老朽化した設備の更新、デジタル化(DX)の遅れといった経営課題を、新たな設備投資によって解決し、「稼ぐ力」を向上させることにあります。政府は、この税制優遇を通じて中小企業の積極的なチャレンジを促し、日本経済全体の活性化を図ることを目指しています。
制度のポイントを以下にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 中小企業経営強化税制 |
| 対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主など) |
| 適用要件 | 「経営力向上計画」の認定を受け、対象となる設備を取得・事業供用すること |
| 優遇措置 | 以下のいずれかを選択 即時償却(取得価額の100%を損金算入) 税額控除(取得価額の7%または10%を税額から控除) |
| 根拠法 | 中小企業等経営強化法 |
| 管轄 | 中小企業庁 |
この制度を利用するには、まず自社の経営課題を分析し、それを解決するための具体的な目標や設備投資計画を盛り込んだ「経営力向上計画」を策定し、事業分野に応じた主務大臣の認定を受ける必要があります。計画の認定が、税制優遇を受けるための第一歩となります。詳細については、中小企業庁のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。(参考:中小企業庁:経営強化法による支援)
1.2 適用期限は延長
中小企業経営強化税制の適用期限は延長され、事業の用に供した設備が対象となります。税制改正によって延長されています。
注意すべき点は、この期限が「経営力向上計画の申請期限」ではなく、「対象設備を取得し、実際に事業で使い始める期限」であるということです。経営力向上計画の認定には、申請から1ヶ月〜2ヶ月程度の期間を要する場合があるため、設備の導入を検討している場合は、十分に余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが極めて重要です。
特に、高額な設備や納品に時間がかかる特注品などを検討している場合は、発注から納品、設置、稼働開始までの期間を逆算し、早急に計画策定と申請手続きに着手することをおすすめします。期限直前になると申請が集中し、認定までに通常より時間がかかる可能性も考えられます。この貴重な機会を逃さないよう、計画的な準備を心がけましょう。
中小企業経営強化税制の対象となる企業と設備
中小企業経営強化税制は、すべての企業が利用できるわけではありません。この制度を活用するためには、対象となる「中小企業者等」の条件を満たし、さらに国が定めた特定の「設備」を導入する必要があります。ここでは、自社が制度の対象となるか、また導入を検討している設備が要件を満たすかを確認するための詳細を解説します。
2.1 対象となる中小企業者の条件
本税制の対象となるのは「中小企業者等」です。具体的には、青色申告書を提出する法人または個人事業主のうち、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 対象法人・個人 | 資本金または出資金の額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 資本金または出資金を有する法人 | 1億円以下 | – |
| 資本金または出資金を有しない法人 | – | 1,000人以下 |
| 個人事業主 | – | 1,000人以下 |
| 協同組合等 | (企業組合、協業組合、事業協同組合など) | |
ただし、資本金が1億円以下であっても、大規模法人(資本金1億円超の法人など)から2分の1以上の出資を受ける法人や、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人などは対象外となります。これを「適用除外事業者」と呼びますので、自社の資本関係は必ず事前に確認してください。
2.2 対象となる設備の種類 A類型からD類型まで
中小企業経営強化税制の対象となる設備は、その目的や性質に応じて「A類型」から「D類型」までの4つに分類されています。どの類型に該当するかによって、申請時に必要な書類や手続きが異なります。自社が導入する設備がどの類型に当てはまるか、それぞれの要件を確認しましょう。
2.2.1 A類型 生産性向上設備
A類型は、企業の生産性を高めるための設備が対象です。「一定期間内(10年以内)に販売が開始されたモデル」であり、「生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する」という2つの要件を満たす必要があります。この要件を満たしていることは、設備を製造したメーカーを通じて、各設備に関する工業会等から証明書を取得することで証明します。
| 資産の種類 | 最低取得価額 | 備考 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | – |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | – |
| 器具備品 | 30万円以上 | サーバー、パソコン、複合機など |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 空調設備、昇降機など |
| ソフトウェア | 70万円以上 | 業務効率化ツール、CADソフトなど |
2.2.2 B類型 収益力強化設備
B類型は、企業の収益力を強化するための設備が対象となります。年平均の投資利益率(ROA)が5%以上となることが見込まれる投資計画を策定し、その計画が経済産業大臣(経済産業局)の認定を受ける必要があります。コンサルタントや金融機関などの専門家による事前確認を経て申請する点が特徴です。
対象となる資産の種類と最低取得価額はA類型と同様ですが、B類型では、この投資計画に記載された設備が税制優遇の対象となります。主に、新規事業や海外展開など、大きな投資効果が見込まれるプロジェクトで活用されます。
2.2.3 C類型 デジタル化設備
C類型は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための設備が対象です。具体的には、事業プロセスの「遠隔操作」「可視化」「自動制御化」のいずれかを可能にする設備が該当します。この類型もB類型と同様に、経済産業大臣(経済産業局)の認定を受けた投資計画に記載されていることが必要です。
対象資産はソフトウェア(70万円以上)、機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)などで、クラウド技術を活用したサービス利用料も対象に含まれる場合があります。詳しくは中小企業庁の「経営強化法による支援」のページで最新情報をご確認ください。
2.2.4 D類型 経営資源集約化設備
D類型は、M&A(合併・買収)などによって経営資源の集約化(事業承継等)を行った後に、その効果を高めるために導入する設備が対象です。修正ROA(営業利益+減価償却費)/総資産)または有形固定資産回転率が一定割合以上向上するという要件を満たす投資計画を策定し、経済産業大臣(経済産業局)の認定を受ける必要があります。
この類型は、事業承継やM&Aをきっかけとした設備投資を後押しすることを目的としており、計画の実現性が重視されます。
2.2.5 GPUサーバー(A類型)
近年、AI開発やビッグデータ解析の需要拡大に伴い、高性能なGPUサーバーへの投資を検討する企業が増えています。このGPUサーバーも、中小企業経営強化税制の対象となる可能性があります。
多くの場合、GPUサーバーはA類型「生産性向上設備」の「器具備品」に該当します。この税制優遇を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 取得価額が30万円以上であること
- 生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上すること
- 設備メーカーを通じて、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)などの工業会から証明書を取得すること
GPUサーバーは高額な投資になることが多いため、この税制を活用することで初期投資の負担を大幅に軽減できる可能性があります。導入を検討する際は、まずサーバーの販売店やメーカーに、本税制の対象となるか、また証明書の発行が可能かを確認することから始めましょう。
即時償却と税額控除 選べる2つのメリット
中小企業経営強化税制の最大の魅力は、企業の状況に合わせて「即時償却」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択できる点にあります。これらは設備投資に伴う税負担を軽減するための強力な支援策ですが、その仕組みと効果は大きく異なります。どちらか一方の選択制であり、併用はできません。自社の財務状況や将来の事業計画を踏まえ、最適な選択をすることが節税効果を最大化する鍵となります。
ここでは、それぞれの制度の仕組みとメリットを詳しく解説します。
3.1 即時償却とは 取得価額の全額をその年の経費に計上
即時償却とは、通常であれば法定耐用年数に応じて数年間にわたって分割して経費計上(減価償却)する設備投資額を、取得したその事業年度に全額一括で経費(損金)として計上できる制度です。
例えば、1,000万円の設備を導入した場合、通常の減価償却では毎年少しずつ経費にしていきますが、即時償却を適用すれば、購入した年に1,000万円全額を費用として計上できます。これにより、その年度の課税対象となる利益(課税所得)を大幅に圧縮することが可能になります。
主なメリットは、設備を導入した年度の法人税負担を劇的に軽減し、キャッシュフローを大幅に改善できる点です。税金の支払いを先延ばしにする(課税の繰り延べ)効果があり、手元に残った資金を新たな投資や運転資金に回すことができます。特に、多額の利益が見込まれる年度に大きな設備投資を行う企業にとっては、非常に有効な節税策となります。
ただし、これはあくまで「課税の繰り延べ」である点に注意が必要です。初年度に全ての減価償却費を計上するため、翌年度以降はその設備に関する減価償却費が発生しません。その結果、翌年度以降の利益が通常よりも大きく計上され、税負担が増加することになります。長期的に見れば支払う税金の総額は変わらないものの、短期的な資金繰りを楽にしたい企業にとって大きなメリットがあります。
3.2 税額控除とは 算出された法人税額から直接控除
税額控除とは、設備投資額の一定割合を、算定された法人税額そのものから直接差し引くことができる制度です。経費を増やして課税所得を減らす即時償却とは異なり、税金そのものをダイレクトに減額するため、非常に強力な節税効果があります。
控除できる割合(控除率)は、企業の資本金の額によって異なり、以下の通り定められています。
| 対象となる中小企業者 | 控除率 |
|---|---|
| 資本金3,000万円以下の法人、または個人事業主 | 取得価額の10% |
| 資本金3,000万円超 1億円以下の法人 | 取得価額の7% |
例えば、資本金3,000万円以下の法人が1,000万円の設備を導入した場合、1,000万円の10%にあたる100万円を、その年度に支払うべき法人税額から直接差し引くことができます。これは税金を前払いする即時償却とは異なり、支払う税金の総額そのものを減らす「減税」効果があるのが最大のメリットです。
なお、控除額には上限があり、その事業年度の法人税額(または所得税額)の20%が限度となります。もし控除しきれない金額が発生した場合は、翌事業年度に1年間に限り繰り越すことが可能です(繰越税額控除)。そのため、利益が少ない年度や赤字の企業でも、将来の黒字化を見越して活用できる可能性があります。詳細な要件については、中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。(参考: 中小企業庁:経営強化法による支援)
【徹底比較】即時償却と税額控除はどちらを選ぶべきか
中小企業経営強化税制の最大の魅力は、「即時償却」と「税額控除」という2つの優遇措置から、自社にとって有利な方を選択できる点にあります。しかし、「どちらを選べば一番得なのか?」と悩まれる経営者の方も少なくありません。この章では、両者のメリット・デメリットを徹底的に比較し、どのような企業がどちらを選ぶべきかをケース別に解説します。具体的なシミュレーションを通じて、節税効果の違いも明らかにしていきます。
4.1 それぞれのメリットとデメリットを比較
即時償却と税額控除は、どちらも設備投資に伴う税負担を軽減する制度ですが、その仕組みと効果は大きく異なります。即時償却は「課税の繰り延べ」である一方、税額控除は「税金の直接的な免除」です。この根本的な違いを理解することが、最適な選択への第一歩となります。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 比較項目 | 即時償却 | 税額控除 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 課税の繰り延べ | 税金の免除 |
| 節税効果 | 初年度の税負担を大幅に軽減。ただし、翌年度以降は減価償却費がなくなるため、税負担は増加する。 | 支払うべき法人税額そのものを直接減額。複数年にわたるトータルの節税額で有利になる。 |
| キャッシュフローへの影響 | 初年度の納税額が大きく減るため、手元資金を厚くする効果が非常に高い。 | 法人税額から直接控除されるためキャッシュフローは改善するが、即時償却ほどのインパクトはない。 |
| 対象期間トータルの納税額 | 原則として変わらない(減価償却を前倒しするだけのため)。 | 控除額の分だけ確実に減少する。 |
| 赤字企業への影響 | 当期に法人税が発生しないため、直接的なメリットはない。ただし、赤字額(繰越欠損金)を増やし、将来の黒字と相殺することは可能。 | 法人税額が発生しないため、利用できない。 |
4.2 ケース別解説 即時償却がおすすめの企業
即時償却は、特に初年度の資金繰りを大幅に改善したい企業にとって強力な選択肢となります。以下のようなケースに当てはまる場合は、即時償却の利用を積極的に検討しましょう。
4.2.1 ケース1:今期の利益が想定以上に大きく出た企業
「今年は特別利益が出て、納税額がかなり大きくなりそうだ」という企業に最適です。即時償却を利用すれば、設備投資額の全額を損金として計上できるため、課税対象となる所得を大幅に圧縮できます。これにより、当期の法人税負担を劇的に軽減し、手元のキャッシュを確保することが可能になります。
4.2.2 ケース2:創業期や成長期で資金繰りを重視する企業
創業したばかりの企業や、事業拡大のために積極的に投資を行っている成長企業は、運転資金の確保が最優先課題です。設備投資で多額の資金を使った直後に、大きな納税が重なると資金繰りが厳しくなります。即時償却は、投資初年度の税負担を軽くすることで、貴重な現金を事業の成長に再投資することを可能にします。
4.2.3 ケース3:融資を受けたばかりで手元資金を温存したい企業
金融機関から融資を受けて設備投資を行った場合、返済が始まる前にできるだけ手元資金を厚くしておきたいものです。即時償却で納税額を抑えることができれば、その分を返済原資や不測の事態に備える資金として確保でき、経営の安定性を高めることにつながります。
4.3 ケース別解説 税額控除がおすすめの企業
税額控除は、長期的な視点で着実に節税メリットを享受したい企業に向いています。特に、毎期安定して利益を上げている企業にとっては、非常に有利な選択肢となります。
4.3.1 ケース1:トータルの納税額を確実に減らしたい企業
「目先のキャッシュフローも大事だが、最終的に支払う税金の総額を少しでも減らしたい」と考える企業には税額控除が最適です。即時償却が将来への「課税の先送り」であるのに対し、税額控除は法人税額そのものを直接カットする効果があります。これにより、設備の耐用年数全体で見たときに、最も大きな節税効果を得られます。
4.3.2 ケース2:毎期安定して黒字を計上している企業
毎年コンスタントに利益が出ており、急激な利益変動が少ない企業の場合、即時償却で初年度の税金を大きく減らすメリットは相対的に小さくなります。むしろ、毎年発生する法人税から着実に一定額を控除できる税額控除の方が、長期的かつ安定的な経営計画に合致すると言えるでしょう。
4.3.3 ケース3:税効果会計を適用している企業
税効果会計を適用している企業の場合、即時償却を行うと会計上の利益と税務上の所得に大きな差が生まれ、「繰延税金負債」を計上する必要が生じます。会計処理が複雑になることを避けたい場合や、貸借対照表(B/S)への影響を考慮する場合には、会計処理が比較的シンプルな税額控除を選択する方が管理しやすい場合があります。
4.4 シミュレーションで見る節税効果の違い
言葉での説明だけではイメージしにくい節税効果の違いを、具体的な数値でシミュレーションしてみましょう。どちらの制度が自社にとって有利かを判断するための参考にしてください。
【シミュレーションの前提条件】
- 取得した設備価額:1,500万円
- 法定耐用年数:10年(定額法、償却率0.100)
- 毎年の課税所得(減価償却前):3,000万円
- 法人税等の実効税率:30%と仮定
- 税額控除率:10%(資本金3,000万円以下の法人と仮定)※控除額は法人税額の20%が上限
この条件を基に、「通常償却」「即時償却」「税額控除」の3パターンで初年度と10年間のトータル納税額を比較します。(参考:中小企業庁:経営強化税制)
| 項目 | A. 通常償却の場合 | B. 即時償却の場合 | C. 税額控除の場合 |
|---|---|---|---|
| 初年度の減価償却費 | 150万円 | 1,500万円 | 150万円 |
| 初年度の課税所得 | 2,850万円 | 1,500万円 | 2,850万円 |
| 初年度の法人税額 | 855万円 | 450万円 | 705万円 (855万円 – 控除150万円) |
| 初年度の節税額(Aとの比較) | – | 405万円 | 150万円 |
| 10年間のトータル法人税額 | 8,550万円 | 8,550万円 | 8,400万円 |
| 10年間のトータル節税額(Aとの比較) | – | 0円(課税の繰り延べ) | 150万円 |
シミュレーションの結果から明らかなように、初年度のキャッシュフロー改善効果(節税額)は即時償却が圧倒的に大きいことがわかります。一方で、10年間という長期的な視点で見ると、税額控除の方が150万円もトータルの納税額を圧縮できています。この結果を踏まえ、自社が短期的な資金繰りを重視するのか、長期的なトータルコストの削減を重視するのか、経営戦略に合わせて最適な選択をすることが重要です。
中小企業経営強化税制を利用するための手続きと流れ
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、事前の計画策定と認定、設備の取得、そして確定申告という一連の手続きを正確に進める必要があります。特に、設備を取得する前に「経営力向上計画」の認定を受けることが大原則です。ここでは、制度利用のための3つのステップを具体的に解説します。
5.1 STEP1 経営力向上計画を策定し認定を受ける
最初に行うべきは、自社の経営力を向上させるための具体的な計画書「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることです。この計画には、自社の事業概要、現状認識、課題、目標、そして今回導入する設備がどのように生産性向上や収益力強化に貢献するのかといった具体的な取り組みを記載します。
計画書の様式は中小企業庁のウェブサイトからダウンロードできます。自社だけで作成するのが難しい場合は、税理士や中小企業診断士などの「認定経営革新等支援機関」に相談し、策定支援を受けることを強くおすすめします。
作成した計画書は、事業分野に応じた主務大臣(窓口は各地域の経済産業局など)に提出します。申請は原則として「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用した電子申請となります。申請後、審査を経て無事に認定されると「認定書」が交付されます。認定までには通常1ヶ月程度の期間を要するため、設備投資のスケジュールを考慮し、早めに準備を始めましょう。
詳細な手続きや申請様式については、中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。
中小企業庁:経営強化法による支援
5.2 STEP2 対象設備を取得し事業に使う
経営力向上計画の認定を受けたら、計画書に記載した対象設備を取得し、事業の用に供します(実際に事業で使い始めます)。必ず計画の認定日以降に設備を取得・設置する必要があるため、順番を間違えないように注意してください。
また、税制優遇の適用を受けるためには、その設備が制度の対象であることを証明する書類が必要です。取得する設備の種類(A類型~D類型)によって、必要な証明書類が異なります。
| 設備類型 | 必要な証明書類 | 発行元 |
|---|---|---|
| A類型:生産性向上設備 | 工業会等による証明書 | 設備を生産したメーカーが加盟する工業会など |
| B類型:収益力強化設備 C類型:デジタル化設備 D類型:経営資源集約化設備 | 投資計画に関する確認書 | 認定経営革新等支援機関(公認会計士、税理士など) |
A類型の設備を導入する場合は、設備メーカーを通じて「工業会等による証明書」を入手します。B・C・D類型の設備の場合は、認定経営革新等支援機関に依頼し、投資計画が要件を満たしていることの「確認書」を発行してもらう必要があります。これらの証明書類は、次のステップである確定申告で必要になる重要な書類です。
5.3 STEP3 確定申告で税制優遇の適用を受ける
設備を事業で使い始めた事業年度の確定申告において、税制優遇(即時償却または税額控除)を受けるための手続きを行います。法人税の申告書に、本税制の適用を受ける旨を記載した所定の明細書を添付する必要があります。
確定申告時に主に必要となる添付書類は以下の通りです。
- 経営力向上計画の申請書(写し)
- 経営力向上計画の認定書(写し)
- 工業会等による証明書(写し)、または投資計画に関する確認書(写し)
- 法人税申告書別表(減価償却資産の償却額の計算に関する付表など)
どの書類をどのように作成し、申告書に添付するかは専門的な知識を要します。選択する優遇措置(即時償却か税額控除か)によっても記載する様式が異なるため、必ず顧問税理士などの専門家に相談の上、手続きを進めてください。申告漏れや書類の不備があると、せっかくの税制優遇が受けられなくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
制度利用前に知っておきたい注意点
中小企業経営強化税制は、設備投資を行う企業にとって非常に魅力的な制度ですが、そのメリットを最大限に活用するためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。手続きの順番を間違えたり、対象外の設備を誤って購入したりすると、せっかくの優遇措置が受けられなくなる可能性があります。ここでは、制度利用で失敗しないために、事前に必ず確認しておきたい3つのポイントを詳しく解説します。
6.1 経営力向上計画の認定は設備取得前が原則
この税制を利用する上で、最も重要かつ見落としがちなのが「手続きの順番」です。原則として、税制優遇の対象となる設備を取得する前に、事業計画である「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受ける必要があります。
これは、計画に基づいて生産性向上や収益力強化のための設備投資が行われることを国が確認するという、制度の趣旨に基づいています。設備を先に購入してしまうと、「計画に基づいた投資」とは認められず、原則として税制の適用が受けられません。設備メーカーとの商談を進めると同時に、経営力向上計画の申請準備も並行して進めることが成功のカギとなります。
ただし、例外として設備取得後に計画を申請することも可能ですが、その場合は設備取得日から60日以内に経営力向上計画が主務大臣に受理される必要があります。計画の申請から認定までには一定の期間を要するため、取得後の申請はスケジュールが非常にタイトになります。予期せぬトラブルで期限を過ぎてしまうリスクを避けるためにも、可能な限り「設備取得前の認定」を目指しましょう。
6.2 中古資産や対象外の設備に注意
中小企業経営強化税制が適用されるのは、新品の設備に限られます。原則として、中古品やレンタル品、リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引は対象)は対象外となるため注意が必要です。
また、A類型からD類型に定められた要件を満たす設備であっても、事業内容や使い方によっては対象外と判断されるケースがあります。特に、以下の設備は対象にならない可能性が高いため、導入前に必ず確認してください。
| 注意が必要な資産の種類 | 対象外となる可能性のある理由 |
|---|---|
| 事務用器具備品 | 生産性向上に直接的に寄与しないと判断される場合が多い。(例:応接セット、事務机) |
| 本店・寄宿舎等の建物附属設備 | 生産等を行う事業所ではなく、本社機能や福利厚生施設に関わるものは対象外。(例:本店ビルの空調設備) |
| 福利厚生施設に係るもの | 従業員の福利厚生を目的とした設備は、事業の用に直接供するものと認められない。(例:社員食堂の厨房設備) |
| 汎用性の高いソフトウェア | 特定の業務プロセスを効率化するものではなく、一般的な事務作業に用いるソフトウェア(例:OS、表計算ソフト)は対象外となることがある。 |
| 測定工具及び検査工具 | 生産ラインに組み込まれ、一体となって稼働するもの以外は対象外となる場合がある。 |
「この設備は対象になるだろう」という自己判断は禁物です。高額な投資を無駄にしないためにも、設備メーカーや販売代理店、工業会等が発行する「証明書」を取得できるか、事前に必ず確認しましょう。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
6.3 他の税制優遇措置との併用について
設備投資に関する税制優遇措置は、中小企業経営強化税制以外にも複数存在します。代表的なものに「中小企業投資促進税制」があります。ここで重要な原則は、「一つの設備投資に対して、複数の税制優遇措置を重複して適用することはできない」という点です。
例えば、1,000万円の機械装置を購入した場合、その機械装置に対して中小企業経営強化税制の即時償却と、中小企業投資促進税制の特別償却(30%)の両方を適用することはできません。どちらか一方を選択(選択適用)する必要があります。
どちらの制度が有利になるかは、企業の利益状況や設備の種類、金額によって異なります。それぞれの制度の要件と優遇内容を比較検討し、自社にとって最も節税効果が高いものを選択することが重要です。
| 制度名 | 主な優遇内容 | 主な対象設備 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 中小企業経営強化税制 | 即時償却 または 税額控除(7% or 10%) | 生産性向上設備(A)、収益力強化設備(B)、デジタル化設備(C)、経営資源集約化設備(D) | 経営力向上計画の認定が必須。優遇措置の効果が大きい。 |
| 中小企業投資促進税制 | 特別償却(30%) または 税額控除(7%) | 機械装置、測定工具及び検査工具、ソフトウェアなど幅広い設備が対象 | 経営力向上計画の認定は不要で、比較的利用しやすい。 |
この他にも、「DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制」や「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」など、特定の目的を持つ設備投資を後押しする制度もあります。どの制度を選択すべきか判断に迷う場合は、顧問税理士などの専門家と相談し、最適な選択を行いましょう。詳細については、中小企業庁のウェブサイト「経営強化法による支援」も併せてご確認ください。
まとめ
中小企業経営強化税制は、設備投資を行う中小企業にとって「即時償却」か「税額控除」のいずれかを選択できる強力な税制優遇措置です。当期の利益を圧縮し資金繰りを改善したい場合は即時償却、複数年にわたり安定した節税効果を求めるなら税額控除が適しています。本制度を利用するには、設備取得前に「経営力向上計画」の認定を受けることが必須です。計画的な設備投資を検討している企業は早めに準備を進めましょう。
Zerofieldでは、GPUサーバーを活用した節税をご案内しております。税務面でのご相談がございましたら、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。