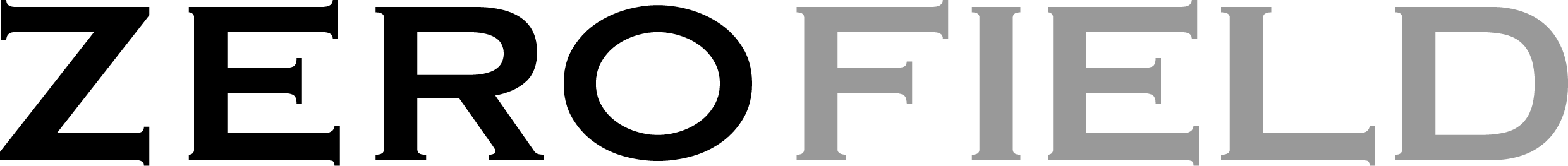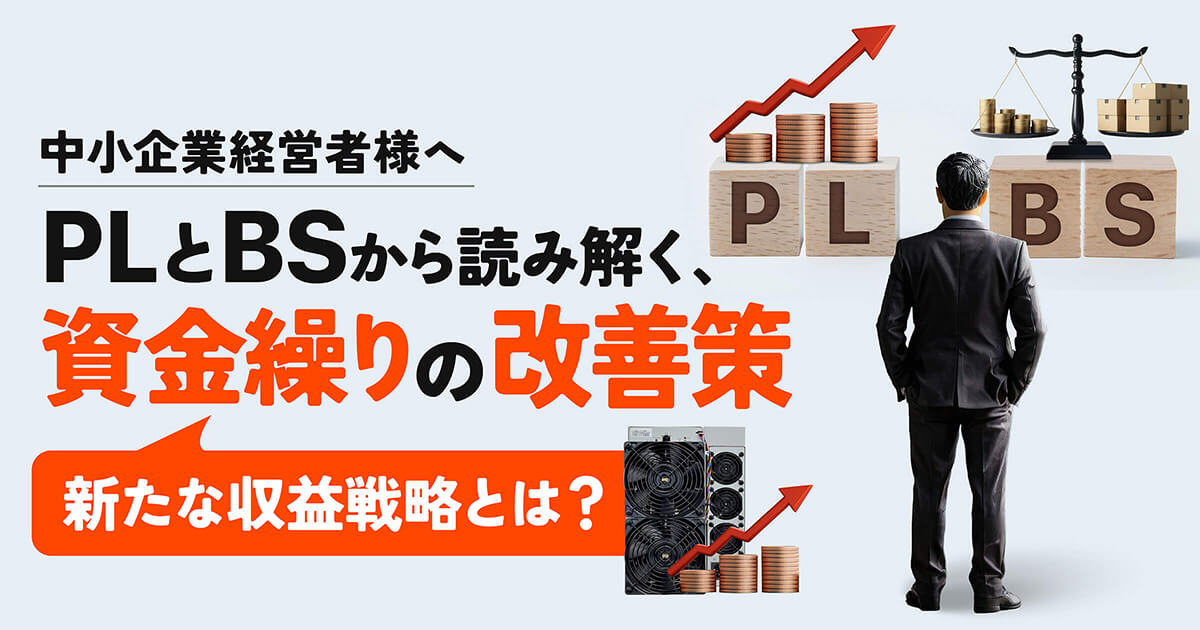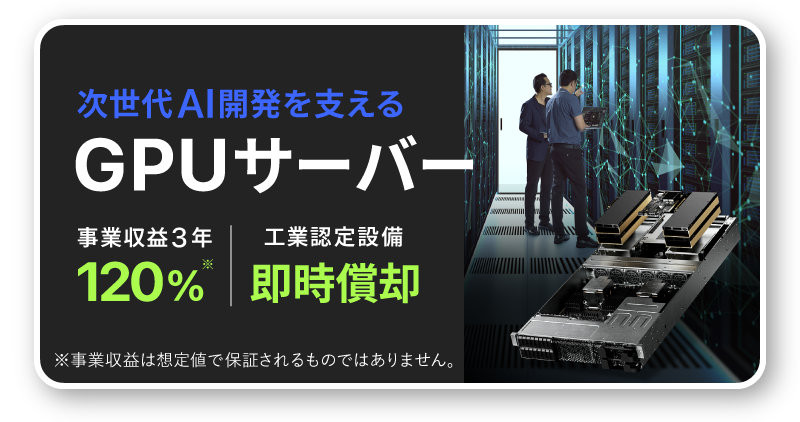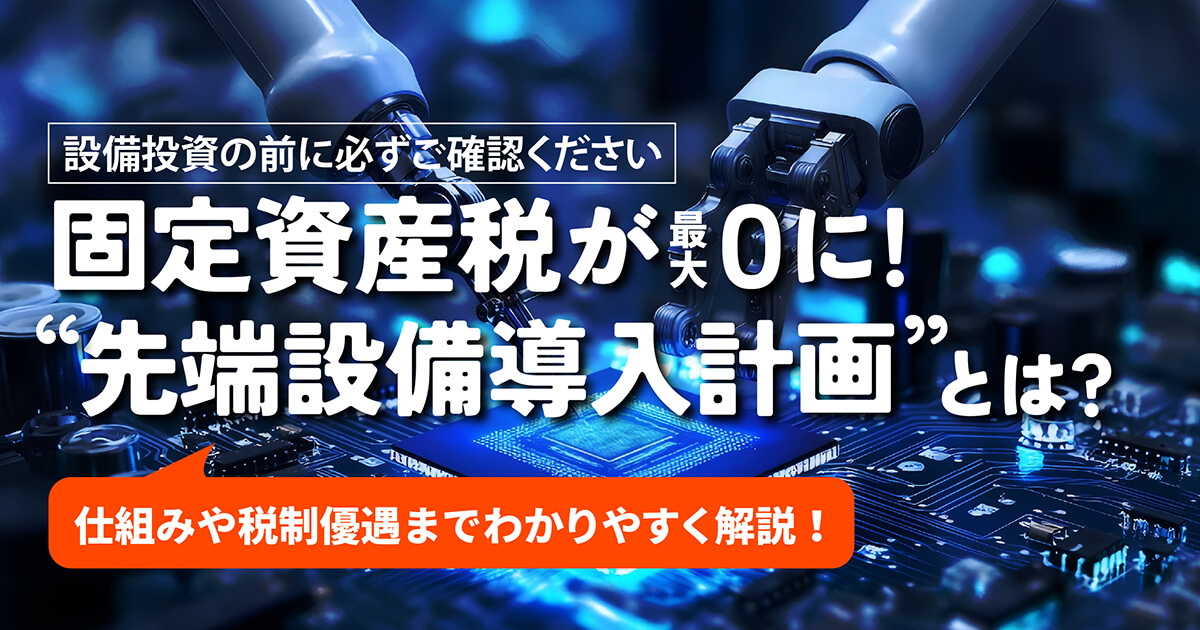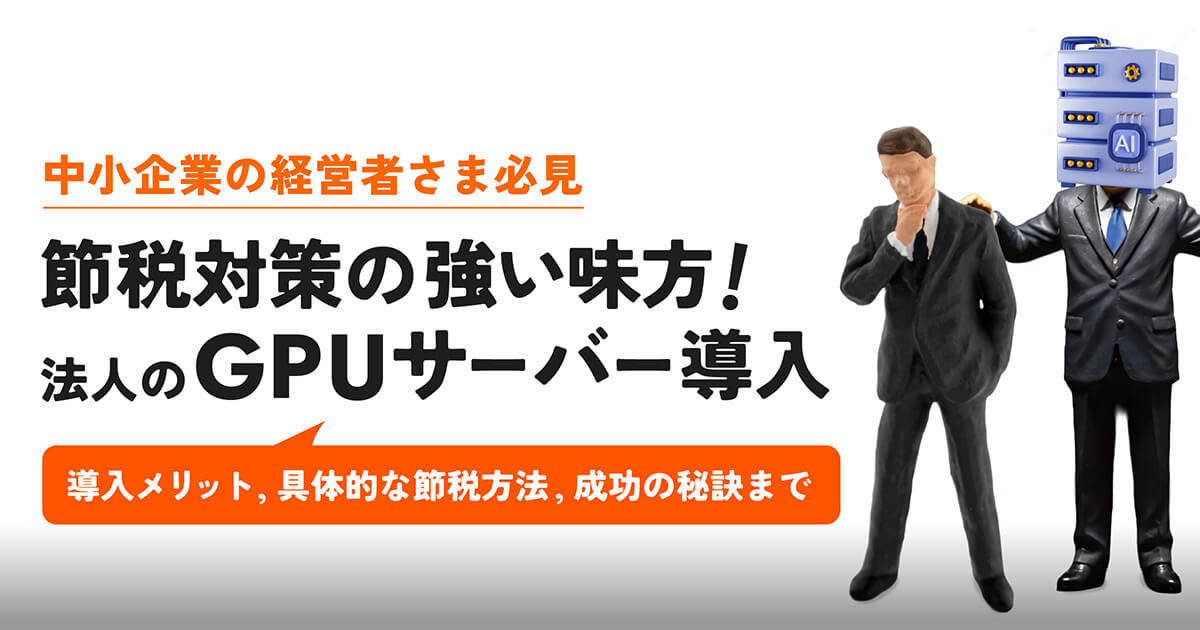会社の決算書で見るPLとBSの違い、正しく説明できますか?PL(損益計算書)は「一定期間の儲け」を示す成績表、BS(貸借対照表)は「ある時点での財産」を示す健康診断書です。この記事を読めば、両者の決定的な違いから密接なつながり、経営分析での活かし方までが初心者にもスッキリわかります。会社の本当の姿を読み解き、健全な経営を目指すための第一歩を踏み出しましょう。
PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)の基本的な役割
会社経営において、自社の経営状況を正確に把握することは、事業を成長させ、安定した資金繰りを実現するための第一歩です。そのために不可欠なのが「財務諸表(決算書)」と呼ばれる書類です。中でも特に重要なのが「PL(損益計算書)」と「BS(貸借対照表)」であり、これに「キャッシュフロー計算書」を加えた3つを総称して「財務三表」と呼びます。
PLとBSは、どちらも会社の経営状態を示す重要な書類ですが、それぞれ見ている側面が異なります。PLが会社の「経営成績」を示すのに対し、BSは「財務状態」を示します。この2つを正しく理解し、両方の視点から会社を分析することで、初めて経営の全体像が見えてくるのです。まずは、それぞれの基本的な役割から見ていきましょう。
1.1 PL(損益計算書)とは?一定期間の「儲け」がわかる成績表
PL(ピーエル)とは、”Profit and Loss Statement”の略で、日本語では「損益計算書」といいます。これは、会計期間(通常は1年間)で、会社がどれだけ売上を上げ、どれだけの費用を使い、最終的にいくら儲かったのか(または損したのか)を示す書類です。
例えるなら、会社の「成績表」や「通信簿」のようなものです。この成績表を見ることで、企業の「稼ぐ力」、つまり収益性を評価することができます。
PLは、主に以下の要素で構成されています。
- 収益:会社の売上高など、事業活動によって得られた収入。
- 費用:売上原価や販売費及び一般管理費(販管費)など、収益を得るためにかかったコスト。
- 利益:収益から費用を差し引いた、会社の儲け。
PLでは、この利益が「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」という5つの段階に分けて計算されます。これにより、利益がどの段階でどれだけ生み出されているのか、あるいはどこに課題があるのかといった、会社の収益構造を詳細に分析することが可能になります。
1.2 BS(貸借対照表)とは?ある時点の「財産」がわかる健康診断書
BS(ビーエス)とは、”Balance Sheet”の略で、日本語では「貸借対照表」といいます。これは、決算日など「ある一時点」で、会社がどれだけの財産(資産)を持っていて、それがどのような形で調達されたのか(負債・純資産)を示す書類です。
PLが期間の成績を示す「成績表」なら、BSは特定の日における会社の財産状況を示す「健康診断書」に例えられます。この健康診断書によって、会社の財務的な体力や安全性、つまり倒産しにくいかどうかを判断することができます。
BSは、大きく分けて以下の3つの要素で構成されており、常に「資産 = 負債 + 純資産」という関係が成り立ちます。
| 貸借対照表(BS)の構造 | |
|---|---|
| 資産の部(左側) 会社が保有する財産 (お金の使い道) | 負債の部(右上) 返済義務のある他人資本 (借入金など) |
| 現金、預金、売掛金、商品、土地、建物など | 純資産の部(右下) 返済義務のない自己資本 (資本金、利益剰余金など) |
この左右の合計金額が必ず一致(バランス)することから、「バランスシート」と呼ばれます。BSを読み解くことで、手元の資金は十分か、借金に頼りすぎていないか、といった資金繰りの状況や倒産リスクを把握できます。
1.3 もう一つの重要書類「キャッシュフロー計算書(CS)」との関係
PLとBSに加えて、もう一つ重要なのが「キャッシュフロー計算書(CS)」です。CS(シーエス)は “Cash Flow Statement” の略で、その名の通り、会計期間中に会社の現金(キャッシュ)がどのように増減したのか、その流れ(フロー)を示す書類です。
PL上の利益は、必ずしも手元にある現金の額とは一致しません。例えば、商品を掛けで販売した場合、売上は計上されてPL上は黒字になりますが、入金が先延ばしになれば手元の現金は増えません。この会計上の利益と現実のお金の動きのズレが、いわゆる「黒字倒産」を引き起こす原因となります。
キャッシュフロー計算書は、このズレを埋める役割を果たし、現金の動きを以下の3つの活動に分けて示します。
- 営業活動によるキャッシュフロー:本業の儲けから得られた現金の増減
- 投資活動によるキャッシュフロー:設備投資や有価証券の売買などによる現金の増減
- 財務活動によるキャッシュフロー:借入れや返済、増資など資金調達に関する現金の増減
PLで「どれだけ儲けたか」を確認し、BSで「財産は健全か」をチェックし、そしてCSで「実際のお金の動きに問題はないか」を検証する。この3つの書類をセットで見ることで、会社の経営状態を多角的に、より深く理解することができるのです。
【一覧表で比較】PLとBSの5つの決定的な違い
PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)は、どちらも会社の経営状態を示す重要な決算書ですが、その役割と見方は全く異なります。PLが会社の「経営成績」を示す通知表なら、BSは会社の「財産状況」を示す健康診断書に例えられます。
両者の違いを理解することは、自社の経営状況を正しく把握し、的確な打ち手を考えるための第一歩です。ここでは、PLとBSの根本的な違いを5つのポイントに絞り、初心者の方にもわかりやすく解説します。
まずは、5つの違いを一覧表で確認してみましょう。
| 比較項目 | PL(損益計算書) | BS(貸借対照表) |
|---|---|---|
| 違い1:目的 | フロー(流れ) 一定期間の経営活動の流れを示す | ストック(蓄積) ある一時点での財産の蓄積を示す |
| 違い2:時間軸 | 期間(例:4月1日~3月31日) 会計期間中の成績 | 時点(例:3月31日時点) 決算日時点での財産状況 |
| 違い3:構成要素 | 収益、費用、利益 | 資産、負債、純資産 |
| 違い4:わかること | 収益力・稼ぐ力 どれだけ儲かったか | 財務の健全性・安全性 倒産しにくいか |
| 違い5:読み解く順番 | 先に見て「儲け」を把握する | PLの後に見て「財産の増減」を確認する |
それでは、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
2.1 違い1:目的|フロー(流れ)とストック(蓄積)
PLとBSの最も本質的な違いは、会社のお金の動きを「フロー」で見るか、「ストック」で見るかにあります。
- PLは「フロー」の計算書
フローとは「流れ」を意味します。PLは、会計期間中にどれだけのお金が入り(収益)、どれだけのお金が出ていったか(費用)という一連の「流れ」を記録し、その結果としてどれだけの利益が残ったかを示す書類です。月々の収入と支出を記録する家計簿をイメージすると分かりやすいでしょう。 - BSは「ストック」の計算書
ストックとは「蓄積」を意味します。BSは、創業から決算日までの経営活動の結果、会社にどれだけの財産(資産)が「蓄積」されているかを一覧にした書類です。特定の日(例えば、月末)の銀行口座の残高のようなものと考えると理解しやすくなります。
このように、PLはプロセス(流れ)を、BSは結果(蓄積)を表すという根本的な目的の違いがあります。
2.2 違い2:時間軸|「期間」と「時点」
目的の違いは、それぞれの書類が示す「時間軸」の違いにも関連しています。
- PLは「期間」の成績
PLは「いつからいつまで」という一定期間の経営成績を示します。通常は1年間(会計年度)ですが、月次や四半期で作成することもあります。言わば、会社の1年間の活動を記録した「ドキュメンタリー動画」のようなものです。 - BSは「時点」の財産
BSは「〇年3月31日現在」のように、ある特定の時点での財産状況を示します。その瞬間の会社の状態を切り取った「スナップ写真」に例えられます。前期末のBSと当期末のBSを比較することで、この1年間で財産がどのように変化したかを知ることができます。
2.3 違い3:構成要素|収益・費用 vs 資産・負債・純資産
PLとBSでは、記載されている項目(勘定科目)が全く異なります。
2.3.1 PLの構成要素:「収益」「費用」「利益」
PLは、会社がどうやって利益を生み出したかを示すため、以下の3つの要素で構成されています。
- 収益:売上高など、会社に入ってくるお金の源泉。
- 費用:売上原価や販売費及び一般管理費(販管費)など、収益を得るために使ったお金。
- 利益:収益から費用を差し引いた儲け。
この「収益 − 費用 = 利益」というシンプルな計算式がPLの基本構造です。
2.3.2 BSの構成要素:「資産」「負債」「純資産」
BSは、会社が保有する財産とその調達源泉のバランスを示すため、以下の3つの要素で構成されています。
- 資産:現金、預金、売掛金、建物、土地など、会社が保有するプラスの財産。資金の「使い道」を示します。
- 負債:借入金や買掛金など、いずれ返済しなければならないマイナスの財産(他人資本)。
- 純資産:資本金や利益剰余金など、返済不要の自己資本。
BSでは常に「資産 = 負債 + 純資産」という等式が成り立ちます。これは、会社の財産(資産)が、返済義務のあるお金(負債)と返済不要の自分のお金(純資産)で、どのように賄われているかを示しています。
2.4 違い4:わかること|収益力 vs 財務の健全性
目的や構成要素が違うため、PLとBSから読み取れる情報も異なります。
- PLでわかること:収益力(稼ぐ力)
PLを分析することで、会社の本業がどれだけ儲かっているか(営業利益)、コスト構造に問題はないか(売上原価率)、最終的にどれだけの利益を確保できたか(当期純利益)など、企業の「収益性」を評価できます。いわば、会社の攻撃力を測る指標です。 - BSでわかること:財務の健全性(安全性)
BSを分析することで、資金繰りに余裕があるか(流動比率)、借金に頼りすぎていないか(自己資本比率)、倒産のリスクは低いかなど、企業の「安全性」や「支払い能力」を評価できます。こちらは、会社の防御力や体力を測る指標と言えるでしょう。
利益が出ていても(PLが黒字)、借金まみれ(BSが不健全)では、会社は長続きしません。両方を見ることが不可欠です。
2.5 違い5:読み解く順番
財務諸表を初めて見る方は、どちらから手をつければ良いか迷うかもしれません。一般的には、以下の順番で見るのがおすすめです。
基本は「PL → BS」の順番で見るのが分かりやすいです。
- まずPLで、その期の「儲け」を確認する。
「この1年で、どれだけ売上を上げて、最終的にいくらの利益(当期純利益)が出たのか?」という経営成績の全体像を把握します。 - 次にBSで、PLの結果がどう反映されたかを確認する。
PLで稼いだ利益は、BSの純資産の部にある「繰越利益剰余金」として蓄積されます。PLの利益によって、会社の財産(特に純資産)が前期末からどれだけ増えたかを確認することで、会社の成長を実感できます。
この流れで見ることで、1年間の経営活動(フロー)が、会社の財産(ストック)にどのような影響を与えたのかをストーリーとして理解することができます。
PLとBSのつながりとは?「利益」が「資産」になる仕組みを図解
PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)は、それぞれ会社の異なる側面を映し出す財務書類ですが、決して独立したものではありません。両者は密接に連携しており、このつながりを理解することこそが、会社の経営状態を深く読み解く鍵となります。
一言でいえば、PL(フロー)で生み出された利益が、BS(ストック)に蓄積されていくという関係です。日々の営業活動の成績(PL)が、会社の財産(BS)をどのように変化させたのか。その具体的な仕組みを見ていきましょう。
3.1 PLの当期純利益がBSの純資産(繰越利益剰余金)に加わる
PLとBSをつなぐ最も直接的で重要な接点が「当期純利益」です。PLは、一定期間(通常は1年間)の売上から費用を差し引いて、最終的に会社に残った利益、つまり「当期純利益」を算出します。この利益が、会社の純粋な財産である純資産を増やす源泉となるのです。
具体的には、会計期間が終了すると、PLで確定した「当期純利益」が、BSの純資産の部にある「繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん)」という項目に加算されます。繰越利益剰余金とは、会社が設立されてから現在までに稼いできた利益の累計額のことです。
この一連の流れを図解すると、以下のようになります。
例えば、ある会社の期首(期のはじめ)の繰越利益剰余金が500万円だったとします。その期に事業活動を行い、PLで計算した結果、当期純利益が100万円出たとします。すると、期末(期の終わり)のBSでは、繰越利益剰余金は以下のようになります。
期首の繰越利益剰余金 500万円 + 当期の純利益 100万円 = 期末の繰越利益剰余金 600万円
このように、毎年PLで利益を出し続けることで、BSの繰越利益剰余金、すなわち純資産が雪だるま式に増えていきます。これが、会社の内部留保が厚くなり、財務基盤が強固になる仕組みです。
利益が増えると、その分だけ会社の現金や預金といった「資産」も増加します。BSは常に「資産 = 負債 + 純資産」という等式が成り立つため、利益によって純資産が増えれば、必ず資産も同額増加し、左右のバランスが保たれるのです。
3.2 両方を見ることで会社の本当の姿が見える理由
では、なぜPLとBSをセットで見なければならないのでしょうか。それは、片方だけでは会社の経営状態を正しく評価できず、重大なリスクを見逃してしまう可能性があるからです。「木を見て森を見ず」の状態に陥らないために、両方の視点が必要不可欠です。
PLだけ、あるいはBSだけを見ることで生じる判断の偏りを、以下の表で確認してみましょう。
| PL(損益計算書)だけを見る場合 | BS(貸借対照表)だけを見る場合 | |
|---|---|---|
| わかること | ・期間中の収益力や利益構造・どの事業で儲かっているか・コストのかけ方 | ・ある時点での財産状況・支払い能力(安全性)・借入金と自己資本のバランス |
| わからないこと(見逃すリスク) | ・資金繰りの実態(黒字倒産のリスク)利益が出ていても、売掛金や在庫ばかりで現金がなければ支払いができず倒産する可能性があります。 | ・現在の収益力(ジリ貧のリスク)過去の蓄積で自己資本が厚くても、今期が赤字続きなら、いずれ財産を食い潰してしまいます。 |
このように、PLは会社の「稼ぐ力(収益性)」というフロー(流れ)を、BSは「支払い能力や倒産しにくさ(安全性)」というストック(蓄積)を示しています。
たとえるなら、PLが「マラソン中のラップタイム」で、BSが「ゴール時点での選手の体力残量」です。速いラップタイム(高い利益)を刻んでいても、体力が尽きれば(資金がショートすれば)ゴールできません。逆に、体力(自己資本)が十分にあっても、ペース(収益力)が落ちていれば、いずれライバルに抜かれてしまいます。
会社の過去から現在までの努力の結晶(BS)と、今まさに発揮している実力(PL)を両方見ることで、初めてその会社の真の姿と将来性を正しく評価できるのです。
中小企業経営者がPLとBSから読み解くべき重要経営指標
PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)は、それぞれ単独で見るだけでも多くの情報が得られますが、それらの数値を組み合わせた「経営指標」を用いることで、会社の経営状態をより深く、多角的に分析できます。ここでは、特に中小企業の経営者が押さえておくべき重要な経営指標を、PL・BSのどちらからわかるのか、あるいは両方を組み合わせて見るのか、という視点で解説します。
4.1 PLで見るべきポイント:5つの利益と利益率
PLは企業の「収益性」、つまりどれだけ効率的に稼げているかを示す成績表です。最終的な当期純利益だけを見るのではなく、利益が生まれる過程を5つの段階に分けて分析することで、自社の強みや弱点、課題が見えてきます。
まずは、基本となる5つの利益を理解しましょう。
| 利益の種類 | 計算式 | わかること |
|---|---|---|
| 売上総利益(粗利) | 売上高 − 売上原価 | 商品やサービスの基本的な儲け。商品力や価格設定の適切さがわかる。 |
| 営業利益 | 売上総利益 − 販売費及び一般管理費(販管費) | 本業での稼ぐ力。営業活動の効率性やコスト管理能力がわかる。 |
| 経常利益 | 営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用 | 会社全体の総合的な収益力。財務活動を含めた平常時の実力がわかる。 |
| 税引前当期純利益 | 経常利益 + 特別利益 − 特別損失 | 臨時的な損益を含めた、税金支払い前の利益。 |
| 当期純利益 | 税引前当期純利益 − 法人税等 | 最終的に会社に残る利益。株主への配当や内部留保の源泉となる。 |
これらの利益額に加えて、売上高に対する割合である「利益率」を分析することが極めて重要です。利益率を見ることで、売上規模の異なる他社や過去の自社と比較しやすくなります。
- 売上総利益率(粗利率):高いほど商品・サービスの競争力が高いことを示します。この数値が低い場合、原価の高騰や不適切な価格設定が原因かもしれません。
- 売上高営業利益率:本業の収益性を測る中心的な指標です。この利益率が低い場合、人件費や広告宣伝費などの販管費が収益を圧迫している可能性があります。
- 売上高経常利益率:企業の総合的な収益力を示します。営業利益率と大きく乖離している場合は、借入金の支払利息など、財務活動に課題があると考えられます。
どの利益段階で数値が悪化しているかを特定することが、具体的な経営改善策を立てるための第一歩となります。
4.2 BSで見るべきポイント:自己資本比率と流動比率
BSは企業の「安全性」、つまり財務体質の健全性や倒産リスクの低さを示します。特に金融機関からの融資審査などでは厳しくチェックされるため、経営者は常に把握しておく必要があります。
| 指標名 | 計算式 | わかること | 目安 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資本(資産合計) × 100 | 総資本のうち、返済不要の自己資本が占める割合。企業の中長期的な安全性を示す。 | 30%以上が望ましい。50%を超えると優良企業とされる。 |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 | 1年以内に現金化できる資産が、1年以内に返済すべき負債をどれだけ上回っているか。企業の短期的な支払い能力を示す。 | 150%以上が望ましい。100%を下回ると資金繰りが厳しい状態。 |
4.2.1 自己資本比率:会社の体力・倒産しにくさ
自己資本比率は、会社の財務的な体力を示す最も重要な指標の一つです。この比率が高いほど、借入金への依存度が低く、経営が安定していると評価されます。赤字が続くと自己資本が減少し、この比率も低下します。金融機関は融資の際にこの比率を重視するため、安定した経営を目指す上で、自己資本比率を高く維持することは非常に重要です。
4.2.2 流動比率:短期的な資金繰りの安全性
流動比率は、会社の短期的な支払い能力、つまり資金繰りの余裕度を示します。この比率が高ければ、急な支払いや予期せぬ支出にも対応しやすいと判断できます。ただし、注意点として、流動資産の中にはすぐに現金化できない「売掛金」や「在庫」も含まれます。そのため、流動比率が高くても、不良在庫や回収不能な売掛金が多い場合は、実態として資金繰りが悪化している可能性があるため、資産の中身を精査することが不可欠です。
4.3 PLとBSを組み合わせて分析する:ROE(自己資本利益率)
PLとBSの数値を組み合わせることで、企業の「効率性」を分析できます。中でもROE(Return On Equity:自己資本利益率)は、経営の総合力を測る上で非常に重要な指標です。
4.3.1 ROE(自己資本利益率):資本をどれだけ効率的に使って儲けたか
ROEは、株主から集めたお金(自己資本)を元手にして、どれだけ効率的に利益(当期純利益)を生み出したかを示す指標です。投資家が企業の収益性を判断する際にもよく利用されます。
計算式:ROE(%) = 当期純利益(PL) ÷ 自己資本(BS) × 100
例えば、自己資本が1億円の会社Aが1,000万円の利益を出した場合、ROEは10%です。一方、自己資本が2億円の会社Bが同じく1,000万円の利益を出した場合、ROEは5%となり、会社Aの方が資本を効率的に活用していると評価できます。
ROEは、PLの最終成果である「利益」とBSの「自己資本」を結びつけ、企業の資本効率を明らかにする指標です。 ROEを高めるには、PLの利益を増やすか、BSの自己資本を適切な水準にコントロールする必要があります。この指標を分析することで、自社の経営が効率的に行われているかを客観的に評価し、次の戦略を立てるためのヒントを得ることができるのです。
PL・BSを経営改善に活かす方法|資金繰り安定化のヒント
PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)は、ただ眺めるだけでは意味がありません。これらを分析し、具体的なアクションに繋げることで初めて、経営改善の強力なツールとなります。特に中小企業にとって生命線である「資金繰り」を安定させるためには、PLとBSの両面から自社の状況を正確に把握し、課題を特定することが不可欠です。この章では、PLとBSの数字をどのように読み解き、具体的な経営改善策に活かしていくのかを解説します。
5.1 PLから利益構造を改善するアクション
PLは会社の「稼ぐ力」を示す成績表です。利益構造を改善するためには、「売上を増やす(トップラインを伸ばす)」ことと「費用を減らす(コストを最適化する)」という2つのアプローチがあります。PLの各項目を分析し、どこに改善の余地があるのかを見つけ出しましょう。
具体的なアクションプランは以下の通りです。
| 改善の方向性 | 具体的なアクション例 | 着目するPLの項目 |
|---|---|---|
| 売上の最大化 | 既存顧客へのアップセル・クロスセル提案 商品・サービスの価格改定(値上げ交渉) 新規顧客開拓のためのマーケティング強化 利益率の高い商品・サービスへの注力 | 売上高、売上総利益 |
| 変動費の削減 | 仕入先の見直しや価格交渉 外注費の適正化、内製化の検討 製造プロセスの改善による歩留まり向上 | 売上原価 |
| 固定費の削減 | 業務効率化による残業代の削減 オフィス賃料の交渉や移転の検討 ペーパーレス化による消耗品費の削減 広告宣伝費の費用対効果(ROI)の見直し | 販売費及び一般管理費 |
これらの施策を講じることで、PL上の各利益(売上総利益、営業利益、経常利益)が改善され、会社の収益性が高まります。
5.2 BSから財務体質を強化するアクション
BSは会社の「財務の健全性」を示す健康診断書です。BSを改善することは、すなわち倒産しにくい強い財務体質を構築することに繋がります。BSの改善は、「資産の効率化」と「負債の圧縮・最適化」が鍵となります。
財務体質を強化するための具体的なアクションは以下の通りです。
| 改善の方向性 | 具体的なアクション例 | 着目するBSの項目 |
|---|---|---|
| 資産の効率化 | 売掛金の回収サイト短縮交渉、早期回収の徹底 滞留在庫・不良在庫の処分、適正在庫の維持 使用していない機械や不動産(遊休資産)の売却 | 流動資産(売掛金、棚卸資産)、固定資産 |
| 負債の圧縮・最適化 | 買掛金の支払いサイト延長交渉 短期借入金から長期借入金への借り換え検討 金利の高い借入金の繰り上げ返済 役員借入金などの整理 | 流動負債(買掛金、短期借入金)、固定負債 |
| 純資産の増加 | PL改善による利益の確保と内部留保(利益剰余金)の蓄積 増資による自己資本の増強 | 純資産(利益剰余金、資本金) |
特に、BSの左側(資産)をスリムにし、右下(純資産)を厚くすることで、自己資本比率が高まり、金融機関からの信頼も得やすくなります。
5.3 なぜ黒字なのに倒産?PLだけでは見えない資金繰りの罠
多くの経営者が陥りがちなのが、「PLで利益が出ているから安心」という思い込みです。しかし、会計上の利益と手元にある現金(キャッシュ)は必ずしも一致しません。このズレが原因で、PL上は黒字にもかかわらず、支払いに必要なお金が足りなくなり倒産してしまう「黒字倒産」が起こるのです。
黒字倒産は、PLという「期間」の成績だけを見て、BSやキャッシュフローという「お金の流れと残高」を見ていないために発生します。会社の血液である現金が尽きれば、どんなに利益が出ていても事業は継続できません。
5.3.1 売掛金と在庫がキャッシュを圧迫する
黒字倒産を引き起こす主な原因は、BSの資産の部に隠されています。特に注意すべきは「売掛金」と「棚卸資産(在庫)」です。
- 売掛金
商品を販売した時点でPLには「売上」として計上されますが、その代金が実際に入金されるのは数ヶ月先というケースがほとんどです。この未回収の売上である売掛金が増えすぎると、売上は伸びているのに手元の現金は増えず、仕入れ代金や経費の支払いに窮することになります。 - 棚卸資産(在庫)
商品を仕入れたり製造したりすると、現金が「在庫」という資産に変わります。この在庫は、販売されて初めて現金化されます。需要予測を誤って過剰な在庫を抱えてしまうと、その分のお金が倉庫で眠っているのと同じ状態になり、資金繰りを著しく悪化させます。
このように、現金化されるまでに時間がかかる資産が増えるほど、会社のキャッシュフローは圧迫されるのです。
5.3.2 資金繰りを改善する具体的な方法
資金繰りの悪化を防ぎ、安定した経営基盤を築くためには、日々のキャッシュフローを意識した具体的な対策が必要です。「入ってくるお金(キャッシュ・イン)を最大化・早期化」し、「出ていくお金(キャッシュ・アウト)を最小化・遅延化」させることが基本原則です。
| 分類 | 施策 | 具体的なアクション例 |
|---|---|---|
| キャッシュ・インの改善 (入金を増やす・早める) | 売掛金の早期回収 | 請求書の発行タイミングを早める(例:月末締め→納品都度) 回収サイトの短い取引を増やす、または交渉する 入金遅延のある取引先への督促を徹底する ファクタリング(売掛債権買取サービス)を利用する |
| 資金調達 | 日本政策金融公庫や制度融資など、有利な条件の融資を活用する 補助金・助成金を積極的に申請する | |
| 資産の現金化 | 不要な在庫をセールなどで処分する 遊休資産(土地、機械など)を売却する | |
| キャッシュ・アウトの改善 (出金を減らす・遅らせる) | 支払いの最適化 | 仕入先と交渉し、買掛金の支払いサイトを延長してもらう 支払いはできるだけクレジットカードや手形を活用する |
| 経費の削減 | PL改善で挙げた固定費・変動費の見直しを徹底する 高額な設備投資は購入ではなくリースを検討する |
これらの施策を地道に実行することが、黒字倒産のリスクを回避し、安定した資金繰りを実現するための第一歩となります。
PLとBSに関するよくある質問
PLとBSの基本を理解すると、次に出てくるのは「自分のビジネスでどう扱えば良いのか?」という実践的な疑問です。ここでは、特に経営者や個人事業主の方から多く寄せられる質問にお答えします。
6.1 個人事業主にもPLとBSは必要ですか?
結論から言うと、個人事業主の方にもPLとBSの作成と理解は強く推奨されます。法人でなくとも、これらを作成するメリットは非常に大きいです。
主な理由は以下の3つです。
- 確定申告で必要になるから
特に、最大65万円または55万円の特別控除が受けられる「青色申告」を行う場合、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)を確定申告書に添付する必要があります。これは、節税の恩恵を受けるための必須条件です。(参考:国税庁 No.2072 青色申告特別控除)
白色申告の場合でも、事業所得などを正確に計算するために「収支内訳書」を作成する必要があり、これはPLの簡易版と言えます。 - 事業の経営状況を正確に把握できるから
PLとBSを作成することで、「どれくらい儲かったか」だけでなく、「手元にどれくらい財産が残っているか」「借入はどれくらいあるか」といった財務状況を客観的な数字で把握できます。どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた経営判断を行うための第一歩となります。 - 融資や補助金の申請時に有利になるから
日本政策金融公庫などから事業資金の融資を受ける際や、各種補助金を申請する際には、事業計画書とともにPLとBSの提出を求められることがほとんどです。日頃から作成・管理していることで、会社の信用度が高まり、審査がスムーズに進む可能性が高まります。
6.2 どのくらいの頻度で確認すれば良いですか?
PLとBSを確認する頻度は、目的によって異なります。理想は「毎月」、経営判断のためには最低でも「四半期ごと」に確認することをおすすめします。
年に一度、確定申告のときだけ見るという方もいますが、それでは経営のかじ取りはできません。病気の発見が手遅れになるのと同じで、経営上の問題も早期発見・早期対策が重要です。
| 確認頻度 | 主な目的 | メリット・できること |
|---|---|---|
| 毎月(月次決算) | タイムリーな経営状況の把握、迅速な意思決定 | 売上や利益の予実管理 資金繰り悪化の兆候の早期発見 問題点に対する迅速な対策の実行 |
| 四半期ごと | 中間的な業績評価、経営戦略の軌道修正 | 3ヶ月単位でのトレンド分析 半期・通期目標達成に向けた計画見直し 銀行への定期的な業況報告 |
| 年1回(本決算) | 税務申告、1年間の業績総括 | 納税額の確定 株主への報告(法人の場合) 次年度の事業計画策定の基礎資料 |
経営者自身が毎月すべての項目を細かくチェックするのは大変かもしれません。まずは「売上高」「営業利益」「現預金残高」「借入金残高」など、特に重要な項目だけでも月次でチェックする習慣をつけましょう。
6.3 作成は税理士に任せきりで大丈夫?
会計や税務の専門家である税理士にPL・BSの作成を依頼すること自体は、非常に有効な選択肢です。しかし、作成を「丸投げ」し、出てきた数字を全く見ない「任せきり」の状態は非常に危険です。
税理士は「税務のプロ」であり、正確な申告や節税対策の専門家です。一方で、経営者は「自社事業のプロ」であり、PL・BSの数字の背景にある事業活動を理解し、未来に向けた経営判断を下す責任があります。
もし任せきりにしてしまうと、以下のようなリスクが生じます。
- 経営判断の遅れ:売上の急な減少や特定の経費の増加といった「数字の異常」に気づけず、対策が後手に回ってしまいます。
- 資金繰りの悪化:PL上で利益が出ていても、キャッシュの動きまでは把握できず、気づいたときには資金ショート寸前という事態に陥りかねません。
- 外部への説明責任を果たせない:銀行から融資を受ける際や、取引先と交渉する際に、自社の財務状況を自分の言葉で説明できず、信用を失う可能性があります。
税理士とは、単に書類作成を依頼する関係ではなく、作成してもらったPLとBSを元に、自社の経営課題について議論するパートナーと考えるべきです。定期的なミーティングの場で「この数字がなぜこうなっているのか」「来月以降の見通しはどうか」といった質問を積極的に行い、数字の裏側にある意味を理解することが、経営者としての重要な役割です。
まとめ
本記事では、PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)の基本的な違いから、両者のつながり、経営分析への活かし方までを解説しました。PLが一定期間の「儲け」を示す成績表であるのに対し、BSはある時点での「財産」を示す健康診断書です。PLの利益がBSの純資産を増やすという関係性から、両方をセットで見なければ会社の本当の姿はわかりません。特に「黒字倒産」のリスクを避けるためにも、この2つの財務諸表を正しく読み解き、自社の経営改善に役立てましょう。
Zerofieldでは、GPUサーバーを活用した節税をご案内しております。税務面でのご相談がございましたら、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。