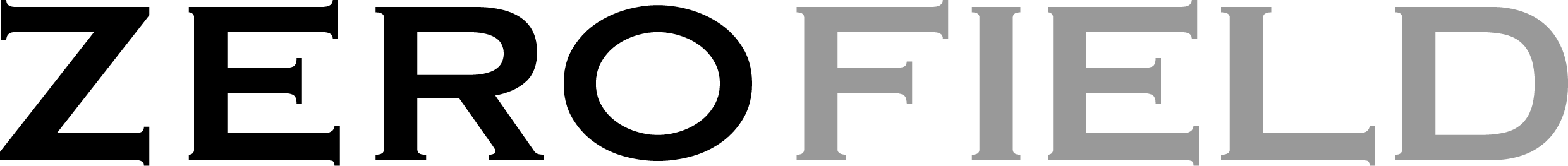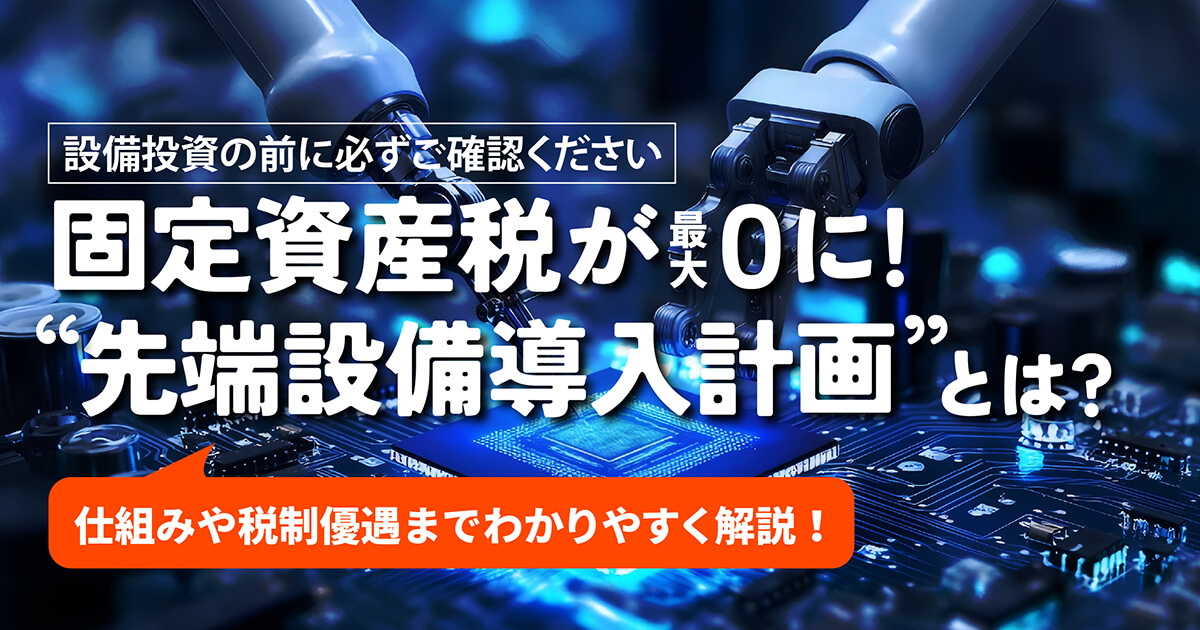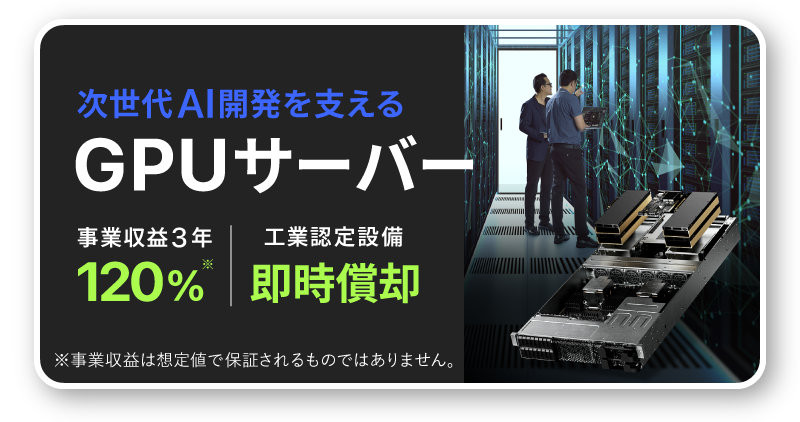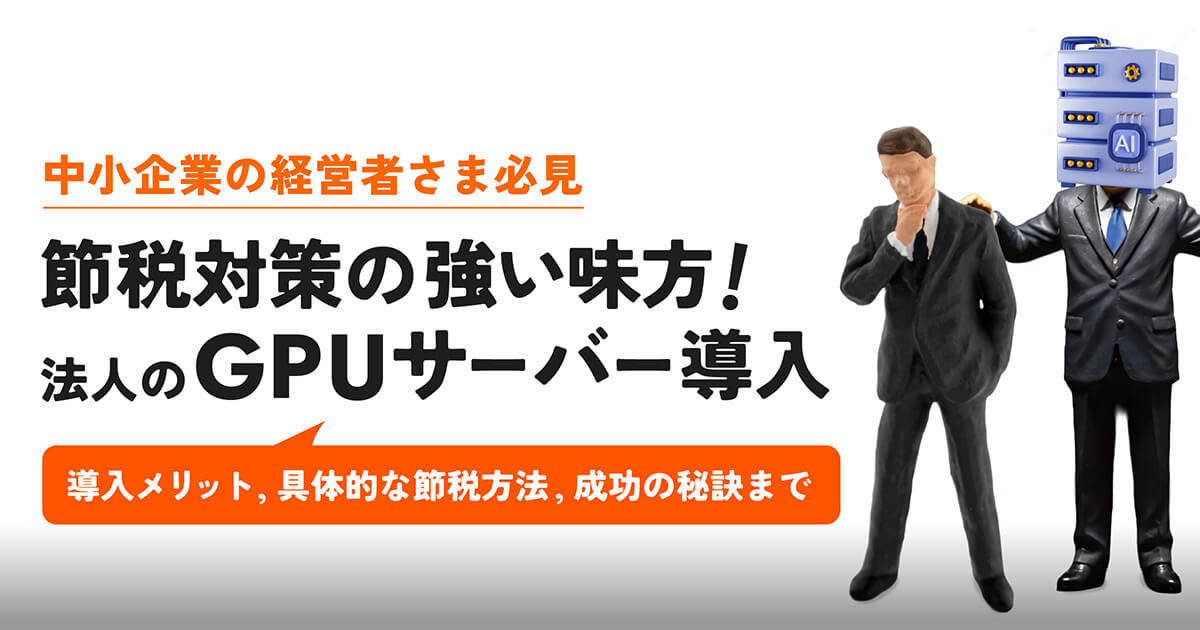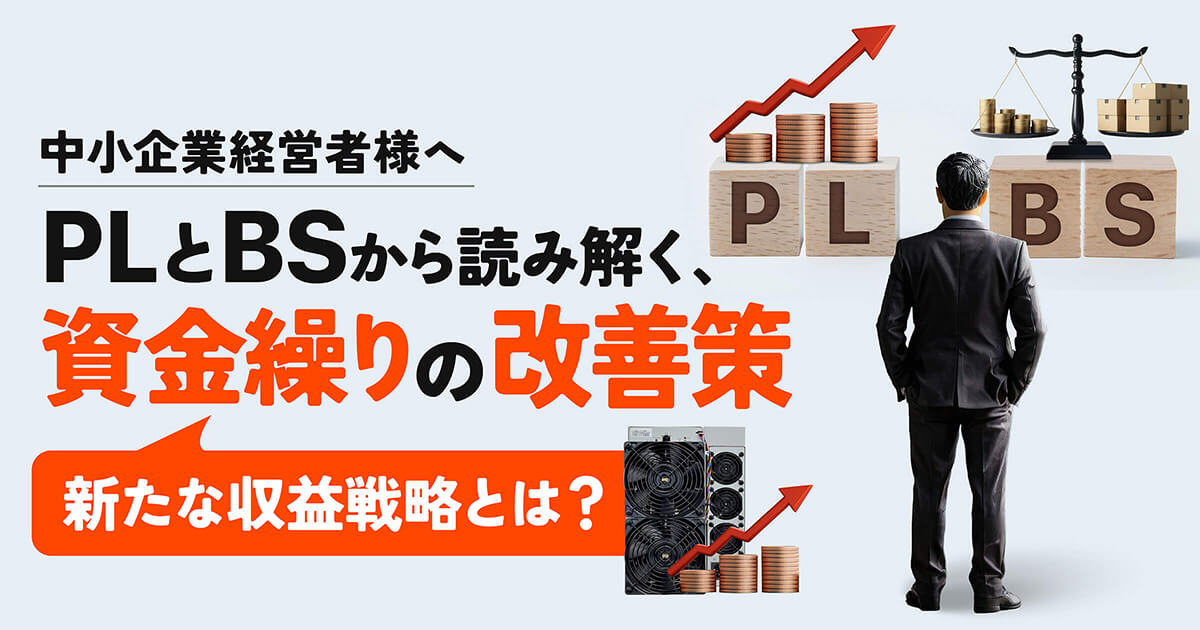先端設備導入計画とは、中小企業が設備投資を行う際に、固定資産税の軽減や補助金の加点といった大きなメリットを受けられる国の支援策です。本記事では、制度の概要や対象要件はもちろん、認定経営革新等支援機関への相談から税務申告まで、申請の流れを5ステップで徹底解説します。この記事を読めば、自社が対象か判断でき、税制優遇を受けるための具体的な手順がすべてわかります。
先端設備導入計画とは そもそもどんな制度か
先端設備等導入計画とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画が市区町村から認定されると、固定資産税の軽減措置や国の補助金の優先採択など、様々な支援を受けられるようになります。物価高や人手不足といった厳しい経営環境に直面する中小企業にとって、最新の設備を導入し、競争力を強化するための非常に有効な制度です。
具体的には、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」が、市区町村が策定した「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。この認定を足がかりに、企業の成長と発展を国が後押ししてくれる、心強い支援策といえるでしょう。
1.1 中小企業の労働生産性向上を目的とした国の支援策
本制度の最も重要な目的は、中小企業の労働生産性を向上させることにあります。少子高齢化による人手不足が深刻化する中、少ない人員でも高い付加価値を生み出せる体制を構築することは、日本経済全体の持続的な成長に不可欠です。
国は、中小企業がAI、IoT、ロボット、高効率な工作機械といった先端設備を導入し、DX(デジタルトランスフォーメーション)や生産プロセスの改善を進めることを奨励しています。この計画を活用することで、中小企業は資金的な負担を軽減しながら、以下のような経営課題の解決を目指せます。
- 最新の機械導入による製造時間の短縮と品質向上
- ITツールやソフトウェア活用による業務プロセスの自動化・効率化
- データ分析に基づく新たなサービス開発や経営判断の迅速化
このように、先端設備等導入計画は、単なる設備投資の支援に留まらず、中小企業が変化の激しい時代を勝ち抜くための経営基盤強化を促進する国の重要な施策です。より詳細な情報については、中小企業庁の公式ウェブサイトもあわせてご確認ください。
1.2 根拠となる法律は中小企業等経営強化法
先端設備等導入計画の根拠となっている法律は「中小企業等経営強化法」です。この法律は、中小企業の経営力を総合的に強化し、生産性向上を支援することを目的としています。先端設備等導入計画は、この法律に定められた支援措置の一つとして明確に位置づけられています。
法律に基づいた制度であるため、申請手続きや要件が全国的に標準化されており、信頼性が高いのが特徴です。ただし、計画の認定主体は各市区町村であるため、自治体ごとに独自の要件を設けている場合もあります。
なお、この制度はもともと「生産性向上特別措置法」に基づいていましたが、法改正により2023年4月1日から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。これに伴い、制度内容も一部変更されています。
| 根拠法 | 適用期間 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 生産性向上特別措置法 | 2018年6月6日~2023年3月31日 | 固定資産税の特例(3年間ゼロ~1/2)が中心。 |
| 中小企業等経営強化法 | 2023年4月1日~ | 固定資産税の特例(3年間または5年間1/2)に加え、賃上げ表明による税率の優遇措置が追加。 |
このように、制度は時代背景に合わせて見直されています。最新の情報を確認しながら、自社にとって最適な形で制度を活用することが重要です。
先端設備導入計画を活用する3つのメリット
先端設備導入計画の認定を受けることで、中小企業は単に設備投資を計画的に進められるだけでなく、国から手厚い支援を受けられます。具体的には「税制支援」「補助金の優遇」「金融支援」という3つの大きなメリットがあります。これらのメリットを最大限に活用することで、設備投資の負担を大幅に軽減し、企業の成長を加速させることが可能です。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
2.1 メリット1 固定資産税の特例措置が受けられる
先端設備導入計画の最大のメリットとも言えるのが、新規に取得した先端設備等にかかる固定資産税(償却資産税)が大幅に軽減される税制支援です。設備投資は多額の費用がかかるだけでなく、導入後も固定資産税が継続的に発生するため、この特例はキャッシュフローの改善に直結します。
具体的には、計画の認定を受けて導入した一定の要件を満たす機械装置や器具備品などの償却資産について、課税標準が一定期間、軽減されます。軽減割合や期間は、企業の賃上げ方針の表明有無によって異なります。
| 要件 | 軽減措置 |
|---|---|
| 通常の場合 | 取得から3年間、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減 |
| 賃上げ方針を表明した場合 | 以下の期間、固定資産税の課税標準を3分の1に軽減 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
例えば、取得価額3,000万円の機械装置(耐用年数10年、税率1.4%)を導入した場合、通常であれば初年度に約42万円の固定資産税がかかります。しかし、この特例(通常の場合)を使えば21万円に、さらに賃上げ方針を表明すれば14万円まで負担を抑えることが可能です。この差が3〜5年間続くため、企業経営に与えるインパクトは非常に大きいと言えるでしょう。詳細な要件については、中小企業庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。
2.2 メリット2 ものづくり補助金などの審査で加点や優遇がある
先端設備導入計画の認定は、国の主要な補助金を申請する際に大きなアドバンテージとなります。具体的には、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」や「事業再構築補助金」といった人気の補助金の審査において、加点措置を受けられるのです。
これらの補助金は、革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資などを支援するものですが、非常に人気が高く、採択されるには質の高い事業計画が求められます。審査では複数の項目で評価が行われますが、先端設備導入計画の認定を受けていることで「政策点」として加点され、採択の可能性が大きく高まります。
なぜなら、先端設備導入計画の認定を受けているということは、その事業計画が「国の定めた要件を満たし、生産性向上に資するものである」と市区町村から客観的なお墨付きを得ている証明になるからです。補助金の審査においても、計画の妥当性や実現可能性が高いと評価されやすくなります。設備投資と合わせて補助金の活用を検討している企業にとって、この加点措置は非常に価値のあるメリットです。
2.3 メリット3 日本政策金融公庫などからの金融支援
大規模な設備投資を行う際には、自己資金だけでは不足し、金融機関からの融資が必要になるケースがほとんどです。先端設備導入計画の認定は、こうした資金調達の場面においても有利に働きます。
計画認定を受けた中小企業は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大といった支援(金融支援)を受けることができます。これにより、プロパー融資(保証協会を通さない金融機関独自の融資)が難しい場合でも、民間金融機関からの融資が受けやすくなるのです。
また、日本政策金融公庫などの政府系金融機関からも、設備資金の融資を受けやすくなる場合があります。計画の実現に必要な運転資金や設備資金について、低利融資制度の対象となる可能性があるため、資金繰りの負担を軽減しながら計画的に事業を進めることができます。このように、税制や補助金だけでなく、融資という側面からも手厚いサポートが用意されている点が、本制度の大きな魅力です。
先端設備導入計画の対象となる中小企業者と設備
先端設備導入計画は、すべての中小企業が利用できるわけではありません。法律で定められた「中小企業者」の定義に合致し、かつ対象となる設備を導入する場合にのみ活用できます。ここでは、自社が制度の対象となるか、また導入したい設備が要件を満たすかを確認していきましょう。
3.1 対象となる中小企業者の定義と要件
先端設備導入計画の対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定されている法人または個人を指します。具体的には、以下の表に示す資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれか一方が、業種ごとに定められた基準以下である必要があります。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
このほか、個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合なども対象に含まれます。ただし、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は対象外となるため注意が必要です。
- 同一の大規模法人(資本金1億円超の法人等)に発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有されている法人
- 複数の大規模法人に発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有されている法人
詳細な要件については、中小企業庁のウェブサイトで確認することをおすすめします。(中小企業庁:先端設備等導入計画策定の手引き)
3.2 対象となる先端設備の種類と満たすべき要件
先端設備導入計画の対象となる設備は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるもので、以下の種類に分類されます。中古資産は対象外です。
| 設備の種類 | 最低取得価額(1台または1基あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
| ソフトウェア | 70万円以上 |
さらに、これらの設備は以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。
- 生産性向上要件(年平均の投資利益率5%以上)
導入する設備が、企業の労働生産性を向上させるものであることを示す必要があります。具体的には、その設備の投資利益率が年平均5%以上になることが見込まれる計画であることが求められます。この確認は、認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士など)が行います。 - 旧モデル比の生産性向上要件(年平均1%以上向上)
導入する設備が、一定期間内に販売が開始されたモデルであり、かつ旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するものである必要があります。この証明は、設備メーカーなどが加盟する工業会から「生産性向上設備等に係る仕様等証明書」を取得することで行います。
つまり、単に新しい設備を導入するだけでなく、「企業の収益性を高める投資であること」と「設備自体の性能が向上していること」の両方を客観的に証明する必要があるのです。
3.3 GPUサーバーも対象に
近年、生成AIの開発やデータ分析の需要急増に伴い、高性能なサーバー、特にGPU(Graphics Processing Unit)を搭載したサーバーへの投資を検討する企業が増えています。
こうしたニーズに応える形で、2024年度(令和6年度)の税制改正により、先端設備導入計画の対象設備に一定のサーバーが追加されました。
具体的には、コインランドリー業またはインターネット附随サービス業の用に供する「機械装置」として、以下の要件を満たすサーバーが対象となります。
- 中央演算処理装置(CPU)に代えて、またはCPUと併用して画像処理装置(GPU)が組み込まれたもの
- 主として生成AIの開発または利用に資するもの
これにより、これまで対象となりにくかったAI開発企業やデータセンター事業者、クラウドサービス事業者などが、GPUサーバー導入時に本制度を活用しやすくなりました。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で、非常に強力な後押しとなるでしょう。
先端設備導入計画の申請から認定までの流れを5ステップで解説
先端設備導入計画の認定を受けるまでの手続きは、一見すると複雑に感じるかもしれません。しかし、各ステップでやるべきことを正確に理解し、順を追って進めることで、スムーズに申請を完了させることができます。ここでは、計画の策定から税制優遇を受けるまでの具体的な流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。
4.1 ステップ1 計画の策定と認定経営革新等支援機関への事前確認
最初に行うべきは、「先端設備導入計画」そのものの策定です。この計画書には、どのような設備を導入し、それによって労働生産性をどれだけ向上させるかという具体的な目標を盛り込む必要があります。労働生産性の向上目標は、計画認定から3〜5年で年平均3%以上と定められています。
計画書を策定したら、次に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」による事前確認を受けます。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあるとして、国から認定を受けた公的な支援機関です。商工会議所や商工会、金融機関、税理士、公認会計士などがこれにあたります。
認定支援機関に策定した計画書を提出し、計画が要件を満たしているか、実現可能な内容であるかといった点について客観的な確認を受けます。内容に問題がなければ、認定支援機関から「事前確認書」が発行されます。この事前確認書は、市区町村への申請時に必須となる重要な書類です。
4.2 ステップ2 工業会による証明書の取得
固定資産税の特例措置を受けるためには、導入予定の設備が制度の対象要件を満たしていることを証明する「工業会証明書」の取得が必要です。この証明書は、設備メーカーを通じて、その設備を所管する工業会に発行を依頼するのが一般的です。
証明書には、以下の要件を満たしていることが記載されます。
- 一定期間内に販売されたモデルであること(最新モデルである必要はありません)
- 生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること
証明書の発行には時間がかかるケースもあるため、設備メーカーへの相談や依頼は、計画策定と並行して早めに進めることをお勧めします。なお、この工業会証明書は、市区町村への計画申請時に間に合わない場合でも、後日(賦課期日である1月1日まで)の提出が認められることがあります。詳細は申請先の市区町村にご確認ください。
4.3 ステップ3 市区町村へ先端設備導入計画を申請し認定を受ける
ステップ1と2で準備した書類が揃ったら、いよいよ設備を設置する事業所が所在する市区町村の担当窓口(商工課など)へ先端設備導入計画の認定申請を行います。申請に必要な主な書類は以下の通りですが、自治体によって追加の書類が求められる場合があるため、必ず事前に公式ウェブサイトや窓口で確認してください。
| 書類名 | 入手・作成方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 先端設備導入計画に係る認定申請書 | 市区町村のウェブサイトからダウンロード | 計画内容を具体的に記載します。 |
| 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 認定支援機関から発行 | ステップ1で取得した書類です。 |
| 工業会による証明書の写し | 設備メーカーを通じて工業会から取得 | 固定資産税の特例を受ける場合に必須です。 |
| (法人の場合)定款の写し、登記事項証明書 | 自社保管、法務局で取得 | 市区町村によって要否が異なります。 |
| (個人事業主の場合)開業届の写しなど | 自社保管 | 市区町村によって要否が異なります。 |
提出された計画書は市区町村によって審査され、内容が法令や導入促進基本計画に適合すると判断されれば、正式に認定され「認定書」が交付されます。審査期間は自治体によって異なりますが、数週間から1ヶ月程度が目安です。
4.4 ステップ4 計画認定後に設備を取得する
このステップは、制度を利用する上で最も重要な注意点を含みます。対象となる先端設備の取得は、必ず市区町村から計画の認定を受けた後に行わなければなりません。認定前に設備を発注・契約・購入してしまうと、たとえ後から計画が認定されたとしても、その設備は税制特例の対象外となってしまいます。
「取得」とは、購入だけでなく、リース契約の締結なども含まれます。中古資産は対象外です。必ず市区町村から「認定書」が交付された日付以降に、設備の契約・発注手続きを進めるように徹底してください。
この流れは、中小企業庁が公開している「先端設備等導入計画策定の手引き」にも明記されているため、申請前に必ず確認しておきましょう。
4.5 ステップ5 税務申告で特例の適用を受ける
計画の認定を受け、無事に設備を取得したら、最後の手続きとして税務申告を行います。固定資産税の特例を受けるためには、毎年1月1日時点の償却資産の所有状況を申告する「償却資産申告」の際に、特例の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して提出する必要があります。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 償却資産申告書 | 「課税標準の特例」の欄に適用条項を記載します。 |
| 先端設備導入計画に係る認定書の写し | 市区町村から交付されたものです。 |
| 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し | ステップ1で取得したものです。 |
| 工業会による証明書の写し | ステップ2で取得したものです。 |
| リース契約見積書の写し、固定資産税軽減額計算書の写し | リース会社から入手します。(リース契約の場合) |
これらの書類を、設備を設置した市区町村の税務担当部署へ、申告期限(通常は毎年1月31日)までに提出します。この手続きをもって、固定資産税の課税標準が軽減されることになります。申告漏れがないよう、経理担当者や顧問税理士としっかり連携して進めましょう。
申請前に知っておきたい先端設備導入計画の注意点
先端設備導入計画は、中小企業の設備投資を強力に後押しする非常に有用な制度ですが、申請や活用のプロセスでつまずきやすいポイントがいくつか存在します。税制優遇などのメリットを確実に受けるためには、これから解説する注意点を事前にしっかりと理解しておくことが不可欠です。これらのポイントを見落とすと、最悪の場合、計画の認定が受けられなかったり、認定が取り消されたりするリスクもありますので、細心の注意を払いましょう。
5.1 設備の取得は必ず市区町村の計画認定後に行う
先端設備導入計画を利用する上で、絶対に守らなければならない最も重要なルールが「設備の取得タイミング」です。対象となる設備は、必ず市区町村から先端設備導入計画の「認定」を受けた後に取得(購入やリース契約の締結)しなければなりません。
もし、市区町村の認定を受ける前に設備を取得してしまった場合、その設備は税制特例の対象外となり、固定資産税の軽減措置を受けることができなくなります。これは、多くの中小企業が陥りがちな失敗例であり、後から気付いても取り返しがつきません。申請準備と並行して設備メーカーと商談を進めることは問題ありませんが、発注や契約といった最終的な「取得」行為は、認定通知書が手元に届くまで絶対に行わないでください。
このルールは、中小企業等経営強化法という法律で定められており、例外は認められていません。正しい手順を下の表で確認し、スケジュール管理を徹底しましょう。
| 手順 | ステータス | 注意点 |
|---|---|---|
| 正しい流れ | ① 計画申請② 市区町村による認定③ 設備取得(発注・契約) | 税制特例の対象となります。 |
| 誤った流れ | ① 設備取得(発注・契約)② 計画申請③ 市区町村による認定 | 税制特例の対象外となります。 |
5.2 申請先の市区町村によって要件が異なる場合がある
先端設備導入計画は国の制度ですが、計画の申請受付や認定を行うのは、事業所が所在する各市区町村です。国が定めた大枠のルールに基づき、それぞれの市区町村が「導入促進基本計画」を策定し、それに沿って運用しています。そのため、申請先の市区町村によって、申請書の様式や必要書類、さらには独自の要件が設けられている場合があります。
例えば、以下のような点で違いが見られます。
- 申請書のフォーマットや添付書類の種類
- 労働生産性の向上率に関する目標値の設定基準
- 固定資産税の特例率(多くの自治体では条例によりゼロに軽減していますが、一部異なる場合があります)
- 申請の受付期間や審査にかかる標準的な期間
- 地域経済への貢献など、独自の加点要素
計画の策定を始める前に、必ず自社の事業所が所在する市区町村の公式ホームページを確認し、担当部署(商工課など)に問い合わせるようにしましょう。思い込みで準備を進めると、書類の不備で手戻りが発生し、設備導入のスケジュールに遅れが生じる可能性があります。詳細については、中小企業庁が公開している各市区町村の導入促進基本計画に関する情報も参考にしてください。
5.3 計画の変更や修正には手続きが必要
一度、先端設備導入計画の認定を受けた後でも、事業の状況変化により計画内容を変更せざるを得ないケースが出てくることがあります。例えば、「導入予定だった設備のモデルが変更になった」「設備の取得価格が想定より変動した」「新たに関連設備を追加する必要が生じた」といった場合です。
このような重要な変更が生じた場合、自己判断で計画と異なる設備を導入するのではなく、速やかに市区町村へ「計画変更申請」の手続きを行う必要があります。変更申請を怠ると、当初の計画と実態が異なることになり、認定が取り消され、税制優遇が受けられなくなる恐れがあります。
変更申請には、通常、変更申請書や変更後の計画書、そして認定経営革新等支援機関による確認書などが再度必要となります。手続きの詳細は市区町村によって異なるため、変更の必要性が出てきた段階で、まずは担当窓口に相談することが賢明です。ただし、社名や代表者名の変更といった軽微な変更については、届出のみで済む場合もあります。どのような変更が「重要な変更」に該当するのか、事前に確認しておきましょう。
まとめ
先端設備導入計画は、中小企業が生産性向上のための設備投資を行う際に活用できる国の支援制度です。最大のメリットは、新規取得した設備の固定資産税が軽減される特例措置を受けられる点にあります。さらに、ものづくり補助金といった国の補助金で加点措置が受けられたり、日本政策金融公庫から金融支援を受けやすくなったりする利点もあります。申請時は、必ず市区町村から計画の認定を受けた後に設備を取得するという手順を守ることが重要です。自社の設備投資に本制度を有効活用し、事業の成長につなげましょう。
Zerofieldでは、GPUサーバーを活用した節税をご案内しております。税務面でのご相談がございましたら、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。