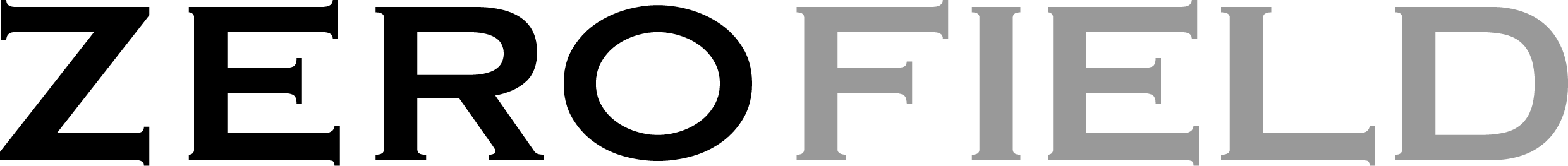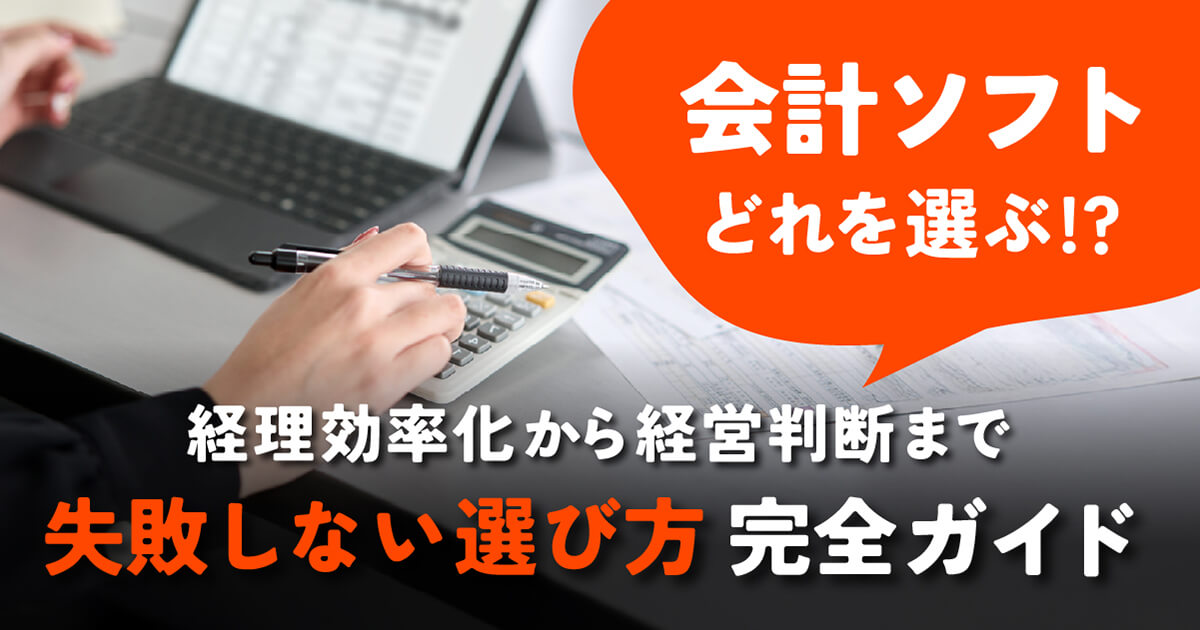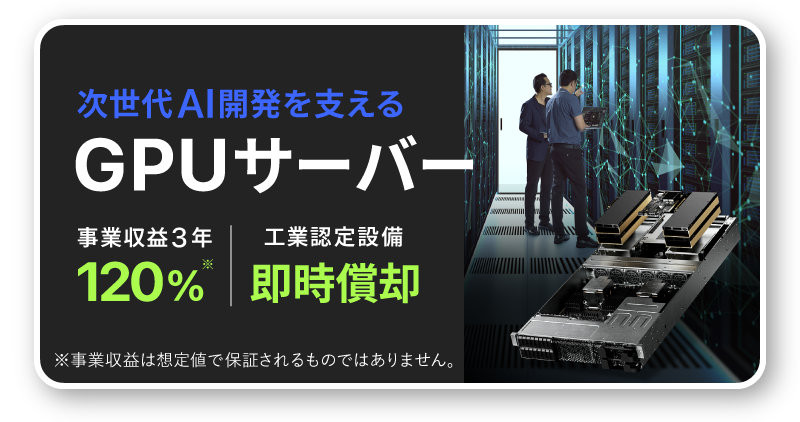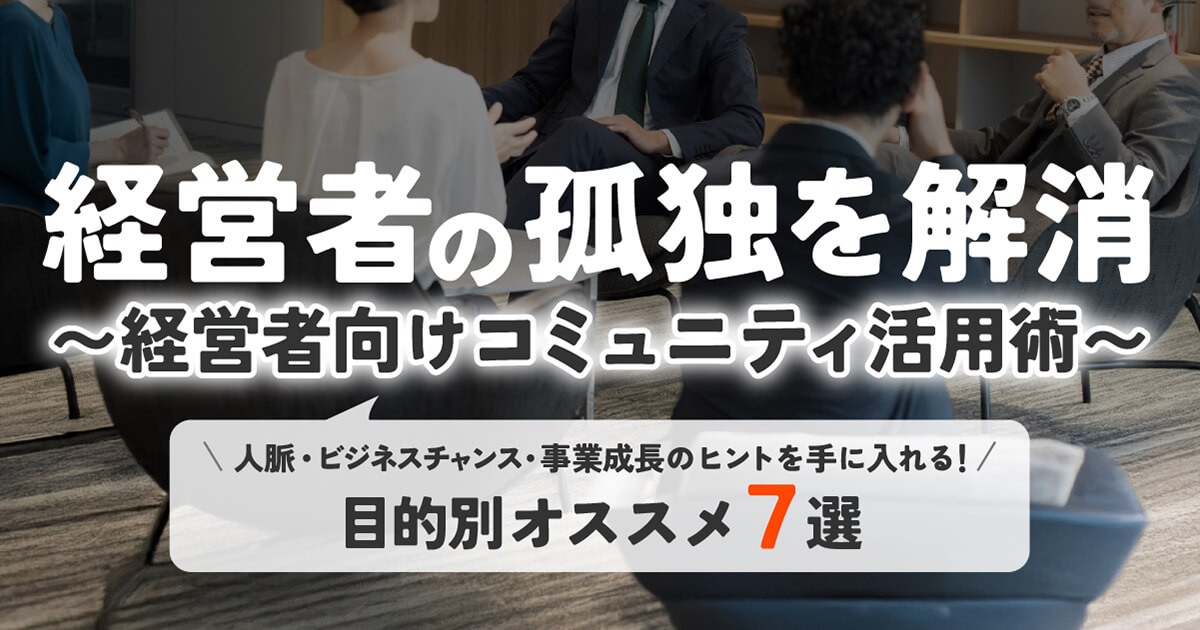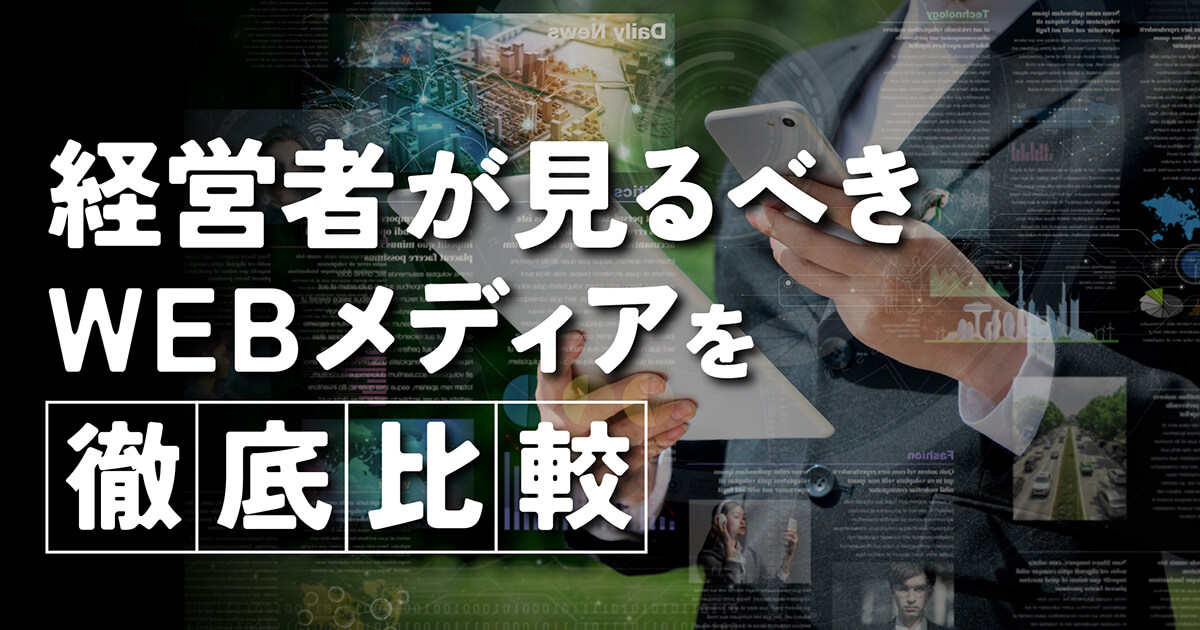「経理業務に追われて本業に集中できない」「自社の経営状況をリアルタイムで把握したいが、方法がわからない」そんな悩みを抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、会計ソフトの導入は、こうした課題を解決し、事業成長を加速させるための必須ツールです。特に、場所を選ばず法改正にも自動で対応できるクラウド型会計ソフトは、多忙な経営者にとって最適な選択肢と言えるでしょう。
この記事では、会計ソフトの基礎知識から、導入による5つの具体的なメリット、そして自社に最適なソフトを失敗せずに選ぶための5つのポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。さらに、freee会計やマネーフォワード クラウドといった人気ソフトを目的別に徹底比較。
この記事を最後まで読めば、あなたの会社の事業形態や規模にぴったりの会計ソフトが見つかり、経理業務の自動化と経営状況の可視化を実現できます。
経営者向け会計ソフトとは 基礎知識を解説
会社の経営者や個人事業主にとって、経理業務は事業の根幹をなす重要な作業です。しかし、日々の取引の記録から決算書の作成まで、その業務は多岐にわたり、専門知識も求められます。こうした複雑で時間のかかる経理業務を、誰でも簡単かつ正確に行えるようにサポートしてくれるツールが「会計ソフト」です。会計ソフトを導入することで、これまで手作業で行っていた帳簿付けや計算を自動化し、経営判断に必要な数値をリアルタイムで把握できるようになります。
特に、経理担当者を置く余裕のない中小企業や、本業に集中したい個人事業主にとって、会計ソフトはもはや必須の経営ツールと言えるでしょう。
1.1 会計ソフトでできること
現在の会計ソフトは、単に帳簿を作成するだけのツールではありません。経営を強力にバックアップする多彩な機能を備えています。主な機能を見ていきましょう。
- 日々の取引入力・自動仕訳:銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取得し、AIが勘定科目を推測して仕訳候補を提案します。これにより、手入力の手間とミスを大幅に削減できます。
- 帳票作成:見積書、請求書、納品書、領収書といった、事業に不可欠な書類を簡単な操作で作成・管理できます。作成した請求書の情報は自動で売掛金として計上されるため、入力漏れも防げます。
- 決算書・確定申告書類の作成:日々の取引データを基に、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの決算書を自動で作成します。また、法人税申告書や消費税申告書、個人事業主向けの確定申告書(青色申告・白色申告)の作成もサポートしてくれます。
- 経営状況の可視化:売上や経費の推移、資金繰りの状況などをグラフやレポートで分かりやすく表示します。リアルタイムで自社の財務状況を把握できるため、迅速な経営判断に繋がります。
- 法改正への対応:消費税の増税や、近年注目されている電子帳簿保存法やインボイス制度など、複雑な法改正にもアップデートで迅速に対応します。自力で情報を追いかける手間が省け、法令遵守の観点からも安心です。
1.2 クラウド型とインストール型の違い
会計ソフトは、提供形態によって大きく「クラウド型」と「インストール型」の2種類に分けられます。それぞれに特徴があり、どちらが自社に適しているかを見極めることが重要です。まずは両者の違いを比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | クラウド型 | インストール型 |
|---|---|---|
| 利用環境 | インターネット環境があればどこでも利用可能(PC、スマホ、タブレット) | ソフトをインストールした特定のPCのみ |
| データ保存場所 | 提供会社のサーバー(オンライン) | 自社のPCやサーバー(オフライン) |
| 料金体系 | 月額・年額課金のサブスクリプション制が多い | 買い切り制が多い(バージョンアップは別途費用) |
| 導入コスト | 低い(初期費用無料の場合が多い) | 高い(ソフト購入費用がかかる) |
| 法改正への対応 | 自動で無料アップデート | 追加費用を払ってのアップデートや買い替えが必要な場合がある |
| データ共有 | 容易(複数人で同時アクセス・編集が可能) | 手間がかかる(データの書き出し・取り込みが必要) |
| データバックアップ | 提供会社が自動で行う | 自分で行う必要がある |
1.2.1 クラウド型会計ソフトのメリット・デメリット
クラウド型は、インターネット経由でサービスを利用する形態です。近年、会計ソフトの主流はこちらになりつつあります。
【メリット】
- 場所やデバイスを問わない:インターネットさえあれば、オフィスのPC、自宅のノートPC、外出先のスマートフォンからでもアクセスできます。移動中や空き時間に経理作業を進められる手軽さが最大の魅力です。
- 導入が簡単で低コスト:ソフトウェアのインストールが不要で、アカウントを登録すればすぐに利用を開始できます。初期費用が安く、月額数千円から始められるプランが多いのも特徴です。
- 常に最新バージョンを利用可能:法改正や機能改善のアップデートが自動的に行われるため、ユーザーは常に最新の状態でソフトを利用できます。
- データ共有がスムーズ:経営者、経理担当者、顧問税理士などが同じデータに同時にアクセスできます。これにより、情報共有が円滑になり、ミスの削減や迅速なアドバイスに繋がります。
【デメリット】
- ランニングコストがかかる:月額または年額で費用が発生し続けるため、長期的に見るとインストール型より高くなる可能性があります。
- インターネット環境が必須:オフラインでは利用できないため、通信環境が不安定な場所では作業が滞るリスクがあります。
- カスタマイズ性に制限がある場合も:多くのユーザーが同じシステムを利用するため、自社の特殊な業務フローに合わせた細かいカスタマイズは難しい場合があります。
1.2.2 インストール型会計ソフトのメリット・デメリット
インストール型(パッケージ型)は、CD-ROMやダウンロードファイルを使って、自社のPCにソフトウェアをインストールして利用する従来ながらの形態です。
【メリット】
- 長期的なコストを抑えられる可能性:一度購入すれば、大きな法改正がなければ長期間使い続けられるため、ランニングコストがかかりません。
- オフラインでも作業可能:インターネット環境に依存しないため、場所を選ばず安定した環境で作業に集中できます。動作レスポンスが速いのも魅力です。
- セキュリティを自社で管理できる:会計データを社内のPCやサーバーに保存するため、外部のサーバーにデータを置くことに抵抗がある場合でも安心です。
【デメリット】
- 初期費用が高い:ソフトの購入費用として、数万円単位の初期投資が必要です。
- 利用場所が限定される:ソフトをインストールしたPCでしか作業ができないため、テレワークや外出先での利用には不向きです。
- 法改正への対応が有料・手動:法改正に対応するには、有料のバージョンアップ版を購入したり、自分でアップデート作業を行ったりする必要があります。
- データ共有やバックアップに手間がかかる:税理士とデータを共有する際は、データをエクスポートしてメールで送るなどの手間が発生します。また、PCの故障に備えたデータバックアップも自己責任で行わなければなりません。
経営者が会計ソフトを導入する5つのメリット
会計ソフトの導入は、単に経理作業を楽にするだけではありません。経営の根幹に関わる重要なデータを活用し、ビジネスを加速させるための強力な武器となります。ここでは、経営者が会計ソフトを導入することで得られる5つの具体的なメリットを、詳しく解説します。
2.1 メリット1 経理業務の自動化と効率化
創業期の経営者や中小企業では、経営者自身が経理業務を兼任することも少なくありません。しかし、請求書の発行、入金確認、領収書の整理、帳簿への記帳といった一連の作業は、非常に時間がかかり、本来注力すべきコア業務を圧迫する原因となります。
会計ソフトは、これらの煩雑な業務を自動化・効率化する機能を豊富に備えています。例えば、銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取得し、AIが勘定科目を推測して仕訳候補を提案してくれます。これにより、手作業での入力ミスを防ぎ、帳簿作成の時間を劇的に短縮できます。また、請求書の作成から送付、入金管理までを一元化できるため、売掛金の回収漏れを防ぐことにも繋がります。手作業による記帳や入力作業から解放され、経営者は本来注力すべき事業戦略の立案や営業活動に集中できるようになることは、最大のメリットと言えるでしょう。
2.2 メリット2 経営状況のリアルタイムな可視化
「今、会社の資金はいくらあるのか?」「今月の利益はどのくらいか?」といった経営状況を正確に把握できていますか?従来のExcelや手作業での管理では、試算表や損益計算書が完成するのは月末や期末になりがちで、経営判断が後手に回ってしまう危険性がありました。
会計ソフトを導入すれば、日々の取引データがリアルタイムで反映され、いつでも最新の経営状況をダッシュボードやレポートで確認できます。売上や費用の推移、利益率、資金繰りの状況などがグラフで分かりやすく表示されるため、直感的に会社の財務健全性を把握できます。これにより、「勘」に頼った経営から、データに基づいた的確な経営判断へとシフトできるようになります。資金ショートの危険性を早期に察知したり、投資のタイミングを見極めたりと、迅速で戦略的な意思決定を下すための強力なサポートとなります。
2.3 メリット3 確定申告や決算業務の負担を軽減
個人事業主にとっての確定申告、法人にとっての決算業務は、年に一度の大きな負担です。会計の専門知識が必要な上、膨大な書類を作成しなければならず、多くの時間と労力を要します。税理士に依頼するにも、相応のコストがかかります。
会計ソフトを使えば、日々の取引をルールに沿って入力するだけで、確定申告書や決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)が自動で作成されます。多くのソフトには、質問に答えていくだけで申告書類が完成するナビゲーション機能が搭載されており、会計知識に自信がない初心者でも安心です。また、作成したデータはe-Tax(国税電子申告・納税システム)と連携して電子申告できるため、税務署に行く手間も省けます。年に一度の煩雑で専門的な業務を、日々の簡単な入力作業の積み重ねで乗り越えられるため、精神的なストレスも大幅に軽減されるでしょう。
2.4 メリット4 法改正への迅速な対応
近年、消費税のインボイス制度や改正電子帳簿保存法など、会計・税務に関する法改正が頻繁に行われています。これらの変更に自力で対応し、正確な経理処理を行うのは非常に困難であり、対応を誤ると追徴課税などのペナルティを受けるリスクもあります。
特にクラウド型の会計ソフトは、専門家でなくても、複雑な法改正に自動で対応し、コンプライアンスを維持できる安心感を得られる点が大きな強みです。法改正が行われると、提供会社がシステムを迅速にアップデートしてくれるため、ユーザーは特別な作業をすることなく、常に最新の法令に準拠した会計処理を行えます。例えば、インボイス制度に対応した請求書の発行や、電子帳簿保存法の要件を満たしたデータ保存などが簡単に行えます。詳しくは国税庁のインボイス制度特設サイトや電子帳簿保存法関係のページもご確認ください。
| ソフトの種類 | 法改正への対応方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | 提供会社が自動でアップデート | 常に最新の法令に対応でき、手間がかからない | インターネット環境が必須 |
| インストール型 | アップデート版の購入や手動での更新が必要 | オフラインでも作業できる | 対応が遅れるリスクや追加コストが発生する場合がある |
2.5 メリット5 専門家とのデータ共有が容易に
顧問税理士や会計士に記帳代行や決算を依頼している場合、領収書の束やExcelファイルを郵送やメールで送るなど、データの受け渡しに手間がかかっていませんか?こうしたアナログなやり取りは非効率なだけでなく、情報のタイムラグや入力ミスを生む原因にもなります。
クラウド型会計ソフトの多くは、税理士や会計士などの専門家を招待し、同じデータをリアルタイムで共有できる機能を備えています。経営者が入力したデータを専門家がいつでも確認し、仕訳の修正やアドバイスを行えるため、コミュニケーションが非常にスムーズになります。これにより、月次決算の早期化や、より的確な経営アドバイスを受けることが可能になります。会計の専門家を強力な経営パートナーとして、より身近に活用できる環境が整うのです。
失敗しない経営者向け会計ソフトの選び方 5つのポイント
会計ソフトは一度導入すると乗り換えが難しいため、最初の選択が非常に重要です。自社に合わないソフトを選んでしまうと、かえって業務が非効率になったり、不要なコストが発生したりする可能性があります。ここでは、経営者が会計ソフト選びで後悔しないための5つの重要な選定ポイントを、具体的に解説します。
3.1 ポイント1 事業形態で選ぶ(個人事業主・法人)
まず最初に確認すべきなのは、ご自身の事業形態です。個人事業主と法人では、会計処理の目的や税務申告で求められる書類が大きく異なります。そのため、それぞれの事業形態に最適化されたソフトを選ぶことが、会計業務をスムーズに進めるための第一歩となります。
個人事業主・フリーランスの場合は、主な目的が「確定申告」になります。特に、最大65万円の特別控除が受けられる「青色申告」に対応しているかは必須のチェック項目です。多くの個人事業主向けソフトは、日々の取引入力から青色申告決算書、確定申告書Bの作成までをサポートしてくれます。比較的機能がシンプルで、低コストで利用できるプランが充実しているのが特徴です。
一方、法人の場合は、日々の記帳に加えて、株主や金融機関に提出するための「決算書(貸借対照表、損益計算書など)」の作成が義務付けられています。さらに、法人税申告書の作成支援機能も必要です。複数人での同時利用や、担当者ごとの権限設定、部門別の損益管理といった、より高度な機能が求められることも少なくありません。自社の事業形態に特化した会計ソフトを選ぶことが、効率的な経理体制を築く上で最も重要なステップと言えるでしょう。
3.2 ポイント2 会計知識のレベルで選ぶ
経営者ご自身や経理担当者の会計知識のレベルも、ソフト選びの重要な判断基準です。会計ソフトの操作性は、簿記の知識を前提としているものと、そうでないもので大きく異なります。
簿記の知識に自信がない、または会計業務が初めての初心者の方には、専門用語を極力使わず、直感的に操作できるソフトがおすすめです。例えば、「〇〇社から入金があった」「経費として〇〇を支払った」といった質問に答えていくだけで、自動的に適切な勘定科目に仕訳してくれる機能を持つソフト(freee会計などが代表的)は、初心者でも安心して利用できます。
簿記の知識がある、または経理経験者の方には、従来の会計帳簿に近い形式で、仕訳を直接入力できる自由度の高いソフトが適しています。貸方・借方といった簿記のルールに沿って入力できるため、これまでの経験を活かしながら効率的に作業を進めることが可能です(マネーフォワード クラウド会計や弥生会計などがこれにあたります)。
どちらのタイプが自分に合っているかを確認するためにも、多くのソフトが提供している無料トライアル期間を積極的に活用し、実際の画面で操作感を試してみることを強く推奨します。
3.3 ポイント3 必要な機能で選ぶ
会計ソフトには、基本的な記帳や申告書作成機能以外にも、業務を効率化するための様々な機能が搭載されています。自社の業務フローを洗い出し、どのような機能が必要かを事前に明確にしておきましょう。
まずは、ほとんどの事業者にとって必須と言える基本機能です。
- 銀行口座・クレジットカード連携:利用明細を自動で取得し、仕訳候補を提案してくれる機能。入力の手間を大幅に削減できます。
- レポート・経営分析機能:資金繰りの状況や収益の推移をグラフなどで可視化し、経営判断に役立てます。
さらに、事業内容に応じて以下のような連携機能があると、バックオフィス業務全体を効率化できます。
| 機能カテゴリ | 主な機能内容 | このような事業者におすすめ |
|---|---|---|
| 販売管理 | 見積書・納品書・請求書の作成、送付、入金管理 | 取引先への請求業務が多い事業者 |
| 経費精算 | レシートのスマホ撮影による自動読み取り、従業員の経費申請・承認フロー | 従業員による経費の立て替えが多い企業 |
| 給与計算 | 給与・賞与計算、勤怠管理連携、給与明細の発行、年末調整 | 従業員やアルバイトを雇用している事業者 |
| 外部サービス連携 | POSレジ、ECサイト(Amazon、楽天市場など)、決済サービスとのデータ連携 | 店舗での小売業やネットショップを運営している事業者 |
すべての機能が揃っている必要はありません。自社の事業規模や業務内容に合った機能を備えているか、また将来の事業拡大を見据えて機能を追加できる拡張性があるかという視点で選ぶことが大切です。
3.4 ポイント4 サポート体制の充実度で選ぶ
会計ソフトの導入初期や、決算期などの繁忙期には、操作方法や仕訳に関する疑問が生じやすいものです。特に会計業務に不慣れな場合、迅速で丁寧なサポートを受けられるかどうかは、ソフトを継続利用する上で極めて重要な要素となります。
サポートの形式には、以下のような種類があります。
- チャットサポート:最も手軽で、簡単な質問をすぐに解決したい場合に便利です。
- メールサポート:問い合わせ内容を文章で整理して送りたい場合や、営業時間外に連絡したい場合に適しています。
- 電話サポート:複雑な内容を直接オペレーターと話しながら解決したい場合に安心感があります。
- 画面共有サポート:オペレーターに自分のPC画面を見てもらいながら、具体的な操作方法を教えてもらえるため、問題解決がスムーズです。
注意すべきは、料金プランによって利用できるサポートの範囲(チャットのみ、電話も可など)や対応時間が異なる場合が多いという点です。安価なプランではサポートが限定的であることも少なくありません。契約前には、自分が求めるレベルのサポートがプランに含まれているかを必ず確認しましょう。また、ソフトの導入設定を支援してくれる有償の導入サポートや、提携する税理士を紹介してくれるサービスを提供しているかも、併せてチェックしておくと良いでしょう。
3.5 ポイント5 料金プランとコストで選ぶ
会計ソフトの料金体系は、主に月額または年額で支払うサブスクリプションモデルが主流です。機能や利用できるユーザー数に応じて、複数の料金プランが用意されています。
料金を比較する際は、単に月額料金の安さだけで判断するのではなく、以下の点を総合的に評価する必要があります。
| チェック項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 導入時に別途費用が発生するかどうか。クラウド型は無料の場合がほとんどです。 |
| 月額・年額料金 | 年払いにすることで割引が適用されることが多いです。長期利用を考えるなら年払いがおすすめです。 |
| 機能制限 | 安価なプランでは、必要な機能(例:請求書作成、部門別管理など)が使えない、またはオプション料金になっている場合があります。 |
| 利用人数・仕訳数 | プランごとに利用できる従業員数や、登録できる仕訳数に上限が設けられていないか確認しましょう。 |
目先の安さだけで選ぶと、後から必要な機能を追加するために結局上位プランに変更し、かえって割高になってしまうケースもあります。自社の事業規模や将来性を見据え、長期的な視点で最もコストパフォーマンスに優れたプランを選択することが賢明です。まずは無料プランやトライアルで使い勝手を試し、機能と価格のバランスが取れているかを見極めましょう。
【目的別】おすすめの経営者向け会計ソフトを徹底比較
ここまでの選び方のポイントを踏まえ、いよいよ具体的な会計ソフトを見ていきましょう。経営者の皆様が抱える課題や事業規模は多種多様です。そこでこの章では、「会計初心者・個人事業主向け」と「中小企業・法人向け」の2つのカテゴリに分け、それぞれ人気の高いおすすめ会計ソフトを徹底比較してご紹介します。自社の状況に最適なソフトを見つけることで、経理業務の効率化だけでなく、経営判断の迅速化にも繋がります。インボイス制度や電子帳簿保存法といった最新の法改正への対応状況も重要な選定基準となりますので、ぜひ参考にしてください。
4.1 初心者でも使いやすい人気の会計ソフト3選
まずは、簿記の知識に自信がない方や、初めて会計ソフトを導入する個人事業主・フリーランス、小規模法人の経営者におすすめのソフトを3つ厳選しました。いずれも直感的な操作が可能で、日々の経理業務から確定申告までをスムーズにサポートしてくれます。
4.1.1 freee会計
freee会計は、「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるfreee株式会社が提供するクラウド会計ソフトです。簿記の知識がなくても、質問に答えていくだけで確定申告書が作成できる手軽さが最大の特徴です。銀行口座やクレジットカードを連携すれば、取引明細を自動で取得し、AIが勘定科目を推測して仕訳を提案してくれるため、日々の記帳作業を大幅に削減できます。請求書の発行から売掛金の管理、入金確認まで一気通貫で行えるのも魅力です。
- 特徴:直感的なUI/UX、簿記知識不要の操作性、強力な自動仕訳機能
- こんな経営者におすすめ:
- 簿記や経理の知識が全くない方
- 日々の経理作業をとにかく自動化・効率化したい方
- スマートフォンアプリで隙間時間に作業したい方
- 料金プラン(個人事業主向け):
- スタータープラン:月額1,180円(年払い)〜
- スタンダードプラン:月額2,380円(年払い)〜
- 注意点:独自のインターフェースを採用しているため、簿記の知識がある方にとっては逆に使いにくく感じられる場合があります。
4.1.2 やよいの青色申告 オンライン
「やよいの青色申告 オンライン」は、会計ソフト業界で長年の実績と高いシェアを誇る弥生株式会社が提供するクラウドサービスです。シンプルで分かりやすい画面設計と、業界最大規模のカスタマーセンターによる手厚いサポート体制が魅力です。多くの会計事務所で導入されているため、顧問税理士とのデータ連携もスムーズに行えます。また、初年度無料で全ての機能が使えるキャンペーンを実施していることが多く、導入コストを抑えたい方にも最適です。
- 特徴:シンプルな画面構成、充実したサポート体制、高い信頼性と実績
- こんな経営者におすすめ:
- 初めての確定申告で不安が大きく、手厚いサポートを求める方
- 導入コストをできるだけ抑えたい方
- 顧問税理士が弥生シリーズを利用している方
- 料金プラン:
- セルフプラン:初年度0円、次年度以降8,800円/年
- ベーシックプラン:初年度半額 7,700円、次年度以降15,400円/年(操作サポート付き)
- 注意点:自動仕訳機能はfreee会計などに比べると、やや手動での設定が必要な場面があります。
4.1.3 マネーフォワード クラウド確定申告
「マネーフォワード クラウド確定申告」は、家計簿アプリでも有名な株式会社マネーフォワードが提供するサービスです。連携できる金融機関やクレジットカード、ECサイトなどのサービス数が業界トップクラスで、あらゆる取引データを自動で取得・仕訳できます。AIによる勘定科目の学習機能も優秀で、使えば使うほど自動化の精度が向上します。請求書作成や経費精算など、確定申告以外のバックオフィス業務に対応する機能も豊富に揃っています。
- 特徴:圧倒的な連携サービス数、高精度なAIによる自動仕訳、豊富な機能
- こんな経営者におすすめ:
- 複数の銀行口座やクレジットカードを利用している方
- データ連携による自動化を最優先したい方
- 将来的に法人化や事業拡大を視野に入れている方
- 料金プラン(個人事業主向け):
- パーソナルミニプラン:月額980円(年払い)〜
- パーソナルプラン:月額1,280円(年払い)〜
- 注意点:多機能なため、会計初心者の方には少し画面が複雑に感じられる可能性があります。
▼初心者・個人事業主向け会計ソフト 比較表
| ソフト名 | 特徴 | 料金(最安プラン/年払い) | 無料お試し | サポート |
|---|---|---|---|---|
| freee会計 | 簿記知識がなくても直感的に操作可能。自動化に強い。 | 要問合せ | 30日間無料 | チャット、メール |
| やよいの青色申告 オンライン | シンプルな画面と手厚いサポートが魅力。初年度無料。 | 要問合せ | 1年間無料 | 電話、チャット、メール(プランによる) |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 連携サービス数が豊富。AIの学習能力が高い。 | 要問合せ | 1ヶ月間無料 | チャット、メール |
4.2 中小企業・法人経営者におすすめの会計ソフト3選
次に、従業員を雇用している中小企業や、より高度な経営管理を求める法人経営者におすすめの会計ソフトをご紹介します。これらのソフトは、部門別会計や資金繰り管理、予算実績管理といった法人特有のニーズに応える機能を搭載しており、経営判断に役立つ詳細なレポートを作成できます。
4.2.1 マネーフォワード クラウド会計
個人事業主向けでも人気の「マネーフォワード クラウド」の法人向けサービスです。基本的な自動仕訳機能や連携サービスの豊富さに加え、複数人での同時利用、権限設定、仕訳承認ワークフロー、部門別会計など、組織での利用を前提とした機能が充実しています。また、「クラウド給与」や「クラウド経費」といった同シリーズのサービスと連携させることで、会計だけでなく人事労務や経費精算など、バックオフィス業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現できる点が最大の強みです。
- 特徴:バックオフィス業務全体をカバー、詳細な権限設定、豊富な経営分析レポート
- こんな経営者におすすめ:
- バックオフィス全体の効率化・DXを推進したい企業
- IPO(株式上場)を視野に入れているスタートアップ
- リアルタイムで詳細な経営状況を把握したい経営者
- 料金プラン(法人向け):
- スモールビジネスプラン:月額3,980円(年払い)〜
- ビジネスプラン:月額5,980円(年払い)〜
4.2.2 弥生会計 オンライン
デスクトップ版で絶大なシェアを誇る「弥生会計」のクラウド版です。長年のノウハウが凝縮された安定感と信頼性が特徴で、特に税理士や会計事務所からの支持が厚いです。デスクトップ版と遜色のない帳票出力機能や、手厚い「あんしん保守サポート」が付属するプランが用意されており、安心して利用できます。クラウドでありながら、デスクトップ版に近い操作感で利用できるため、従来のインストール型ソフトからの移行もスムーズです。
- 特徴:会計事務所での高い導入実績、安定したシステム、充実のサポート体制
- こんな経営者におすすめ:
- 顧問税理士とスムーズにデータ共有したい企業
- インストール型ソフトからの乗り換えを検討している企業
- システムの安定性や信頼性を最重視する経営者
- 料金プラン:
- セルフプラン:28,600円/年
- ベーシックプラン:41,800円/年(操作サポート付き)
4.2.3 勘定奉行クラウド
「勘定奉行クラウド」は、株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供する、中堅・中小企業向けのクラウド会計システムです。「奉行シリーズ」として高いブランド力と実績を持ち、特に内部統制やセキュリティを重視する企業に適しています。API連携によって様々な業務システムと柔軟に連携でき、企業独自の業務フローに合わせたカスタマイズ性が高いのが特徴です。電子帳簿保存法への完全対応や、複数税率、インボイス制度といった複雑な税制にも標準で対応しており、法改正にも安心して対応できます。
- 特徴:高い信頼性とブランド力、強固なセキュリティと内部統制機能、柔軟なAPI連携
- こんな経営者におすすめ:
- 従業員数が数十名以上の中小企業
- 厳格なセキュリティポリシーや内部統制が求められる企業
- 販売管理システムなど、他の基幹システムとの連携を重視する企業
- 料金プラン:
- iJシステム:月額10,000円〜
- ※企業の規模や利用機能に応じて個別見積もりとなる場合が多いです。
▼中小企業・法人向け会計ソフト 比較表
| ソフト名 | 特徴 | 料金(目安/年払い) | 対象企業規模 | 強み |
|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド会計 | バックオフィス全体のDXを推進。スタートアップに人気。 | 要問合せ | 小規模〜中堅企業 | 他サービス連携、経営分析 |
| 弥生会計 オンライン | 税理士との連携がスムーズ。安定性と信頼性が高い。 | 要問合せ | 小規模〜中小企業 | サポート体制、コスト |
| 勘定奉行クラウド | 内部統制やセキュリティに強い。中堅企業での実績豊富。 | 要問合せ | 中小〜中堅企業 | 内部統制、API連携 |
まとめ
本記事では、経営者向け会計ソフトの基礎知識から、導入するメリット、そして失敗しない選び方までを詳しく解説しました。会計ソフトは、単なる経理業務の効率化ツールにとどまらず、経営状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定をサポートする強力な経営基盤となります。
会計ソフトを導入することで得られる「経理業務の効率化」「経営状況の可視化」「申告業務の負担軽減」といったメリットは、多忙な経営者の時間と労力を大幅に削減します。自社に最適なソフトを選ぶためには、「事業形態」「会計知識のレベル」「必要な機能」「サポート体制」「コスト」の5つのポイントを総合的に比較検討することが成功のカギです。
今回ご紹介した「freee会計」「マネーフォワード クラウド」「弥生会計」などの人気ソフトは、多くが無料プランや体験期間を設けています。この記事を参考に、まずは気になるソフトを試してみて、操作性や機能性を体感し、自社の成長を加速させる最適なパートナーを見つけてください。メディアの記事と照らし合わせる」といったように、これらのツールを組み合わせることで、無理なく効率的な情報収集のサイクルを構築できます。
Zerofieldでは、節税検討している中小企業の経営者向けに節税商品としてAIのGPUサーバー、暗号資産マイニングに特化した高性能なマイニングマシンを提供しております。是非ご検討ください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。