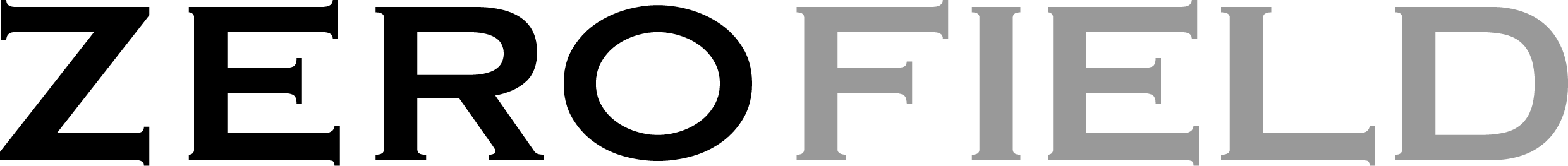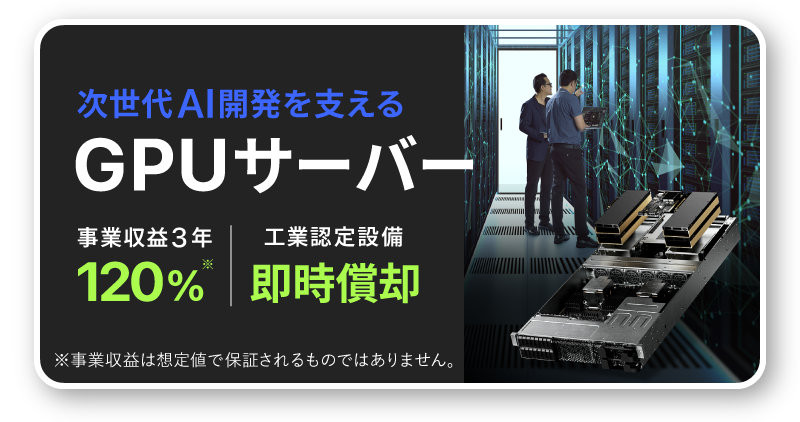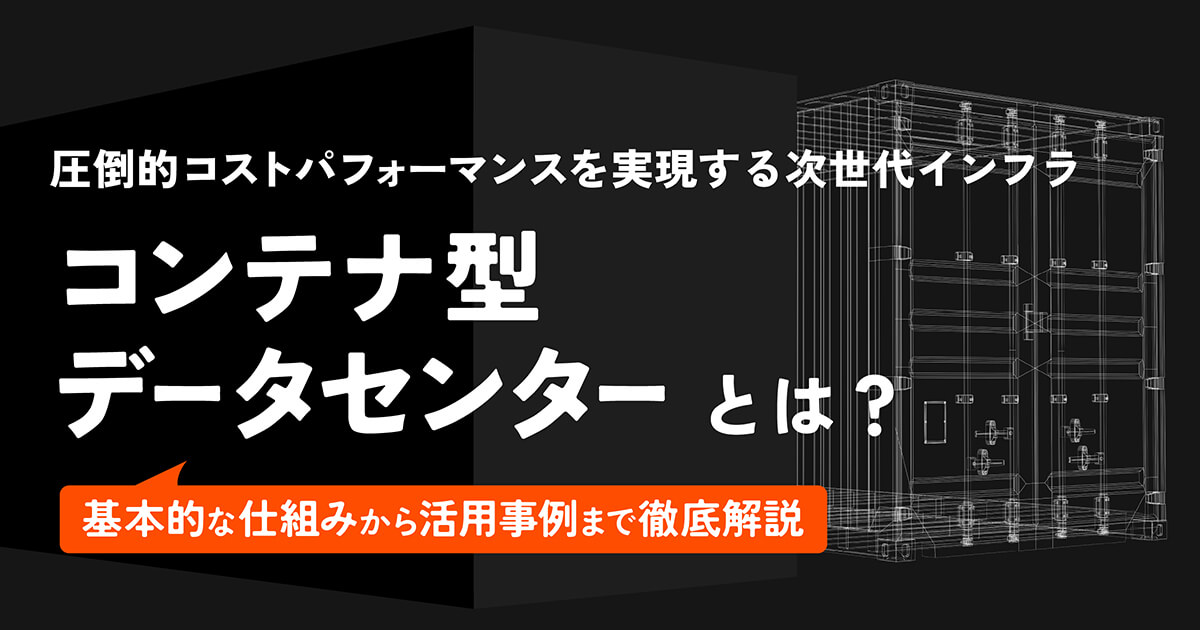「データセンターとは何か、クラウドや自社サーバーとの違いは?」そんな疑問を抱えていませんか。本記事では、IT社会の心臓部であるデータセンターの役割や機能、種類といった基礎知識を初心者にも分かりやすく解説します。結論として、データセンターは企業の重要なIT資産を災害や攻撃から守り、事業継続を支える堅牢な施設です。利用メリットや失敗しない選び方まで網羅しており、自社に最適なIT環境を検討するための知識が身につきます。
データセンターとは?IT社会を支える心臓部
データセンターとは、サーバーやネットワーク機器といったIT機器を安全かつ安定的に稼働させるために特化した建物や設備そのものを指します。私たちが日常的に利用するWebサイト、SNS、ネットショッピング、動画配信サービス、そして企業の基幹システムなど、あらゆるデジタルサービスのデータは、このデータセンターに集約・管理されています。
まさに現代のデジタル社会を24時間365日、休みなく支える「心臓部」ともいえる重要な施設です。堅牢な建物の中に、大量のサーバーを収納するラック、安定した電力供給設備、最適な温度・湿度を保つ空調設備、そして厳重なセキュリティシステムなどが備わっています。
1.1 データセンターの基本的な役割と目的
データセンターの最も基本的な役割は、企業や組織が保有する膨大なデジタルデータを安全に保管し、それを利用するための情報システムを安定して稼働させ続けることです。もしデータセンターがなければ、停電や災害、サイバー攻撃などによって簡単にサービスが停止し、社会活動や経済活動に甚大な影響が及ぶ可能性があります。
その主な目的は、企業が自社でサーバー等を管理する際に直面する、以下のような課題を解決することにあります。
- 事業継続性の確保:地震や火災などの災害時でもシステムを停止させないための耐震・防災設備を提供する。
- 情報資産の保護:不正な侵入やサイバー攻撃からサーバーやデータを守るための高度なセキュリティ環境を提供する。
- 運用負荷の軽減:専門の技術者が24時間体制でシステムの監視やメンテナンスを行い、企業のIT担当者の負担を減らす。
- コストの最適化:サーバー運用に必要な電源や空調などの設備投資や維持管理コストを、複数の利用企業で分担することで効率化する。
これらの役割を通じて、企業がITインフラの管理に煩わされることなく、本来の事業活動に専念できる環境を提供することが、データセンターの大きな目的です。
1.2 サーバーや自社運用(オンプレミス)との違い
「データセンター」という言葉を聞くと、「サーバー」や「オンプレミス」といった用語と混同してしまう方も少なくありません。それぞれの違いを理解することが、データセンターの役割を正確に把握する第一歩です。
まず、「サーバー」はデータやサービスを提供するコンピューター(機器)そのものを指します。一方で、「データセンター」は、そのサーバーを設置・運用するための専門的な「場所・施設」です。つまり、サーバーはデータセンターという建物の中にあるIT機器の一つ、という関係性になります。
そして、「オンプレミス」とは、企業が自社のオフィス内や建物内にサーバー室などを設けて、IT機器を自分たちで管理・運用する形態を指します。これに対して、データセンターを利用することは、ITインフラの管理を外部の専門施設に委託する「アウトソーシング」の一形態と言えます。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | データセンター利用 | 自社運用(オンプレミス) |
|---|---|---|
| 設置場所 | 専門事業者が管理する堅牢な施設 | 自社のオフィス内やサーバー室 |
| 初期コスト | 比較的低い(設備投資が不要) | 高い(建屋、電源、空調、セキュリティ設備等の投資が必要) |
| 運用管理 | データセンター事業者に委託可能(24時間365日監視) | 自社で全て対応(専門人材の確保が必要) |
| セキュリティ | 非常に高い(物理・情報両面で多重の対策) | 自社の対策レベルに依存 |
| 災害対策 | 高い(耐震・免震構造、自家発電設備など) | 自社の対策レベルに依存 |
| 拡張性 | 高い(ラックスペースや電力の追加が容易) | 低い(物理的なスペースや電源容量に制約) |
1.3 クラウドサービスとデータセンターの関係性
「データセンター」と「クラウド」も、よく混同されがちな言葉ですが、両者は密接な関係にあります。結論から言うと、私たちが利用しているクラウドサービスは、データセンターという物理的なインフラを基盤として成り立っています。
Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) といった大手クラウド事業者は、世界中の複数のデータセンターに膨大な数のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器を設置しています。そして、それらのITリソースを仮想化技術によって分割し、インターネットを通じてユーザーが必要な分だけ手軽に利用できるようにしたサービスが「クラウドサービス」です。
ユーザーから見た両者の違いは、利用する対象です。
- データセンター利用(ハウジングなど):サーバーなどの「物理的な機器」を設置する「スペース」や「電力」などを借りる。機器の管理責任は利用者側にあることが多い。
- クラウドサービス利用:仮想サーバーやデータベースといった「サービス(機能)」を借りる。物理的な機器を意識する必要がなく、管理もクラウド事業者に任せられる。
例えるなら、データセンターが「駐車場(スペース)」のレンタルだとすれば、クラウドは「レンタカー(すぐに使える機能)」のような関係です。どちらも企業のITインフラを支える選択肢ですが、管理範囲や柔軟性に大きな違いがあります。
データセンターの主要な機能と設備
データセンターは、単にサーバーを設置する建物を指すのではありません。企業や社会のITシステムを支える心臓部として、24時間365日、ノンストップで稼働し続けることを使命としています。そのため、内部にはサーバーやネットワーク機器を安定して動かすための、最先端かつ堅牢な機能と設備が整えられています。ここでは、データセンターが持つ主要な5つの機能と、それを支える具体的な設備について詳しく解説します。
2.1 安定した電力供給を支える設備
IT機器にとって電力は生命線です。オフィスで利用する一般的な商用電源だけでは、落雷による瞬断や災害時の停電といったリスクに対応できません。データセンターでは、いかなる状況でも電力供給が途絶えることのないよう、多重の防護策が講じられています。
2.1.1 無停電電源装置(UPS)と自家発電装置
データセンターの電力供給は、主に以下の設備によって冗長化(二重化以上の備えを持つこと)されています。
| 設備名 | 主な役割 | 詳細 |
|---|---|---|
| 無停電電源装置(UPS) | 瞬時の電力供給 | 内部に大容量バッテリーを備えた装置です。万が一、商用電源に瞬断や電圧低下が発生した際に、即座にバッテリーからの電力供給に切り替わります。これにより、自家発電装置が起動して安定するまでの数分間、サーバーを停止させることなく稼働させ続けることができます。 |
| 自家発電装置 | 長時間の電力供給 | 大規模な停電が発生した際に、データセンター内で電力を生み出す設備です。ディーゼルエンジンやガスタービンなどが用いられ、敷地内に備蓄された燃料で48時間や72時間以上といった長時間の連続稼働が可能です。これにより、大規模災害時でも事業を継続できます。 |
さらに、信頼性を高めるために、異なる変電所から電力を引き込む「2系統受電」や、電源設備全体を二重化する「N+1構成」「2N構成」といった設計が採用されています。
2.2 サーバーを守るための空調・冷却設備
サーバーやネットワーク機器は、稼働中に大量の熱を発生させます。この熱を適切に排出しなければ、機器は熱暴走を起こし、性能低下や故障、最悪の場合は火災の原因にもなりかねません。そのため、データセンターには強力かつ精密な空調・冷却設備が不可欠です。
データセンターでは、CRAC(Computer Room Air Conditioner)と呼ばれる専用の大型空調機を用いて、サーバールーム内の温度と湿度を常に一定(例:室温22℃前後)に保ちます。効率的な冷却を実現するため、「ホットアイル・コールドアイル」と呼ばれる手法が広く採用されています。
- コールドアイル:サーバーラックの前面(吸気側)を向かい合わせに配置し、床下から供給される冷気を集中させる通路。
- ホットアイル:サーバーラックの背面(排気側)を向かい合わせに配置し、排出された熱い空気を集めて効率的に回収・冷却する通路。
この配置により、冷気と暖気が混ざるのを防ぎ、無駄なくサーバーを冷却できます。近年では、AI開発などで利用される高性能GPUサーバーの高発熱に対応するため、水冷方式や、機器を特殊な液体に直接浸して冷やす液浸冷却といった次世代の冷却技術も導入が進んでいます。
2.3 堅牢なセキュリティ対策
データセンターは、企業の機密情報や顧客の個人情報といった重要な「情報資産」の保管庫です。そのため、物理的な侵入とサイバー攻撃の両面からデータを守るため、要塞ともいえる厳重なセキュリティ対策が施されています。
2.3.1 物理的セキュリティ(入退室管理・監視)
権限のない人物がサーバールームに侵入するのを防ぐため、何重もの物理的な障壁が設けられています。
- 立地・建物:データセンターの所在地は非公開の場合が多く、周囲をフェンスで囲い、監視カメラを多数設置しています。
- 入退室管理:建物入口からサーバールームに至るまで、ICカード認証、生体認証(指紋・静脈・顔認証など)を組み合わせた多段階の認証ゲートが設置されています。一人ずつしか通過できないサークルゲート(共連れ防止システム)も一般的です。
- 監視体制:警備員が24時間365日常駐し、施設内外を巡回・監視しています。監視カメラの映像も常に監視センターでチェックされ、録画されています。
- ラック管理:契約者ごとにサーバーラックが施錠されており、鍵やカードがなければ開けることはできません。
2.3.2 情報セキュリティ(防火壁・不正侵入検知)
物理的な防御だけでなく、ネットワークを通じたサイバー攻撃からシステムを守るための対策も万全です。
| セキュリティシステム | 役割 |
|---|---|
| ファイアウォール | 外部ネットワークからの不正なアクセスを遮断する「防火壁」の役割を果たします。 |
| IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム) | ネットワーク上の通信を監視し、サイバー攻撃の兆候や不正なアクセスを検知・通知(IDS)、あるいは自動的にブロック(IPS)します。 |
| WAF(Web Application Firewall) | Webアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃(SQLインジェクションなど)に特化して防御します。 |
これらのセキュリティ対策に加え、多くのデータセンターではDDoS攻撃対策サービスやマネージドセキュリティサービスなども提供しており、ユーザーは自社のセキュリティポリシーに合わせて高度な防御体制を構築できます。
2.4 高速で信頼性の高いネットワーク環境
データセンターは、インターネットの世界における主要な交通結節点(ハブ)としての役割も担っています。国内外の主要な通信事業者のバックボーン回線が集中しており、高速・大容量かつ低遅延のネットワーク接続を利用できます。
特に重要なのが「キャリアニュートラル」という特徴です。これは、特定の通信事業者に依存せず、複数の事業者の回線の中からユーザーが自由に選択して利用できることを意味します。これにより、以下のようなメリットが生まれます。
- 冗長性の確保:異なる通信事業者の回線を契約することで、一方に障害が発生してももう一方で通信を継続できる。
- コストの最適化:各社のサービスを比較し、最もコストパフォーマンスの高い回線を選択できる。
- 接続性の向上:特定のクラウドサービスやIX(インターネットエクスチェンジ)への閉域接続など、多様な接続オプションを利用できる。
2.5 災害から機器を守る防災・耐震設備
地震大国である日本において、データセンターの選定で最も重要視される要素の一つが災害対策です。データセンターは、大規模な地震や火災、水害といった自然災害が発生しても、そこに預けられたサーバーとデータを守り、事業を継続させるための強固な設備を備えています。
- 耐震・免震・制震構造:多くのデータセンターでは、建物と基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を設置する「免震構造」が採用されています。これにより、地面の揺れが直接建物に伝わるのを防ぎ、サーバールックへの衝撃を最小限に抑えます。建物の骨格を強化して揺れに耐える「耐震構造」や、ダンパーで揺れを吸収する「制震構造」よりも、サーバー機器への影響が少ないとされています。
- 火災対策:サーバールームでは、スプリンクラーのように水を噴射する消火設備は使用されません。IT機器にダメージを与えないよう、高感度の煙・熱感知器が火災を早期に検知し、窒素やアルゴンといった不活性ガスを噴射して消火する「ガス消火設備」が導入されています。
- 水害対策:ハザードマップで浸水リスクが極めて低い地域に立地しているほか、万が一に備えて防水扉や止水板を設置し、建物内への浸水を防ぐ対策が講じられています。
データセンターの種類とサービス形態
データセンターと一言でいっても、その特徴や提供されるサービスは多岐にわたります。企業の目的や予算、事業戦略に応じて最適な選択をするためには、どのような種類があるのかを理解することが重要です。データセンターは、主に「立地」と「サービス形態」という2つの軸で分類することができます。
ここでは、それぞれの分類について、特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
3.1 立地による分類:都市型データセンターと郊外型データセンター
データセンターがどこに建設されているかは、その性能やコスト、そして利用目的に大きく影響します。立地による分類では、主に「都市型」と「郊外型」の2種類に分けられます。
都市型は利便性に優れ、郊外型はコストや災害対策に強みを持つなど、それぞれに明確な特徴があります。以下の表で両者の違いを比較してみましょう。
| 分類 | 都市型データセンター | 郊外型データセンター |
|---|---|---|
| 特徴 | 企業のオフィスが集まる都市部やその近郊に立地。交通の便が良く、アクセス性に優れる。 | 地価や電気料金が比較的安価な郊外に立地。広大な敷地を確保しやすい。 |
| メリット | 物理的なアクセスが容易で、緊急時の駆けつけ対応が迅速。 主要なIX(インターネットエクスチェンジ)に近く、ネットワークの遅延が少ない。 金融機関の取引システムなど、低遅延が求められる用途に適している。 | 土地代や建設コスト、電気料金を抑えられるため、利用料金が安価な傾向にある。 都市部から離れているため、首都直下地震などの広域災害時のリスクを分散できる。 広大な敷地を活かした高い拡張性と、再生可能エネルギーの活用がしやすい。 |
| デメリット | 地価や人件費、電気料金が高いため、利用コストが高額になりやすい。 災害(特に地震や洪水)のリスクが比較的高いエリアに位置することがある。 敷地面積に限りがあり、大規模な拡張が難しい場合がある。 | 都心からのアクセスに時間がかかり、物理的なメンテナンスや緊急対応に不便。 都市型に比べ、ネットワーク遅延が若干発生する可能性がある。 周辺に利用できる公共交通機関が少ない場合がある。 |
| 主な用途 | オンラインゲーム、動画配信サービス、金融系のトレーディングシステム、企業の主要システム(本番環境) | バックアップサイト、ディザスタリカバリ(DR)サイト、大規模クラウドサービスの基盤、コンテンツアーカイブ |
3.2 サービス形態による分類
データセンターの利用方法は、事業者が提供するサービスの範囲によって大きく異なります。利用者は、自社のITリソースや専門知識、予算に合わせてサービス形態を選択します。代表的なサービスとして「ハウジング(コロケーション)」と「ホスティング」の2種類があります。
3.2.1 ハウジング(コロケーション)
ハウジングとは、データセンター事業者が提供するサーバースペース(ラック)、電源、空調、インターネット回線といった設備を借りて、利用者自身が所有するサーバーやネットワーク機器を設置・運用するサービスです。コロケーションとも呼ばれます。
利用者はサーバーやOS、アプリケーションを自由に選定・構築できるため、自社の要件に合わせた柔軟なシステム設計が可能です。一方で、機器の調達から設定、保守・運用までを自社で行う必要があるため、専門的な知識を持つ人材が不可欠です。オンプレミス(自社運用)でサーバーを管理していた企業が、より堅牢な設備やセキュリティを求めてデータセンターへ移行する際の主要な選択肢となります。
3.2.2 ホスティング(レンタルサーバー)
ホスティングとは、データセンター事業者が所有・管理するサーバーを、利用者がレンタルするサービス形態です。「レンタルサーバー」という名称で広く知られています。利用者はサーバー機器を自前で用意する必要がなく、初期投資を抑えて手軽に利用を開始できるのが最大のメリットです。
サーバーの物理的な管理やメンテナンスはすべて事業者が行うため、利用者はインフラ運用に関する負担が大幅に軽減されます。ただし、提供されるサーバーのスペックやOS、インストールできるソフトウェアには制約があり、ハウジングに比べてカスタマイズの自由度は低くなります。ホスティングは、提供形態によってさらにいくつかの種類に分かれます。
- 共有サーバー:1台の物理サーバーを複数のユーザーで共有して利用する形態。最も低コストですが、他のユーザーの利用状況によってパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。個人のブログや小規模なWebサイトの運営に向いています。
- 専用サーバー:1台の物理サーバーを1ユーザーが独占して利用する形態。リソースをすべて自社で使えるためパフォーマンスが安定しており、カスタマイズの自由度も高いですが、コストは高額になります。大規模なECサイトやアクセス数の多いメディアサイトなどで利用されます。
- VPS(Virtual Private Server/仮想専用サーバー):1台の物理サーバー上に複数の仮想的なサーバー環境を構築し、それぞれをユーザーが専有して利用するサービスです。共有サーバーの低コストさと、専用サーバーの自由度を両立したバランスの良いサービスとして人気があります。
以下の表で、ハウジングとホスティングの責任分界点や特徴の違いをまとめます。
| 項目 | ハウジング(コロケーション) | ホスティング(レンタルサーバー) |
|---|---|---|
| サーバー機器の所有権 | 利用者 | データセンター事業者 |
| 初期コスト | 高い(機器購入費が必要) | 低い(月額料金のみの場合が多い) |
| カスタマイズの自由度 | 非常に高い | 低い(プランによる制約あり) |
| 運用・管理の責任範囲 | ハードウェア、OS、ミドルウェア、アプリケーションなど広範囲 | 主にアプリケーションやコンテンツ(OSより下層は事業者が管理) |
| 向いている用途 | 独自のシステム構成、基幹システム、高いセキュリティ要件を持つシステム | Webサイト、ブログ、メールサーバー、開発環境、小〜中規模のWebサービス |
企業がデータセンターを利用するメリット・デメリット
サーバーやネットワーク機器などのITインフラを自社で運用する「オンプレミス」と比較して、データセンターの利用には多くのメリットがあります。一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。ここでは、企業がデータセンターを活用する際に知っておくべきメリットとデメリットを、多角的な視点から詳しく解説します。
まずは、メリットとデメリットの概要を一覧表で確認してみましょう。
| 比較項目 | メリット(データセンター利用) | デメリット(データセンター利用) |
|---|---|---|
| コスト | TCO(総所有コスト)を削減できる可能性がある。設備投資が不要で、資産をオフバランス化できる。 | 継続的なランニングコスト(月額利用料)が発生する。 |
| 事業継続性(BCP) | 耐震・免震構造、冗長化された電源・空調により、災害時でも安定稼働が見込める。 | 自社拠点から離れている場合、緊急時の駆けつけに時間がかかる。 |
| セキュリティ | 24時間365日の有人監視や生体認証など、物理的・情報的に高度なセキュリティを確保できる。 | セキュリティポリシーがデータセンターの規定に依存する部分がある。 |
| 運用・管理 | 専門スタッフによる24時間体制の運用監視により、自社の管理負担を大幅に軽減できる。 | 自社内にITインフラの運用ノウハウが蓄積されにくい。 |
| 拡張性 | 事業規模の拡大に合わせて、ラックスペースや電力を柔軟かつ迅速に拡張できる。 | 契約プランによっては、拡張に制限があったり、追加コストが高額になったりする場合がある。 |
| 物理アクセス | 専門家が管理するため、自社で物理的なメンテナンスを行う必要がほぼない。 | 機器に直接触れるためには、事前申請や移動が必要となり、自由度が低い。 |
4.1 データセンター活用の4つのメリット
それでは、企業がデータセンターを利用することで得られる具体的なメリットを4つのポイントに絞って見ていきましょう。
4.1.1 事業継続計画(BCP)の強化
企業にとって、事業の継続は最も重要な課題の一つです。データセンターは、地震や台風、洪水といった自然災害や、予期せぬ停電などのリスクから企業の重要なIT資産を守るために設計されています。
多くのデータセンターは、地盤の強固な場所に建設され、最新の耐震・免震構造を採用しています。また、電力供給は複数の変電所から受電し、万が一の停電に備えて大容量の無停電電源装置(UPS)や自家発電装置を完備。これにより、災害時でもサーバーを停止させることなく、事業を継続することが可能になります。これは、自社のオフィスビルやサーバールームでは実現が困難な、極めて高いレベルの可用性です。
4.1.2 運用コストと管理負担の削減
自社でサーバーを運用(オンプレミス)する場合、サーバー機器本体の費用だけでなく、設置場所の確保、電源設備、空調設備、セキュリティ対策、そしてそれらを24時間365日監視・運用するための人件費など、莫大な「TCO(総所有コスト)」が発生します。
データセンターを利用すれば、これらの設備投資や維持管理コストを大幅に削減できます。専門の技術者が24時間体制でインフラを監視・運用してくれるため、情報システム部門の担当者はサーバーの物理的な管理業務から解放され、より戦略的なコア業務に集中できるようになります。結果として、人件費の最適化と生産性の向上にも繋がります。
4.1.3 高度なセキュリティ環境の確保
企業の機密情報や顧客データを守るためには、堅牢なセキュリティ対策が不可欠です。データセンターでは、自社単独では構築が難しい高レベルなセキュリティ環境が提供されています。
物理的なセキュリティ面では、ICカードや生体認証による多段階の入退室管理、監視カメラによる24時間録画、警備員による常駐監視など、部外者の侵入を徹底的に防ぐ仕組みが整っています。また、情報セキュリティ面でも、ファイアウォールや不正侵入検知システム(IDS/IPS)などが導入されており、サイバー攻撃からシステムを保護します。ISMS認証(ISO/IEC 27001)など第三者機関の認証を取得している施設も多く、信頼性の高い環境でデータを預けることができます。
4.1.4 事業成長に合わせた高い拡張性
ビジネスの成長に伴い、必要なサーバーの台数やデータ量は増加していきます。オンプレミスの場合、サーバー増設のために電源容量が不足したり、設置スペースがなくなったりすると、大規模な工事や移転が必要となり、多大なコストと時間がかかります。
データセンターのハウジング(コロケーション)サービスを利用すれば、事業の成長に合わせてラックスペースや電力、ネットワーク帯域を柔軟に追加することが可能です。これにより、将来の事業拡大を見越した過剰な初期投資を抑え、必要な時に必要な分だけリソースを拡張する「スケーラビリティ」を実現できます。
4.2 データセンター利用時の注意点とデメリット
多くのメリットがある一方で、データセンターの利用にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。導入を決定する前に、これらの点を十分に理解しておくことが重要です。
4.2.1 利用コストの発生
最大のデメリットは、当然ながら利用コストが発生することです。データセンターの利用料金は、主にラックのスペース利用料、消費電力に応じた電気料金、インターネット回線の利用料などで構成され、毎月継続的に支払いが発生します。
特に、小規模なシステム構成の場合、オンプレミスで運用する方がトータルコストを安く抑えられるケースもあります。ただし、オンプレミスにかかる見えにくいコスト(空調の電気代、管理者の人件費、設備の減価償却費など)も考慮に入れた上で、長期的な視点での費用対効果を慎重に比較検討する必要があります。
4.2.2 物理的なアクセスの制約
データセンターは強固なセキュリティで守られているため、自社の機器であっても、オンプレミスのようにいつでも自由にアクセスできるわけではありません。
サーバーのメンテナンスや機器の交換などで物理的な作業が必要な場合、データセンターへの入館には事前申請が必要となり、手続きに時間がかかることがあります。また、データセンターが遠隔地にある場合は、移動時間と交通費も考慮しなければなりません。このデメリットを補うため、多くのデータセンターでは、スタッフが利用者に代わって機器の再起動やケーブルの抜き差しなどを行う「リモートハンドサービス」を提供しています。サービスの範囲や料金は事業者によって異なるため、契約前に確認しておくことが重要です。
データセンターの活用事例
データセンターは、単にサーバーを保管するだけの施設ではありません。その堅牢な設備と高度な運用体制を活かし、現代のIT社会を支える様々なサービスの基盤となっています。ここでは、データセンターが具体的にどのように活用されているのか、代表的な3つの事例を紹介します。
5.1 クラウドサービスの基盤
私たちが日常的に利用しているAmazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud (GCP) といったクラウドサービスは、物理的には世界中に点在する巨大なデータセンター群によって支えられています。これらのサービスは、データセンター内にある膨大な数のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器といったリソースを仮想化技術によって切り分け、インターネット経由でユーザーに提供しています。
データセンターが持つ高い可用性、拡張性、そして厳重なセキュリティが、クラウドサービスの安定性と信頼性を担保しているのです。ユーザーは自社で物理的なインフラを所有・管理する必要がなく、必要な時に必要な分だけリソースを利用できるというクラウドのメリットは、データセンターという強力な基盤があってこそ成り立っています。
| サービス種類 | 概要 | データセンターが提供する主なリソース |
|---|---|---|
| IaaS (Infrastructure as a Service) | サーバーやストレージなどのインフラ機能を提供するサービス | 仮想サーバー、ストレージ、ネットワーク、電力、空調 |
| PaaS (Platform as a Service) | アプリケーション開発・実行環境を提供するサービス | IaaSのリソースに加え、OS、ミドルウェア、データベース |
| SaaS (Software as a Service) | ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス | アプリケーションが稼働する全てのインフラとプラットフォーム |
5.2 AI・機械学習のためのGPUサーバー運用
近年、急速に発展しているAI(人工知能)や機械学習、特にディープラーニング(深層学習)の分野では、膨大な量のデータを並列処理するための高い計算能力が求められます。この計算処理に不可欠なのが、高性能なGPU(Graphics Processing Unit)を搭載したGPUサーバーです。
しかし、GPUサーバーは一般的なサーバーに比べて消費電力が非常に大きく、また高熱を発するという特性があります。そのため、一般的なオフィス環境や家庭での運用は、電力供給や冷却の面で極めて困難です。データセンターは、こうした課題を解決するための最適な環境を提供します。
- 大容量の電力供給:複数のGPUを搭載したサーバーも安定して稼働させられる、冗長化された電力設備。
- 高度な冷却設備:サーバーが高温になるのを防ぎ、性能を最大限に引き出すための効率的な空調・冷却システム。
- 高速ネットワーク:大量の学習データを高速に転送するための、広帯域で低遅延なネットワーク環境。
- 物理セキュリティ:高価なGPUサーバーや重要な研究データを盗難や破壊から守るための厳重な入退室管理。
これらの設備が整ったデータセンターを活用することで、企業や研究機関は自前で大規模な設備投資をすることなく、最先端のAI開発に集中できます。
5.3 暗号資産(仮想通貨)のマイニング
ビットコインなどに代表される暗号資産の取引を承認し、ブロックチェーンに記録する作業は「マイニング」と呼ばれます。このマイニングには、非常に複雑な計算を高速で解く必要があり、ASIC(特定用途向け集積回路)と呼ばれる専用のマイニングマシンが使用されます。
マイニングマシンもGPUサーバーと同様に、24時間365日稼働し続けることで膨大な電力を消費し、大量の熱を発生させます。個人が自宅で大規模なマイニングを行うのは、騒音、排熱、そして高額な電気代といった問題から現実的ではありません。そこで、マイニング事業の拠点としてデータセンターが活用されています。
データセンターでマイニングを行う主なメリットは以下の通りです。
- 電力コストの削減:データセンターは電力会社と特別高圧電力契約を結んでいる場合が多く、一般的な家庭用や業務用の電力に比べて電気料金の単価が安価です。これにより、マイニングの収益性を大きく左右する電力コストを大幅に削減できます。
- 最適な冷却環境:マイニングマシンの性能は温度に大きく影響されます。データセンターの高度な空調システムによってマシンを常に最適な温度に保つことで、故障リスクを低減し、安定したパフォーマンスを維持できます。
- 高度なセキュリティと安定稼働:停電対策(UPSや自家発電装置)や高速ネットワークはもちろん、厳重な物理セキュリティによって高価なマイニングマシンを盗難などのリスクから守ります。これにより、機会損失を防ぎ、安定した運用が可能になります。
このように、データセンターは特殊な要件を持つ機器の運用にも最適な環境を提供し、新たなビジネスの創出を支えています。
失敗しないデータセンターの選び方と比較ポイント
データセンターの選定は、企業のITインフラの安定性、セキュリティ、そして事業継続性を左右する極めて重要な意思決定です。しかし、数多くの事業者が多様なサービスを提供しているため、どのデータセンターが自社に最適かを見極めるのは容易ではありません。ここでは、データセンター選びで失敗しないための具体的な比較ポイントを4つの観点から詳しく解説します。
6.1 立地と災害リスクの確認
データセンターの物理的な場所は、運用効率と事業継続計画(BCP)の両面から最初に確認すべき重要な要素です。特に自然災害の多い日本では、災害リスクの低い立地を選ぶことが不可欠です。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 災害ハザードマップの確認:建設地が地震、津波、洪水、土砂災害などのリスクが低いエリアにあるかを確認します。各自治体が公開しているハザードマップが参考になります。
- 地盤の安定性:強固な地盤の上に建設されているか、液状化のリスクが低いかを確認します。データセンター事業者の公式サイトや資料で、地盤に関する情報が開示されていることが多いです。
- 交通アクセス:自社のオフィスからのアクセスが良いか、緊急時に技術者が駆けつけやすい場所にあるかを確認します。都市型データセンターはアクセス性に優れ、郊外型は災害リスクが低く大規模な設備を構えやすいという特徴があります。
- 電力供給の安定性:複数の変電所から電力供給を受けられるなど、電力インフラが安定しているエリアかどうかも重要なポイントです。
万が一の事態を想定し、本社や主要拠点から地理的に離れた場所にバックアップサイトとしてデータセンターを契約することも、有効なBCP対策となります。
6.2 信頼性を示す指標「ティア(Tier)」を参考にする
データセンターの信頼性や可用性を客観的に評価するための指標として、米国Uptime Instituteが定めた「ティア(Tier)」という基準が広く用いられています。Tierは1から4までの4段階で格付けされ、数字が大きいほど高い可用性を持つことを意味します。
Tierレベルはデータセンターの設備冗長性や耐障害性を示す重要な指標であり、自社のシステムの重要度に応じて適切なレベルを選択する必要があります。
| Tierレベル | 概要と冗長性 | 可用性(目標値) | 年間停止時間(目安) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 冗長性の考慮なし。単一経路での電力・冷却供給。メンテナンスや障害発生時にはシステムが停止する。 | 99.671% | 28.8時間以下 |
| Tier 2 | 基本的な冗長性を確保(N+1)。一部の設備は冗長化されているが、電力供給経路は単一。計画メンテナンス時にはシステム停止の可能性がある。 | 99.741% | 22時間以下 |
| Tier 3 | 完全な冗長性を確保(N+1)。電力・冷却供給経路が複数あり、メンテナンス中でもシステムを停止させることなく運用が可能(コンカレント・メンテナンス)。 | 99.982% | 1.6時間以下 |
| Tier 4 | 完全なフォールトトレラント(耐故障性)設計(2N+1)。全ての設備が二重化され、いかなる単一障害が発生してもシステム運用に影響を与えない。 | 99.995% | 26.3分以下 |
基幹システムやECサイトなど、停止が許されないミッションクリティカルなシステムにはTier 3以上が、開発環境や情報系システムなど、ある程度の停止が許容される場合はTier 2やTier 1が選択肢となります。
6.3 サービス内容とサポート体制
データセンターが提供するサービス内容と、万が一の際のサポート体制も重要な比較ポイントです。自社の運用体制に合わせて、必要なサービスが提供されているかを確認しましょう。
6.3.1 提供サービスの確認
ラックやスペースを借りるハウジング(コロケーション)が基本ですが、以下のような付加サービスも確認しましょう。
- リモートハンドサービス:現地に行けない場合に、データセンターのスタッフが再起動やケーブルの抜き差しといった簡単な物理作業を代行してくれるサービス。
- 監視サービス:サーバーやネットワーク機器の死活監視やパフォーマンス監視を代行するサービス。
- セキュリティサービス:ファイアウォールやWAF(Web Application Firewall)の運用・監視サービス。
- 接続サービス:特定のクラウドサービス(AWS、Azureなど)への閉域網接続サービスの有無。
6.3.2 サポート体制の確認
障害はいつ発生するかわかりません。24時間365日、迅速かつ的確に対応してくれるサポート体制が整っているかを確認します。
- 24時間365日の有人対応:専門知識を持つ技術者が常駐し、いつでも電話やメールで対応可能か。
- SLA(Service Level Agreement):サービスの品質保証制度。電源供給やネットワークの可用性、障害発生時の対応時間などが具体的に定められているかを確認します。
- 持ち込み機器の制約:データセンターによっては、設置できるサーバーのメーカーや消費電力、サイズに制限がある場合があります。自社で利用したい機器が問題なく設置できるか、事前に確認することが不可欠です。
6.4 コスト体系と契約形態
最後に、コストが予算に見合っているかを確認します。データセンターの利用料金は、複数の要素で構成されるため、総額で比較検討することが重要です。
6.4.1 コストの内訳
一般的に、データセンターのコストは以下のような項目で構成されます。
- 初期費用:契約時に発生する費用。ラックの設置工事費などが含まれます。
- 月額費用:
- ラック利用料:借りるラックスペース(1/4ラック、ハーフラック、フルラックなど)に応じた料金。
- 電力料金:サーバーが消費する電力に対する料金。契約アンペア数に応じた固定料金制や、使用量に応じた従量課金制があります。高負荷なサーバーを運用する場合は特に注意が必要です。
- ネットワーク料金:インターネット接続の帯域に応じた料金。
- その他オプション料金:リモートハンドサービスなどの付加サービスの利用料。
6.4.2 契約形態の確認
コストだけでなく、契約期間や条件も確認しましょう。
特に最低利用期間や解約時の条件は、将来の事業計画の変更に柔軟に対応できるかどうかに直結するため、契約前に必ず確認してください。事業の成長に合わせてラックスペースや電力を追加できるかといった拡張性も、長期的な視点で重要なポイントとなります。
まとめ
本記事では、データセンターの役割や機能、クラウドとの違いから選び方までを解説しました。データセンターは、サーバーなどのIT機器を安全に運用するための専門施設であり、現代のデジタル社会を支える心臓部です。安定した電源や空調、堅牢なセキュリティ、災害対策といった設備により、自社運用に比べて事業継続性を高め、管理負担を軽減できる点が大きなメリットです。自社の目的に合わせ、立地や信頼性の指標であるティアなどを比較検討し、最適なデータセンターを選びましょう。
ZerofieldではGPUサーバーを活用した節税をご案内しております。税務面でのご相談がございましたら、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
また、AIの受託開発も行っております。GPU等の環境構築のプロが企業にあったAI開発を推進いたします。
お困りの企業様は、ぜひこちらからご相談ください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。