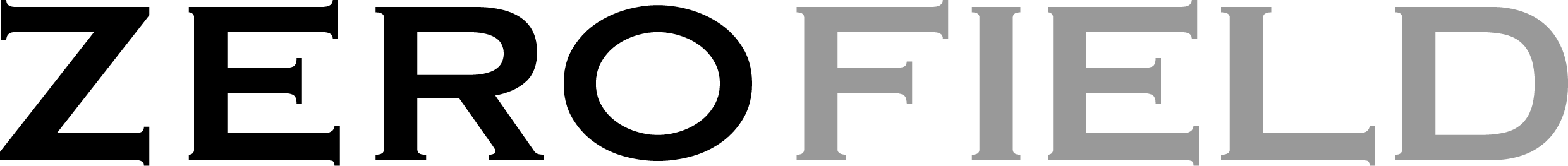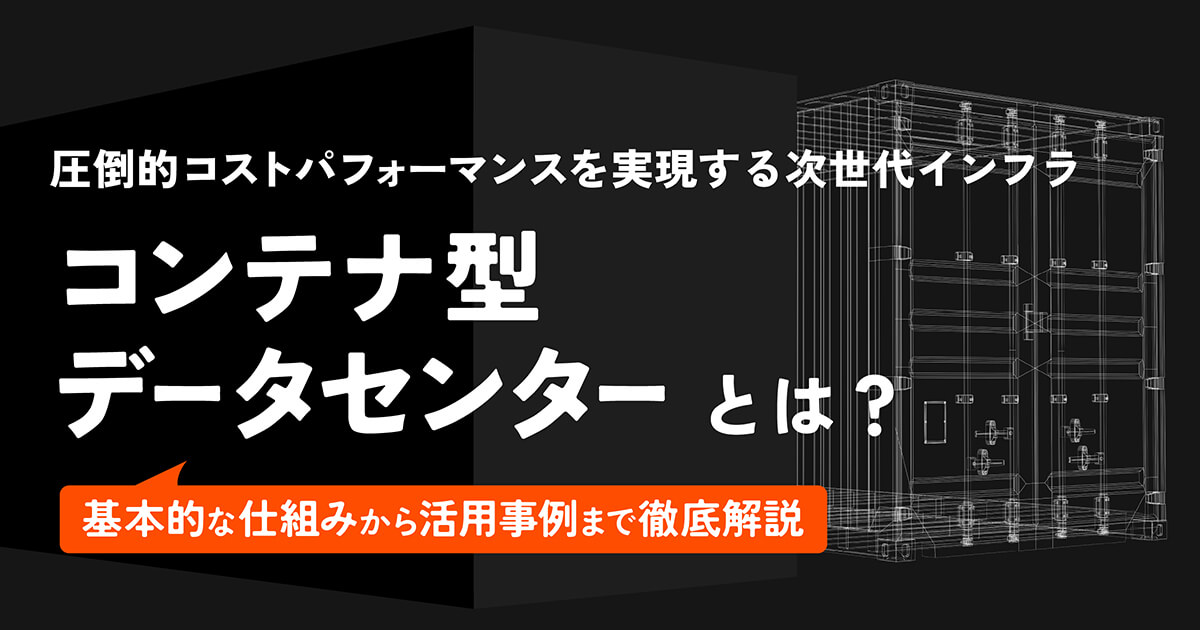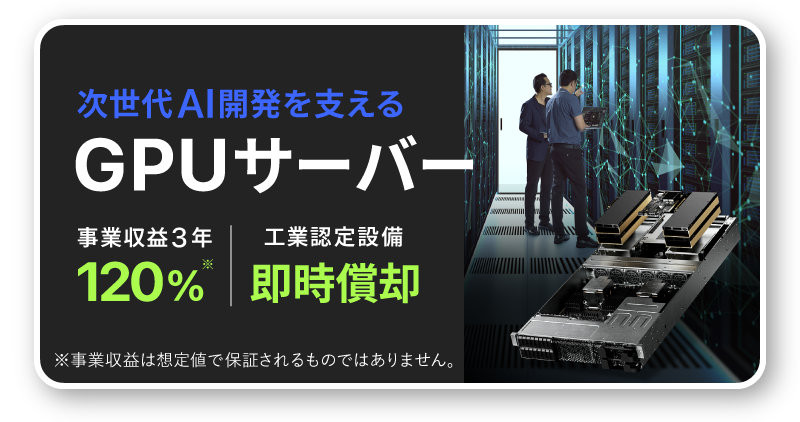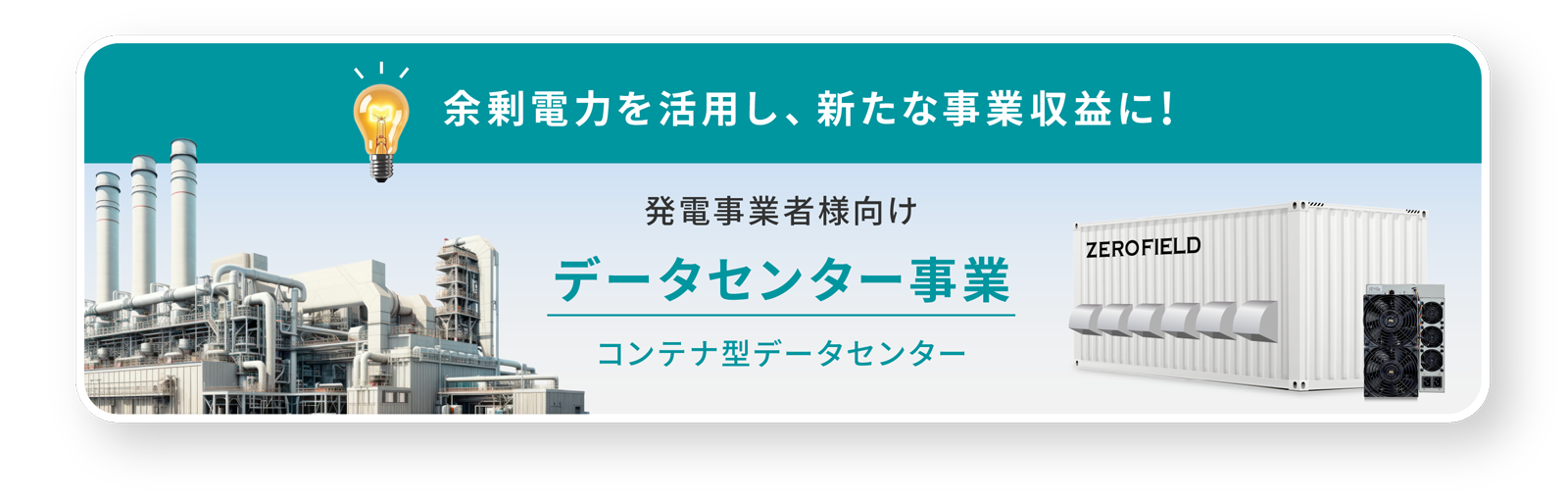コンテナ型データセンターは、DX推進やエッジコンピューティングの需要拡大を背景に、コスト削減と短納期を実現する次世代インフラとして注目を集めています。本記事では、その基本的な仕組みから従来のデータセンターとの違い、メリット・デメリット、具体的な活用事例までを徹底解説。導入を成功させるためのポイントが理解でき、自社に最適なデータセンター基盤を検討する上で必要な知識がすべて得られます。
コンテナ型データセンターとは 従来のデータセンターとの違い
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やIoTの普及に伴い、企業が扱うデータ量は爆発的に増加しています。こうした状況下で、従来のデータセンターの課題を解決する新たなインフラとして「コンテナ型データセンター」が大きな注目を集めています。この章では、コンテナ型データセンターの基本的な仕組みから、従来型のデータセンターや類似するモジュール型データセンターとの違いを分かりやすく解説します。
1.1 コンテナ型データセンターの基本的な仕組み
コンテナ型データセンターとは、国際標準規格(ISO)の輸送用コンテナの中に、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器といったIT機器と、それらを稼働させるための電源、空調、セキュリティ設備などを一体化して収容したデータセンターのことです。「データセンター in a Box」とも呼ばれ、必要な機能がすべて一つのパッケージにまとめられています。
コンテナ内部には、高密度に実装されたサーバーラック、PDU(電源分配装置)、UPS(無停電電源装置)、冷却効率の高い空調設備、さらには監視カメラや消火設備までが機能的に配置されています。これにより、工場で事前に製造・テストを完了させたコンテナを現地に輸送し、電源と通信回線を接続するだけで、短期間でデータセンターとして稼働させることが可能です。この「プラグアンドプレイ」に近い手軽さが、コンテナ型データセンターの大きな特徴です。
1.2 従来の建物型データセンターとの比較
コンテナ型データセンターの利点を理解するために、土地の選定から建物の建設までを行う従来の「建物型データセンター」と比較してみましょう。両者には、構築期間やコスト、拡張性などにおいて明確な違いがあります。
| 比較項目 | コンテナ型データセンター | 従来の建物型データセンター |
|---|---|---|
| 設置形態 | ISO規格の輸送用コンテナ | 免震・耐震構造の専用建物 |
| 構築期間 | 数ヶ月程度 | 1年~数年単位 |
| 初期コスト | 比較的低い(建屋が不要) | 高額(土地取得、建設費など) |
| 設置場所 | 工場の敷地、建物の屋上、駐車場など | 広大な土地と強固な地盤が必要 |
| 拡張性 | コンテナ単位での増設が容易 | 大規模な増改築が必要で困難 |
| エネルギー効率 (PUE) | 外気冷却などを活用しやすく、最適化しやすい | 建物全体の設計に依存し、大規模になりがち |
| 移設・撤去 | 比較的容易 | 原則として不可能 |
このように、従来のデータセンターが「大規模・集中型」で、一度建設すると場所や規模の変更が難しい不動産としての側面が強いのに対し、コンテナ型データセンターは「小規模・分散型」で、ビジネスの状況に応じて柔軟に配置・拡張できる動産としての特性を持っています。この機動性の高さが、変化の激しい現代のビジネス環境において大きなアドバンテージとなります。
1.3 モジュール型データセンターとの関係性
コンテナ型データセンターとしばしば混同される言葉に「モジュール型データセンター」があります。これらは全く別の概念ではなく、密接な関係にあります。
モジュール型データセンターとは、データセンターを構成する電源、空調、IT機器などの機能を、標準化された「モジュール(部品)」として工場で事前製造し、現地でブロックのように組み合わせて構築する方式の総称です。このアプローチにより、従来工法に比べて工期を大幅に短縮できるというメリットがあります。
そして、コンテナ型データセンターは、このモジュール型データセンターの一種と位置づけられます。特に、ISOコンテナという世界共通の輸送規格をモジュールの筐体として採用することで、輸送のしやすさと設置の自由度を最大限に高めた形態がコンテナ型データセンターなのです。
つまり、「モジュール型」という大きなカテゴリの中に、輸送性や屋外設置に特化した「コンテナ型」が存在すると理解すると良いでしょう。実際に、国内の大手ベンダーであるIIJは、コンテナ型をラインナップに含むモジュール型データセンターソリューション「IZmo」を提供しています。(参考: IIJ eco-SIRIUS/IZmo)
コンテナ型データセンターが注目される理由
従来の建物型データセンターが抱える課題を解決し、次世代のITインフラとして期待されるコンテナ型データセンター。なぜ今、これほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を象徴する3つの大きな潮流があります。
2.1 理由1 DX推進とデータ量の増加
現代のビジネスにおいて、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は企業の競争力を左右する重要な経営課題です。IoTデバイスの普及、AIによる高度なデータ解析、そして5G(第5世代移動通信システム)による超高速・大容量通信の本格化は、社会の利便性を飛躍的に向上させる一方で、企業が扱うデータ量を爆発的に増加させています。
この「データ爆発」とも呼べる状況に対し、従来の建物型データセンターでは対応が追いつかないケースが増えています。用地の確保から設計、建設、そしてサーバールームの稼働までには数年単位の時間と莫大なコストがかかるため、急増するデータ処理需要に迅速かつ柔軟に応えることが困難でした。
その点、コンテナ型データセンターは、必要なIT機器をあらかじめ工場でコンテナに組み込み、完成品として現地に輸送・設置します。これにより、数ヶ月という圧倒的な短期間でデータセンターを構築することが可能です。このスピード感は、変化の激しい市場でDXを推し進める企業にとって、ビジネスチャンスを逃さないための強力な武器となります。
2.2 理由2 エッジコンピューティングの需要拡大
クラウドコンピューティングは多くのメリットをもたらしましたが、全てのデータを遠隔地のクラウドへ送信して処理するモデルには限界も見え始めています。特に、自動運転車やスマート工場、遠隔医療といった分野では、コンマ数秒の通信遅延(レイテンシ)が重大な事故につながる可能性があり、リアルタイム性が極めて重要です。また、膨大なデータをすべてクラウドに送信すると、通信帯域を圧迫し、通信コストが増大するという課題もあります。
そこで注目されているのが「エッジコンピューティング」です。これは、データが発生する場所(エッジ)やその近くにサーバーを配置し、データ処理を行う仕組みです。クラウドにデータを送る前にエッジ側で一次処理を行うことで、通信遅延を最小限に抑え、通信量を削減できます。
コンテナ型データセンターは、その省スペース性と設置場所の自由度の高さから、エッジコンピューティングを実現するための物理インフラとして最適です。例えば、工場の敷地内や携帯電話の基地局の隣、店舗の駐車場など、データが発生するまさにその場所に「ミニデータセンター」を迅速に設置できます。これにより、低遅延かつ高セキュリティなデータ処理基盤を、必要な場所に柔軟に配置することが可能になるのです。
| 比較項目 | クラウドコンピューティング | エッジコンピューティング |
|---|---|---|
| データ処理場所 | インターネット経由の遠隔地にあるデータセンター | データ発生源の近く(デバイスの近傍) |
| 通信遅延(レイテンシ) | 大きい(物理的な距離が遠いため) | 小さい(物理的な距離が近いため) |
| 通信データ量 | 多くなりがち | 必要最低限に抑制可能 |
| 適した用途 | ビッグデータ分析、ファイル保管、Webサービスなど | 自動運転、スマート工場、遠隔医療、リアルタイム監視など |
2.3 理由3 BCP対策や災害復旧への貢献
地震や台風、集中豪雨といった自然災害が頻発する日本において、BCP(事業継続計画)の策定はすべての企業にとって不可欠です。万が一、メインのデータセンターが被災しシステムが停止してしまえば、事業の継続が困難になるだけでなく、顧客や社会に多大な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、多くの企業がDR(ディザスタリカバリ:災害復旧)サイトとして、メイン拠点から地理的に離れた場所にバックアップ用のデータセンターを構築しています。しかし、従来の建物型でDRサイトを構築するには、メイン拠点と同様に多額の初期投資と長い準備期間が必要となり、特に中堅・中小企業にとっては大きな負担となっていました。
コンテナ型データセンターは、この課題に対する有効な解決策となります。従来の建物型に比べて低コストかつ短納期でDRサイトを構築できるため、これまでコスト面で二の足を踏んでいた企業でも、堅牢なバックアップ体制を整備しやすくなります。また、コンテナ単位で増設できるため、事業規模の成長に合わせてスモールスタートで始められる点も魅力です。災害に強い事業基盤を構築し、企業のレジリエンス(回復力)を高める上で、コンテナ型データセンターは非常に重要な役割を担います。
コンテナ型データセンターの5つのメリット
コンテナ型データセンターは、従来の建物型データセンターが抱えていた課題を解決し、現代のビジネスニーズに応える多くのメリットを提供します。ここでは、導入を検討する上で特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。
3.1 メリット1 短納期での構築を実現
コンテナ型データセンターが持つ最大のメリットの一つが、圧倒的な導入スピードです。従来の建物型データセンターは、土地の選定から建物の設計、建設、そして内部のインフラ構築まで、プロジェクト開始から稼働までに1年以上の期間を要することが一般的でした。
一方、コンテナ型データセンターは、サーバーラック、空調設備、電源(UPS)、セキュリティシステムといった必要なコンポーネントが、あらかじめ工場でISOコンテナ内に組み込まれた状態で出荷されます。これを「プレハブ型」や「工場生産型」と呼びます。現地での作業は、基礎工事と電源やネットワークの接続が中心となるため、発注からわずか数ヶ月という短期間での導入が可能です。この迅速なデプロイメントにより、市場の変化に素早く対応し、ビジネスチャンスを逃すことなくITインフラを拡張できます。
3.2 メリット2 初期投資と運用コストの削減
コスト効率の高さも、コンテナ型データセンターが選ばれる大きな理由です。コストは「初期投資(CAPEX)」と「運用コスト(OPEX)」の両面で削減効果が期待でき、結果としてTCO(総所有コスト)を大幅に圧縮できます。
まず初期投資については、データセンター専用の建物を建設する必要がないため、巨額の建設費用を根本的に削減できます。また、ビジネスの需要に応じてコンテナ単位で段階的に増設できるため、将来の不確実な需要を見越した過剰な先行投資を避ける「スモールスタート」が可能です。
運用コスト面では、特に電気代の削減効果が顕著です。コンテナという密閉された狭い空間に最適化された高効率な空調システムが採用されており、サーバーの発熱を局所的に効率よく冷却できます。これにより、データセンターのエネルギー効率を示す指標であるPUE(Power Usage Effectiveness:電力使用効率)を低く抑えることができます。一般的なデータセンターのPUEが1.5〜2.0程度であるのに対し、コンテナ型ではPUE 1.2前後という高いエネルギー効率を実現する製品も少なくありません。
| 項目 | 従来型データセンター | コンテナ型データセンター |
|---|---|---|
| 初期投資 (CAPEX) | 土地取得、建物建設、インフラ設備など高額になりがち | 建物が不要なため大幅に削減可能。スモールスタートに適している |
| 運用コスト (OPEX) | 広大な空間全体の空調などにより電気代が高くなる傾向 | 高効率な空調によりPUEが低く、電気代を抑制できる |
| TCO (総所有コスト) | CAPEX・OPEXともに高額になる可能性がある | CAPEX・OPEXの両方を削減し、TCOを最適化しやすい |
3.3 メリット3 高い拡張性と柔軟なスケーラビリティ
ビジネスの成長やデータ量の増加に合わせて、ITインフラを柔軟に拡張できるスケーラビリティは、現代の企業にとって不可欠です。コンテナ型データセンターは、この要求に見事に応えます。
サーバー能力の増強が必要になった場合、新たなコンテナを追加で設置し、既存のシステムに接続するだけで簡単にスケールアウトが可能です。これは、レゴブロックを組み合わせるような感覚でインフラを拡張できることを意味します。従来のデータセンターのように、増設のために大規模な工事を行ったり、サービスを長時間停止したりする必要はありません。このモジュール性により、ビジネスの成長曲線に合わせて、俊敏かつシームレスにITリソースを増強していくことができます。逆に、プロジェクトの終了などに伴いリソースが不要になった場合は、コンテナを撤去・移設・売却するといった柔軟な対応も可能です。
3.4 メリット4 省スペースと設置場所の自由度
コンテナ型データセンターは、ISO規格の輸送用コンテナをベースに設計されているため、サイズが標準化されており、設置に必要な面積を最小限に抑えることができます。これにより、従来のデータセンターでは考えられなかったような場所への設置が可能になります。
例えば、工場の敷地内、オフィスの駐車場、建物の屋上といった既存の遊休スペースを有効活用できます。専用の建物を建てるための広大な土地を確保する必要がないため、地価の高い都市部や、データ発生源のすぐ近くにサーバーを置きたい場合に大きなアドバンテージとなります。また、トレーラーによる輸送が容易なため、災害時の臨時拠点や、イベント会場での一時的なインフラとしても活用でき、その機動性は大きな魅力です。
3.5 メリット5 高いエネルギー効率で環境にも配慮
前述の通り、コンテナ型データセンターは非常に高いエネルギー効率を誇ります。これはコスト削減だけでなく、企業の環境に対する取り組み、すなわちサステナビリティやSDGsの観点からも極めて重要です。
高密度に実装されたサーバーを効率的に冷却するため、外気を活用するフリークーリングや、局所的な空調制御技術が用いられます。これにより、データセンター全体の消費電力を大幅に削減し、PUE値を改善します。低いPUEは、IT機器が消費する電力以外の電力(主に空調や電源設備)が少ないことを意味し、CO2排出量の削減に直結します。環境負荷の低減は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で重要な要素であり、コンテナ型データセンターの導入は、「グリーンIT」を推進し、企業の環境評価を高める上でも有効な一手となり得ます。
導入前に知るべきコンテナ型データセンターのデメリットと対策
コンテナ型データセンターは、短納期やコスト削減といった多くのメリットを持つ一方で、導入前に必ず理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、特に重要な「物理セキュリティ」と「設置環境」という2つの側面に焦点を当て、具体的な課題とその対策を詳しく解説します。
4.1 デメリット1 物理的なセキュリティ対策
コンテナ型データセンターは、多くの場合、屋外や建物の敷地内といった人の目が届きにくい場所に単独で設置されます。そのため、堅牢な建物に守られた従来のデータセンターと比較して、物理的な破壊や不正侵入に対するリスクが高まる可能性があります。悪意のある第三者によるコンテナ筐体の破壊、ドアの破壊、あるいは内部設備への直接的な攻撃といった脅威を想定し、万全の対策を講じることが不可欠です。
また、無人での運用が基本となるケースが多いため、侵入や異常をいかに迅速に検知し、対応するかの体制構築も重要な課題となります。これらのセキュリティリスクを軽減するためには、多層的な防御策を組み合わせることが求められます。
| 課題(デメリット) | 具体的な対策例 |
|---|---|
| 物理的な侵入リスク | 高強度な鋼材で作られた、破壊行為に強いコンテナ筐体を選定する。 監視カメラ(CCTV)、赤外線センサー、動体検知センサー、振動センサーなどを複数組み合わせ、コンテナの周囲と内部を24時間監視する。 敷地全体をフェンスやゲートで囲い、部外者の侵入を物理的に防ぐ。 |
| 不正なアクセス・入室 | ICカード認証、生体認証(指紋、静脈など)、暗証番号を組み合わせた多要素認証による入退室管理システムを導入する。 誰が・いつ・どの区画に入退室したかを厳格に記録・管理し、定期的な監査を行う。 |
| 無人運用時の対応遅延 | 各種センサーが異常を検知した際に、管理者へ自動で通報する遠隔監視システムを構築する。 警備会社と連携し、異常発生時に警備員が駆けつけるサービスを契約する。 |
4.2 デメリット2 設置環境の制約と事前調査の重要性
「コンテナを置くだけ」という手軽なイメージがあるかもしれませんが、実際には設置にあたって多くの制約が存在します。これらの条件を無視して導入計画を進めると、後から法令違反が発覚したり、想定外のコストが発生したりするため、専門家を交えた綿密な事前調査(サイトサーベイ)が成功の鍵を握ります。
特に、コンテナが建築基準法における「建築物」と見なされるかどうかは、手続きやコストに大きく影響する重要なポイントです。屋根や柱があり、土地に定着していると判断された場合、建築確認申請が必要となります。また、屋外に設置する場合、直射日光による温度上昇、台風や豪雨、積雪、沿岸部では塩害など、過酷な自然環境への対策も考慮しなければなりません。
| 確認項目 | 具体的な内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 法規制の確認 | 建築基準法、消防法、各自治体の条例(景観条例など)への準拠を確認する。 | コンテナが「建築物」に該当するかどうかで、建築確認申請の要否が決まります。必ず自治体の建築指導課や専門家(建築士など)に事前相談してください。 |
| 設置場所の物理的条件 | コンテナ本体と冷却用の室外機を設置する十分なスペース、地盤の強度、大型トラックやクレーン車が進入・作業できる搬入経路を確保する。 | 地盤が軟弱な場合は、基礎工事が必要となり追加コストが発生します。搬入経路に電線や樹木などの障害物がないかも確認が必要です。 |
| インフラの確保 | サーバーや空調設備を稼働させるための十分な受電容量、安定した通信を確保するためのネットワーク回線を確認する。 | 電力や通信インフラが不足している場合、引き込み工事が必要になります。将来的なサーバー増設も見越した容量を計画することが重要です。 |
| 周辺環境への配慮 | 冷却ファンなどから発生する騒音や、室外機からの排熱が近隣のオフィスや住宅に与える影響を評価する。 | 設置場所によっては、防音壁の設置や低騒音タイプの機器選定が求められる場合があります。 |
| 自然環境への対策 | ハザードマップで浸水や土砂災害のリスクを確認する。また、塩害、積雪、雷など、地域特有の気候条件への対策を検討する。 | 沿岸部では防錆・防食塗装が施された筐体を、豪雪地帯では耐荷重性能の高い筐体を選ぶなど、設置環境に応じた仕様選定が不可欠です。 |
コンテナ型データセンターの活用シーンと国内の導入事例
コンテナ型データセンターは、その理論的なメリットだけでなく、すでに国内の様々なビジネスシーンで実用化が進んでいます。従来のデータセンターでは対応が難しかった課題を解決するソリューションとして、災害対策から最先端の技術開発まで、幅広い分野でその価値を発揮しています。ここでは、具体的な活用シーンと国内の導入事例を詳しく見ていきましょう。
5.1 活用シーン1 災害対策やバックアップ拠点
コンテナ型データセンターが最もその真価を発揮するシーンの一つが、BCP(事業継続計画)やDR(災害復旧)を目的としたバックアップ拠点としての活用です。
地震や水害などの自然災害が多発する日本において、企業のITシステムをいかにして守り、事業を継続させるかは経営上の最重要課題です。従来の建物型でDRサイトを構築する場合、土地の確保から建物の建設、設備の導入までに長い期間と莫大なコストがかかるという問題がありました。
しかし、コンテナ型データセンターであれば、工場で製造されたコンテナを現地に輸送・設置するだけなので、数ヶ月という短期間でDRサイトを構築できます。また、本社やメインのデータセンターから地理的に離れた場所に設置することで、大規模災害発生時の同時被災リスクを大幅に低減させることが可能です。災害発生後、メインサイトが機能停止に陥ったとしても、迅速にDRサイトへシステムを切り替えることで、事業への影響を最小限に抑えられます。
国内では、この利点を活かした導入事例が数多く報告されています。
| 導入団体・企業 | 導入目的 | 概要 |
|---|---|---|
| 島根県松江市 | 災害対策・行政サービスの継続 | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)が提供するコンテナ型データセンター「IZmo(イズモ)」を導入。自然災害が比較的少ないという地理的優位性を活かし、庁舎から離れた場所に設置。災害時にも住民情報などの重要データを保護し、行政サービスを継続できる体制を構築しました。これは、自治体におけるBCP対策の先進的な事例として知られています。 |
| 大手製造業 | 生産管理システムのDRサイト | 国内の主要生産拠点が被災した場合に備え、遠隔地の遊休地にコンテナ型データセンターを設置。メインサイトとデータを同期させることで、万が一の際にも生産ラインの停止時間を最短に抑え、サプライチェーンへの影響を最小化する体制を整えています。 |
5.2 活用シーン2 工場や店舗でのエッジコンピューティング基盤
5Gの普及やIoTデバイスの増加に伴い、データが発生する「現場(エッジ)」で情報を処理するエッジコンピューティングの需要が急速に高まっています。コンテナ型データセンターは、このエッジコンピューティングを実現するための理想的なインフラ基盤として注目されています。
例えば、スマートファクトリーでは、製造ラインに設置された大量のセンサーやカメラから膨大なデータがリアルタイムに生成されます。これらのデータをすべて遠隔地のクラウドに送信していては、通信の遅延(レイテンシ)によって即時的な異常検知や品質管理が困難になります。そこで、工場の敷地内にコンテナ型データセンターを設置し、現場でAIによるデータ解析を行うことで、ミリ秒単位での高速なフィードバックが可能になります。
同様に、スマートストアでは、店舗の駐車場などに設置したコンテナ型データセンターがAIカメラの映像を解析し、顧客の動線分析や商品の欠品検知、無人レジシステムなどを低遅延で実現します。このほか、建設現場での建機自動制御や、病院での医療画像のAI診断など、様々な分野での活用が期待されています。
省スペースで設置場所の自由度が高いコンテナ型データセンターは、データ発生源のすぐそばに高性能なITリソースを配置できるため、エッジコンピューティングの要件と非常に相性が良いのです。
5.3 活用シーン3 研究開発や実証実験の臨時インフラ
大学や企業の研究開発部門では、AIの機械学習や大規模な科学技術計算、シミュレーションなど、一時的に膨大なコンピューティングリソースを必要とするプロジェクトが数多く存在します。しかし、プロジェクト期間が限定的であるにもかかわらず、恒久的な建物型の計算センターを建設するのは投資対効果の面で非効率でした。
このような課題に対し、コンテナ型データセンターは最適な解決策を提供します。必要な期間だけ高性能なサーバーやGPUを搭載したコンテナをレンタルまたは購入し、研究施設の敷地内などに臨時インフラとして設置できます。これにより、初期投資を大幅に抑制しながら、最先端の研究開発に必要な環境を迅速に手に入れることが可能です。
プロジェクトの進捗に応じてコンテナを追加して性能をスケールアップしたり、プロジェクト完了後には撤去・移設したりすることも容易です。この柔軟性とコスト効率の高さから、以下のようなシーンで活用が進んでいます。
- 大学の研究室における気象シミュレーションやゲノム解析
- 自動車メーカーによる自動運転技術のAI開発基盤
- IT企業による新サービスの開発や実証実験(PoC: Proof of Concept)環境
実際に、IIJは移動可能なコンテナ型データセンター「co-IZmo(コイズモ)」を提供しており、顧客の拠点に一定期間設置して実証実験を支援するサービスを展開しています。このように、コンテナ型データセンターは、未来のテクノロジーを創造するための「移動する研究室」としての役割も担い始めているのです。
コンテナ型データセンター導入検討時のポイント
コンテナ型データセンターは、従来のデータセンター構築とは異なる特性を持つため、導入を成功させるにはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、具体的な検討段階で必ず確認すべき3つのポイントを、詳細に解説します。
6.1 自社の目的と規模を明確にする
コンテナ型データセンターの導入を検討する最初のステップは、「なぜ必要なのか」「どの程度の規模が必要なのか」を徹底的に明確にすることです。目的が曖昧なままでは、最適な製品選定や投資対効果の算出が困難になります。
まずは、以下のような導入目的を具体的に洗い出しましょう。
- BCP/DR対策: 主要拠点から地理的に離れた場所に、災害復旧用のバックアップサイトを迅速に構築したい。
- エッジコンピューティング: 工場や店舗など、データ発生源の近くにデータ処理基盤を設置し、低遅延のサービスを実現したい。
- データセンター拡張: 既存データセンターの電力やスペースが逼迫しており、短期間で処理能力を増強したい。
- 一時的な利用: 特定の研究開発プロジェクトや、イベント期間中だけ高性能なコンピューティングリソースを確保したい。
目的が明確になったら、次に必要な規模を定義します。搭載するサーバーやネットワーク機器の台数、1ラックあたりの消費電力(kW)、将来的な拡張性などを考慮し、必要なスペックを算出します。これらの要件をRFI(情報提供依頼書)やRFP(提案依頼書)として文書化することで、各ベンダーから精度の高い提案を引き出すことが可能になります。
6.2 国内の主要なベンダーとサービスを比較する
国内においても、多くのITベンダーが特色あるコンテナ型データセンターソリューションを提供しています。ベンダーごとに強みや提供形態が異なるため、自社の目的と要件に最も合致するパートナーを見つけることが重要です。
製品を比較検討する際は、初期費用やスペックだけでなく、以下の多角的な視点を持つことが求められます。
- 冷却方式: 空冷式か、より高密度な実装が可能な水冷式か。設置場所の環境や搭載機器の発熱量に応じて選択します。
- 提供形態: 筐体のみを販売するモデルか、サーバーや電源、冷却設備までを統合したオールインワンモデルか。また、運用保守まで含めたマネージドサービスの有無も確認しましょう。
- 耐環境性能: 沿岸部の塩害対策や、寒冷地・猛暑地での安定稼働を保証する設計になっているか。
- セキュリティ: 物理的なセキュリティ機能(監視カメラ、入退室管理など)はどのレベルまで標準装備されているか。
- サポート体制: 導入支援から、障害発生時の対応、メンテナンス体制は充実しているか。
以下に、国内の主要ベンダーとその特徴をまとめました。詳細な仕様は各社の公式サイトで必ず確認してください。
| ベンダー名 | 製品/サービス例 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 株式会社インターネットイニシアティブ (IIJ) | co-IZmo/I | クラウドサービスとの高い親和性。モジュールを連結して拡張できる柔軟な設計。運用ノウハウも豊富。 |
| 日本電気株式会社 (NEC) | マイクロデータセンター | 省電力性能と独自の冷却技術に強み。工場や屋外など過酷な環境への設置を想定した高耐久モデルも展開。 |
| 富士通株式会社 | FUJITSU Data Center Facility-in-a-Box | サーバーから空調、電源、セキュリティまでをワンパッケージで提供。短期間での導入と運用開始を重視。 |
| 株式会社日立製作所 | モジュール型データセンター | 高いエネルギー効率(PUE)を追求した設計。日立グループの幅広い製品群との連携ソリューションを提案。 |
単に製品の価格やスペックを比較するだけでなく、自社の既存システムとの連携性や、長期的な運用を見据えたサポート体制まで含めて総合的に評価することが、最適なベンダー選定の鍵となります。
6.3 遊休地の利活用を検討する
コンテナ型データセンターの大きなメリットの一つが、設置場所の自由度の高さです。自社が保有する工場の敷地、事業所の駐車場、ビルの屋上といった遊休地を有効活用することで、土地取得のコストを大幅に削減できる可能性があります。
ただし、遊休地を活用する際には、事前にクリアすべき課題がいくつか存在します。
6.3.1 インフラ設備の確認
データセンターを稼働させるには、十分なインフラが必要です。特に以下の3点は必須の確認項目です。
- 電力供給: 必要な電力を安定的に供給できるか。高圧受電設備の有無や、増設の可否、コストを確認します。UPS(無停電電源装置)や自家発電設備の設置も検討しましょう。
- ネットワーク回線: 高速・大容量の通信回線を引き込めるか。複数の通信キャリアの回線を冗長構成で引き込めることが理想です。
- 給排水設備: 水冷式のモデルを導入する場合、冷却水を供給・排水するための設備が必要になります。
6.3.2 法規制と条例のチェック
コンテナ型データセンターの設置は、様々な法規制の対象となる場合があります。特に「建築基準法」において、コンテナが「建築物」とみなされるか否かは、設置方法や用途によって判断が分かれるため、必ず所轄の特定行政庁や建築士などの専門家への確認が不可欠です。 その他、消防法に基づく消火設備の設置義務や、自治体独自の景観条例なども事前に調査しておく必要があります。
6.3.3 搬入経路と地盤の調査
コンテナは大型トレーラーで輸送され、クレーンで設置されます。そのため、設置場所までの搬入経路に十分な道幅があるか、クレーン車が作業できるスペースを確保できるかを確認しなければなりません。また、コンテナ本体と内部機器の総重量は数十トンに及ぶため、設置場所の地盤がその荷重に耐えられるか、必要に応じて地盤改良工事が可能かも重要な検討ポイントです。
まとめ
コンテナ型データセンターは、DX推進によるデータ量の急増やエッジコンピューティングの需要拡大を背景に、従来の課題を解決する次世代インフラです。最大のメリットは、短納期・低コストでの構築、柔軟な拡張性、高いエネルギー効率にあります。災害対策や事業継続計画(BCP)にも有効で、企業の多様なニーズに応えます。導入を成功させるには、自社の目的を明確にし、設置環境や物理セキュリティ対策を十分に考慮した上で、最適なベンダーを選定することが重要です。
Zerofieldでは、マイニングマシンの提供やデータセンターでの運用支援など、再生可能エネルギー事業者向けのマイニング導入支援サービスを提供しています。効率的なマイニング環境の構築や売電コストにお悩みのある方は、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業経営者に向けて、暗号資産マイニングマシンやAI GPUサーバーを活用した節税対策・投資商材に関する情報発信を行っています。
あわせて、AI活用やDX推進を検討する企業担当者に向け、GPUインフラやAI開発に関する技術的な解説も提供し、経営と技術の両面から意思決定を支援します。