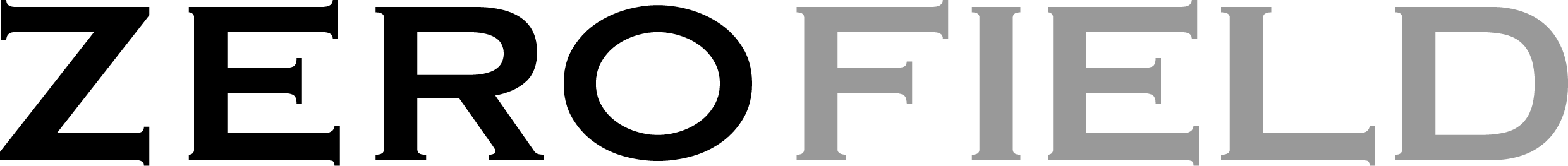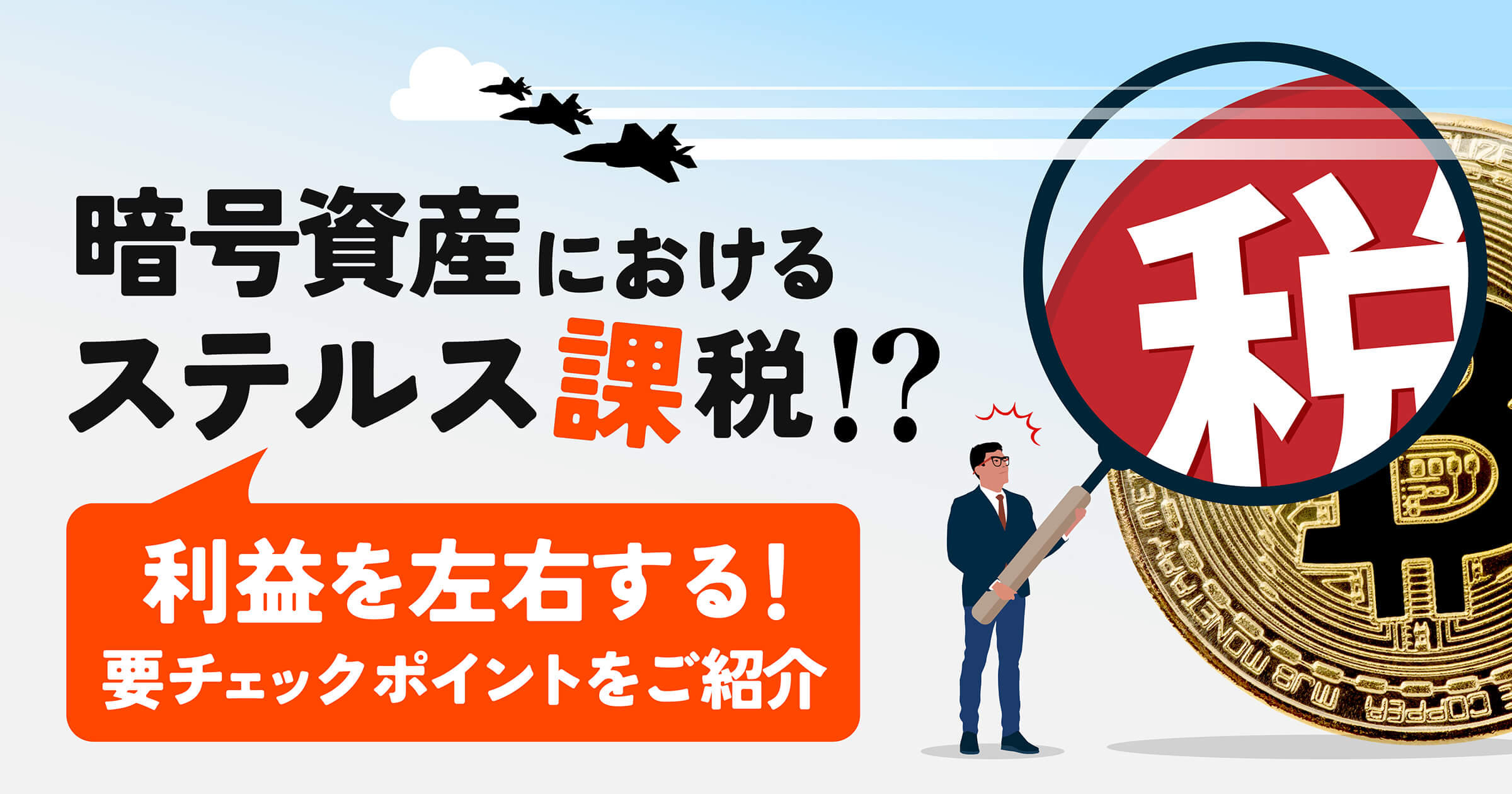暗号資産を法人として保有・運用する企業が増えるなか、「税金」に関する理解は欠かせません。
節税効果を最大限に活かすためにも、仕組み・タイミング・実務対応を体系的に押さえておくことが重要です。本記事では、法人向けの暗号資産税務の基本から最新動向までをわかりやすく解説します。
はじめに──法人で暗号資産を持つと、なぜ「税金」が重要になるのか?
暗号資産を保有する法人が増加するなか、その運用とともに重要になるのが「税務管理」です。知らずに課税対象となるケースもあるため、基礎知識の把握が不可欠です。
近年、法人でビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)を保有・運用する企業が増えています。投資収益の一環としてはもちろん、取引先との送金、ブロックチェーン技術の導入準備など、背景はさまざまです。
しかし、個人と異なり法人が暗号資産を保有する場合、税金の取り扱いには多くの注意点があります。たとえば、取得時点や期末の時価評価、売却益に対する法人税など、知らずに行動すると大きなリスクになることも。
法人の暗号資産にかかる税金の基本
法人が暗号資産を取得・保有・売却する際の税務処理には明確なルールがあります。個人との違いや、課税タイミングについて基礎から解説します。
2-1. 法人と個人で異なる課税の仕組み
まず押さえておきたいのは、「法人と個人では課税体系が異なる」という点です。
- 個人の場合:暗号資産による利益は「雑所得」として総合課税。最大税率は住民税含めて約55%にもなるケースがある。
- 法人の場合:暗号資産の売却益や評価益は、他の事業収益と合算して法人所得となり、法人税等(中小企業で約23%前後)が課されます。
つまり、法人での暗号資産運用は個人よりも税率が抑えられ、経費処理も柔軟に対応可能というメリットがあります。
2-2. 取得・保有・売却それぞれのタイミングでの税務処理
法人が暗号資産を扱う際には、以下の3段階で異なる税務処理が発生します。
- 取得時:取得価額(時価または取得対価)で資産計上。取得手数料等は取得原価に含められます。
- 保有時:期末には評価替えが必要。期末時点の時価と取得価額に差がある場合は、「評価益・評価損」として損益計上されます。
- 売却時:売却価額と帳簿価額の差額が利益または損失となり、法人所得の計算に反映されます。
このように、単に売却時だけでなく「保有しているだけでも」税務処理が発生する点は、特に注意が必要です。
2-3. 決算期末の時価評価のルール
法人税法では、暗号資産は「時価評価」する資産として分類されており、毎期の決算時には必ず「保有分の時価評価」が必要です。
時価の算定には、取引所が公表するレートを基準にします。どの時点の価格を用いるかは会計方針によって異なりますが、継続して一貫した方法を取ることが求められます。
例えば:
- 決算日の終値(最終取引価格)
- 平均値(終値の平均など)
この評価替えによって生じる損益も、課税所得の計算に含まれるため、含み益に対しても課税される可能性がある点には十分留意しましょう。
よくあるケース別の課税パターン
法人が暗号資産を運用する際には、実際の取引内容に応じて異なる税務処理が求められます。代表的なケース別に、課税ポイントと注意点を整理します。
3-1. 長期保有していた暗号資産を売却した場合
暗号資産を数カ月〜数年保有し、その後値上がり時に売却した場合、売却益がそのまま法人の所得として課税対象となります。
この際の課税計算は以下の通りです:
売却益 = 売却価格 − 帳簿価格(取得原価または前期末の評価額)
なお、期末評価によってすでに含み益を計上している場合は、実際の売却益は帳簿価格との差額になる点に注意が必要です。
3-2. マイニングやステーキングで得た暗号資産の場合
法人がマイニングやステーキングによって暗号資産を取得した場合、それは**「役務提供の対価」や「雑収入」**として扱われ、取得時点の時価で法人所得として計上されます。
この収益は売却していなくても計上が必要であり、取得直後に値下がりしても課税は逃れられません。そのため、受領直後の売却や評価替えの判断が利益管理に大きく影響します。
3-3. 取引所間の移動や他通貨への交換時の注意点
一見課税がなさそうに思える「ウォレット間の移動」や「他の暗号資産への交換」も、実は課税対象となる場合があります。
- A取引所 → B取引所 へ送金(価格変動あり) → 評価差が発生すれば、帳簿上の損益が発生する可能性あり。
- BTC → ETH へ交換 → 一度BTCを売却したとみなされ、BTCの売却益に対する課税が発生。
こうしたケースでは、“交換”や“移動”といった行動自体が課税トリガーとなるため、安易な取引には要注意です。
法人での暗号資産管理における注意点
税務リスクを最小限に抑えるためには、記録・証憑管理・ガバナンス体制の整備が不可欠です。実務的な対応ポイントを整理します。
4-1. 帳簿記録・証拠保存の義務とツール活用
法人は、税務申告においてすべての資産取引を帳簿に記録し、証憑を5〜7年間保存することが義務付けられています。暗号資産も例外ではありません。
取引履歴の取得・管理は手作業では難しいため、以下のような暗号資産専用の会計支援ツールの導入が有効です:
- cryptact(クリプタクト)
- Aerial Partners(クリプトリンク)など
こうしたツールを活用することで、自動計算・記録の正確性・税務対応の負荷軽減が可能になります。
4-2. 税務調査で指摘されやすいポイント
暗号資産を保有する法人に対する税務調査は年々増加傾向にあります。よくある指摘例には以下のようなものがあります。
- 取得原価の不明確さ(出所不明のコイン)
- 評価替えの不統一(決算期ごとに評価方法がバラバラ)
- 課税タイミングの誤認(交換・送金時の課税漏れ)
これらはすべて、帳簿記録と税務理解のズレによって発生するため、専門家との連携や継続的な確認が重要です。
4-3. 税理士との連携と社内ルールの整備
暗号資産に詳しい税理士はまだ多くありません。既存の顧問税理士が対応困難な場合は、暗号資産対応を掲げる専門事務所との連携も検討する価値があります。
また、社内でも次のようなルール整備が必要です:
- ウォレット管理のガイドライン
- 取引の事前承認プロセス
- 評価ルールの会計方針としての明文化
これにより、内部統制を保ちながらも柔軟な資産運用が可能になります。
暗号資産に関する法人税制の未来
暗号資産に関する法人税制は、国内外の制度改正や新たな技術トレンドとともに常に進化しています。今後の方向性を見据えることで、長期的な資産戦略のヒントが見えてきます。
5-1. 国際的な動向と日本の制度の変化予測
暗号資産の税制は国によって大きく異なります。たとえば、シンガポールでは法人のキャピタルゲインに非課税措置がある一方、日本では含み益に対しても課税されるという違いがあります。
これまで日本では、暗号資産は「貨幣」ではなく「資産」として扱われてきましたが、世界的なガイドライン整備が進む中で制度の見直し機運が高まりつつあります。
- 2023年には自民党のWeb3プロジェクトチームが「法人課税の見直し」を提言
- 2024年には税制改正により、企業が発行する自社トークンに一定の保有免除が適用
今後さらに、実利用を前提とした保有や、中長期視点の投資に対しては優遇措置が進む可能性があります。
5-2. 税制優遇や見直しの可能性
現在の課題として最も多く挙げられるのが、「期末評価による含み益課税」です。企業にとって、実際に利益を得ていない段階での課税はキャッシュフローを圧迫する要因となります。
この点に関しては、以下のような見直し案が議論されています:
- 長期保有分の含み益課税の繰延べ
- 自社発行トークン保有分への非課税措置
- 一定額以下の暗号資産売却益に対する簡易課税制度
これらが実現すれば、より多くの法人が暗号資産を「安定的に保有・活用」できる環境が整うと期待されます。
将来的なインフラ投資との関連性
将来的には、暗号資産を「通貨」としてだけでなく、インフラ投資の構成要素として組み込む企業も増える可能性があります。たとえば:
- マイニング設備への投資によって、税務戦略+資産形成を同時に実現
- 分散型データセンターとしてブロックチェーンノード運用を行う法人
こうした流れは、税制・会計制度の整備とともに“新しい投資文化”として形成されていくでしょう。
税務を理解して、暗号資産を「攻めの資産」に変える
暗号資産の税務知識は、法人経営においてリスクヘッジだけでなく、戦略的な資産形成にもつながります。基礎知識の習得が、新たな成長のチャンスを生み出します。
暗号資産の保有や取引には、単なる価格変動リスクだけでなく、「税務リスク」も大きく関わってきます。
しかし正しく理解し、管理体制を整備した上で運用すれば、それは大きなアドバンテージとなります。
特に法人においては、次のような形で活用することが可能です:
- 決算対策を見据えた節税資産
- 資産多様化の一環としての中期保有
- マイニング設備を含むインフラ投資との連動
“知っているかどうか”が、そのまま利益の差につながるのが暗号資産の世界。
本記事を通じて、法人での活用を検討する際の土台を築いていただけたら幸いです。
まとめ──マイニングと税務対策を組み合わせた法人戦略をお考えの方へ
暗号資産の取り扱いにおける税務対応は、適切なパートナーと進めることで大きな安心と成果につながります。ご検討中の方へ、弊社サービスをご案内いたします。
Zerofieldでは、マイニングマシンの提供や導入後の運用サポート、さらに税務面でのアドバイスを含めたトータルサポートを提供しています。
特に、4年減価償却を活用した節税対策に関心のある企業様に対しては、最適な導入プランや具体的な税務戦略をご提案しています。
効率的なマイニング環境の構築や、税務面でのご相談がございましたら、ぜひ【資料請求】よりお気軽にお問い合わせください。
投稿者

ゼロフィールド
ゼロフィールド編集部は、中小企業の経営者や財務担当者の方に向けて、実践的な節税対策や経営に役立つ情報をお届けしています。私たちは、企業の成長をサポートするために、信頼性の高い情報を発信し続けます。中小企業の皆様が安心して経営に取り組めるよう、今後も価値あるコンテンツを提供してまいります。